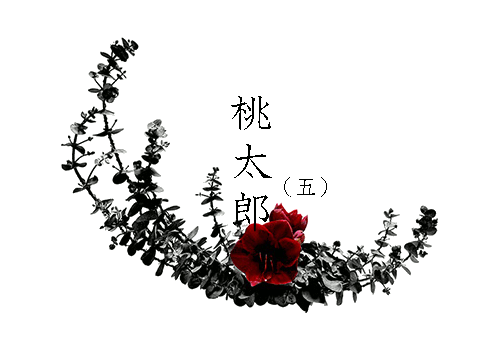
緑の、においがする。
あたたかくて、ここちいい。
まだ眠っていたいなどと思うのは、はじめてだ。
眠るのは、怖かった。
いつ何時敵襲があるかわからないから、自然と眠りは浅くなった。
そしていつも、夢を見た。
屍の山を歩く夢だ。これまでに己がその生命を奪ってきた、屍の。
近頃はとんと見なくなった夢だった。そのことに理由があるならきっと。
きっとあの、笑顔のおかげ。
「――ッ!!」
記憶の中の鳶色の双眸に見つめられて、の意識は急速に覚醒した。
がばりと身を起こして、うなじに走った鈍い痛みに眉をひそめる。
「っ、」
右腕を持ち上げて、うなじに触れる。傷などは無いようだ。
「・・・・・・、」
自分の姿を見下ろす。褥の上だった。素肌に夜着のような、簡単な白い小袖を着ている。袴が無い。
刀は、どこだ。
無意識のうちに手探りで刀を探していて、しかし見つからなくて、視線を走らせる。
・・・・・・ここは、どこだ。
どこかの屋敷のようだった。
板張りの床も同じ板の壁も、相応に年月を経たものと思われるが清潔だ。壁の一面は天井から吊られた御簾で、向こうが見えない。の背後の壁には、高いところに明り取りの窓があって、そこから青白い光が差し込んでいて仄明るい。木々の葉擦れのざわざわという音、そこに混じる虫の音、――今が夜だと、知れた。
「痛むか?」
唐突に声がかかって、はびくりと肩を震わせた。
恐る恐るというようにそちらに首を巡らせれば、御簾を持ち上げて幸村が入ってくるところだった。戦装束を解いた、こちらも簡単な小袖姿だった。
「・・・・・・」
その姿を見て、記憶が繋がり始める。
そうだ、鬼ヶ島に辿りついたのだ。そこに現れた、人に化ける鴉。おそらくは彼の手で、自分は意識を失った。
「申し訳ござらぬ、あの者は加減を知らんのだ。きつう言いつけたゆえ、お許しくだされ」
そう言って幸村が頭を下げるのを、は無言で見つめる。
この男は、――いったい、何だ。
「丸一日以上眠っておられたのだ、喉は乾いておられぬか。茶を用意したゆえ、」
言われてみれば、かすかに痛みを覚えるほど、喉が渇ききっていた。
幸村が差し出したのはどこか温かみの感じられる陶器の椀だった。受け取ってみると、中の茶は飲みやすく冷まされていて、はそれを一息に飲み干す。
喉の奥に浸みこむような、感覚。
「・・・・・・おいしい」
甘いようにすら感じられる茶で、飲んだ後に花のにおいが薫った。
「それはよかった」
空になった椀に、幸村は手にしていた急須から茶を注ぐ。今度は一息に飲むことはせず、一口飲んでから、は幸村を見つめた。
「・・・・・・わたしは、貴方に聞かなければならないことがある」
の声に、幸村は急須を床に置いていた盆に戻して、居住まいを正す。
「俺も、そなたに言わねばならぬことがある」
その優しげな、鳶色の双眸を見つめて、は腹に力を入れる。
幸村の隣は楽しくて、暖かくて、居心地が良くて。
――だがそれは、幸村が、「ひと」であったときのこと。
「・・・・・・、」
緊張からか、心の臓がとくとくと音をたてている。は、と口から漏れた息が、わずかに震えた。
――気圧されるな。
刀は無いが、体術の心得はある。戦う術がないわけではない。
大丈夫だ。眼の前のこの男が鬼ならば、
・・・・・・わたしは、この男を、――殺せる、はずだ。
まずは落ち着かなければ、そう思って、茶をぐいとあおる。
そうして見据えたの視線の先、幸村がすいと立ち上がった。
「の聞きたいこと、それは俺のことであろう」
しゅる、と帯を解く音、ぱさりとその小袖が床に落ちる。
差しこむ月光に、幸村の、よく鍛えられた身体が照らされている。
その、双眸が。
――黄金色に、光る。
「!!」
が眼を見開くその視線の先、幸村の身体に変化が起こった。
ざわりと、幸村の腕や足が、毛に覆われていく。金と黒の縞のような毛皮だ。
耳も同じく毛に覆われ、頭の左右に伸びてぴんと立つ。
手足の先はまるで獣のように、伸びた爪が鋭く光る。
そして完全に毛皮に覆われた背からするりと伸びる、長い尾。
顔や身体のつくりは幸村のままだったが、これでは、まるで。
自失から立ち直って、は腰を浮かせる。
「やはり貴方が、鬼だったのだな」
ゆるりと、幸村がこちらに視線を流した。
「ヒトは、己とは異なる得体の知れぬモノを鬼と呼ぶ。ならば俺も、その括りに入ろうな」
「では、村々を焼き払い、略奪したというのも、貴方が」
「それは違う。アレはの言うていたとおり、ヒトの為したことだ。同族殺しはヒトの生業とはいえ、惨たらしいことだ」
寂しげに笑む、その顔に、は眉を跳ね上げた。
「だが!この島に赴いた者は帰らなかったと聞く、あれは!」
「それは仕方あるまい。この姿を見てヒトは恐れをなし、危害を加えんとする。そうすれば俺は、それらを食わねばならぬ」
生きて返して禍根を残すわけにはいくまい、そう続ける幸村の口元、犬歯が牙のように鋭く大きくなっていることに気が付く。
そして唇を舐める、ひとのものよりも長い、舌。
「――っ、」
人外のものを目の当たりにして、しかしこころが凪いでいくのを、は感じた。
そう、この男が、鬼であるのならば。
この男を、殺さなくては。
それが、己の、生きる理由。
冷えた頭が、眼前の男を殺すために動き出す。まずは武器になるものを探さなくてはならない。ここには何もない、御簾の向こうなら何かあるだろうか――
――立ち上がろうとして、膝がかくりと折れた。
「何、だ、」
力が入らない。息が上がる。身体が熱い。肌が、ひりつくようだ。
「ああ、効いてきたのだな。大丈夫だ、暴れなければ痛いようにはせぬ」
こちらに歩み寄った幸村が、の手から空になった椀を取り上げた。の腕は為されるがまま、満足に自分で動かすことも叶わない。
「・・・・・・は、ずいぶんと他人に気を許すようになったのだな」
「・・・・・・?」
視線だけを強くして、幸村を睨む。
黄金色の眼が、すうと細められる。
「受け取ったものを、確認もせずに飲むなど」
「っ、」
その言葉で、悟る。
先ほどの茶。
「毒ではないから安心なされよ。――壊してしまうわけには、いかぬゆえ」
「・・・・・・、な、ん・・・・・・?」
たいした抵抗もできないまま、片手での両手を押さえ、片手で背を支えながら、幸村がのしかかってくる。
「そなたが俺を殺そうというなら、俺はそなたを食わねばならぬ」
「く、っ!」
足も押さえつけられていて動かせない。そもそも力も入らない。
自由に動くのはもはや眼だけだった。
負けるものか。
最期の最後まで、屈するものか。
力の限りに睨みつけながら、震える口を動かす。
「わたしを、・・・・・・騙して、いたのか」
騙すなどということとは無縁の男だと思っていた。
この男にはどこか、人間らしからぬ、俗世離れしたところがあった。
――この男のそういうところに、自分は、好意をもった、はずだった。
よく考えればすぐわかることだ、人間らしからぬのは当然だった。
この男は、鬼なのだから。
の言葉に、幸村がきょとりと眼を丸くした。
「俺は嘘を言ったことはないぞ、言うたはずであろう。俺はそなたの傍にいると。その、見返りに」
幸村の顔が近づく。
この距離になれば、黄金の色の眼を縁取る睫毛も金茶色なのだと、気付く。
その眼から、視線を逸らすことが、できない。
「――そなたを喰ろうてやろう」
はじめに、口を塞がれた。
口吸いなどという生易しいものではなく、文字通り幸村の口はの口を塞いで、長い舌がの喉の奥をくすぐった。舌がざらざらと感じられるのは、獣のものだからだろうか。
「――ん、ぐ・・・・・・ッ、」
息が苦しい。閉じられない口の端から唾液が垂れていく。
解放されるころには、心の臓がばくばくと暴れていた。
ざらりとした舌が、頬から耳へ、首筋へと動いていく。
身体中が熱くて、どこを触れられてもその刺激が全身に、それこそ爪の先まで走り抜けていくような気がする。
口からは意味不明な声が漏れ、身体が己の意思とは関係なく跳ねる。
思考が、混乱する。
幸村はを喰らうと言った、ならば今身体じゅうを舐められているのはいわば味見といったところか。
「――あ、ぅあ、」
肌が、ざわつく。舌が触れて行ったところが、疼く。
何だ、これは。
痛みになら、慣れている。
痛みになら、いくらでも耐えられし、あるいは諦めることだって、できる。
喰らうというならば、腕でも足でも、その爪で裂いて、牙で食い破ってくれればいいのに。
触れられたところが、もどかしいとすら感じる。
腹の奥が、きゅうと戦慄くような、感覚。
「ひ、・・・・・・ぅ、あ」
やがて、するすると降りて行った幸村腕が、の両足を掴む。帯の緩んだ小袖はほとんど身体を覆うという意味を為していない。食い込んだ爪に痛みを覚える、割り開かれた足の間に、その股ぐらに幸村が顔を寄せる。
「何を、ッ、やめ・・・・・・!」
「・・・・・・濡れておる」
それまで無言だった幸村の、低い声が聞こえる。
誰にも、それこそ自分でも見ることのない場所だ。あまりの羞恥に、もがこうと足を動かそうとして、太ももに鋭い痛みを覚えた。ぎちりと食い込んだ、幸村の爪だ。
「ああ、」
気付いたように、爪がそこから退いて、かわりにざらりと舌が舐めていく。
「っ、」
その感触だけでぞわぞわと背筋が震えるようだった。
「血が出てしまった。動いてはならぬぞ、。ヒトの身体は脆いのだから」
もう一度、舌が傷口を擽る。
「ひ、」
「うむ、の血は甘い。・・・・・・こちらも、甘そうだ」
足の付け根、じくじくとした疼きが燻るそこに、幸村が口を付けた。
「――ッ・・・・・・!!!」
とたん、の身体が跳ねて、声にならない悲鳴が喉を震わせる。
さきほどまでの比ではない。
熱くて、溶けるのではないかと思う。
ずるりと、舌が中に入り込む。
腹の奥。
ずっと戦慄いていた、そこへ舌が伸びる。
「ひ、あ、やぁ、―――ッ!!」
がくがくと暴れるの足を、幸村の腕が押さえつけている。時折痛みが頭を掠めて、爪が肌を破っているのだろうと思うが、もはやその程度の痛みは意識の外だ。
ざらざらと、入り口を舌が行き来する。
まさかそんなところから食べられるとは思っていなくて、の思考はさらに混乱していく。
いかに常人より長い獣の舌とはいえ、腹の奥の「そこ」には届かない。
それがどうしようもなくもどかしい。
これまで感じたことのなかった何かが身体じゅうを包んでいるようで、どうしてよいのかわからない。
身体が、自分のものではないようで。
「やめ、や、あ、あァ、」
ぴちゃぴちゃという水音が、耳に付く。
やめてほしい。
もっとほしい。
ふたつの感情が、を埋め尽くしていく。
「ふ・・・・・・あ、――あ」
ずる、と舌が抜かれて、その感覚で腰が震えた。
背を支えられて、うつ伏せにさせられる。腰だけ持ち上げられて、幸村が覆いかぶさってくる。
「――よかったか、?」
抵抗するだけの力が無い。褥に押し付けたの口は興奮した獣のように、ふうふうと息を繰り返している。
力の入らぬの両腕を押さえつけながら、幸村はその耳元に口を寄せる。耳孔に、ぬるりと舌を差しこむ。
「ひィ・・・・・・っ」
「、そなたは鬼がいなければ生きてはゆけぬ」
「ふ、あぅ、」
「は、俺がいなければ、生きてゆけぬ」
耳朶を打つその低い声は、の頭に、こころに、浸みるように広がっていく。
「は、俺のものだ」
次の瞬間、ぐずぐずに溶けたの下肢に、幸村の欲が突き入れられた。