西へ西へ、鬼が棲むという島を目指して。
の故郷ではただ、「民を困らせている」という程度であった鬼に関する噂は、進むにつれ具体性を増していた。曰く、ある村は焼き払われて草木一本残らなかった、さらにある村では略奪されて村人は皆殺しにされた、どれもおどろおどろしく恐ろしいものだった。
「桃太郎殿は、鬼を恐ろしいとは思われないのでござろうか」
あるとき幸村にこう問われて、は否と答えた。
「恐ろしいかどうかは、実際に鬼をこの眼で見て決めることだ。確かに鬼の噂はどれも悲惨だ、だがそれが本当に『鬼』によるものなのか、確かめた者はいない」
「しかし、鬼ヶ島に向かったものは戻って来ぬと」
「そうだ、だから鬼の姿を見た者はいない。鬼が本当にそのようなことをするのかどうかということも、わからない。村々を襲ったというのも、それは『人』の手でもできることだ」
「人、が?」
不思議そうに聞き返す幸村を、は真っ直ぐと見上げる。
「戦の世だ。人が村を焼くことも、その村人を殺すことも、何も珍しいことではない」
「・・・・・・では、それらが鬼の仕業ではなかったとして、それでも桃太郎殿は鬼を殺すおつもりなのか」
「無論だ」
はそう、即答した。
「それが我が主の、命である」
そして視線を、左腰の刀に落とす。
「これまでも、幾多の戦場を駆けて、数多の人間を殺してきた。人が鬼になったとて、何も変わりはしない」
それを聞いて、幸村は少し、笑ったようだった。
眉を下げた、どこか寂しげな笑みだ。
「桃太郎殿は、主殿がとても大切なのでござるな」
その言葉に、しかし桃太郎は何も答えなかった。
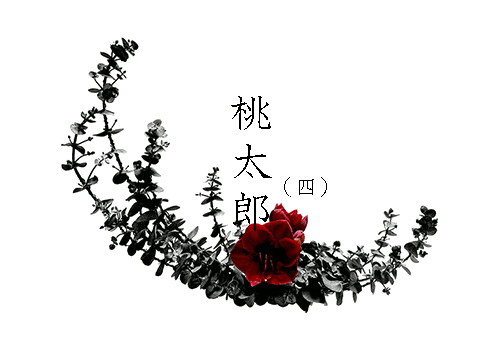
あれよという間に旅路を共にすることになったこの幸村という男は、極度に世間知らずであることや金銭感覚に疎いことが玉に傷ではあったが、総じて悪い男ではなかった。
礼に適った立ち居振る舞いを崩さないし、溌剌とした笑顔で物言う様子は誰の眼にも好感の持てるものである。
そして背の二槍は飾りではなく、幾度か地侍の小競り合いに巻き込まれたときも如何なくその腕前を披露して見せた。その動きはまさに一騎当千、さぞ名のある武人なのだろうと見受けられたが、しかし幸村の素性を、は今も何一つ知らない。
どこから来たのか、どこへ行くのか、鬼ヶ島まで付いてくるつもりなのか、は何も聞かなかった。話し方ひとつとっても相応の身分にあるのだと想像に難くなかったし、何事か理由があって今は自由にしているのだとしても、そのうち自分の前からいなくなるだろうと思っていたからだ。
「・・・・・・いつか、朝が来て貴方がいないということも、あるのだろう」
その夜は野宿で、小さな火を焚きながら、はぽつりとつぶやいた。
「・・・・・・桃太郎殿は、この幸村をそのような恩知らずとお思いか」
隣の幸村がそう言って、は自分の思考が声に漏れたことに気が付く。
暗く静まり返った森だ、火の爆ぜる音がぱちりと響いた。
「いや、違う、だが貴方には貴方の都合もあるだろうと、思っただけのことだ。すまない、気にしないでくれ」
取り繕うようにはそう言って、火の様子を見つめる。
・・・・・・何を考えていたのだろう。
幸村が此処から、――自分の傍からいなくなる、その当たり前のことに、どうして、
――自分は今、狼狽えたのだろう。
「・・・・・・もし本当に、某が急にいなくなったら、どうされるおつもりか」
静かな声だった。
がそちらに顔を向ければ、幸村が真っ直ぐとこちらを見ていた。
「・・・・・・え、」
「そなたの言うとおりに、例えば明日の朝、某の姿がなかったら」
鳶色の双眸が、爆ぜる炎の色を吸って、黄金色に、見える。
「・・・・・・」
その色に、見惚れるように、は言葉を無くした。
そして、彼から視線を外す。
「・・・・・・想像が、難しいな・・・・・・」
言葉を探しながら、は口を開く。
「こんなに長い間、四六時中ともに過ごすのは、貴方が初めてなんだ」
出会った時のこと、不覚にも助けられた時のこと、思い返せばの記憶の中の幸村は、いつも笑顔だ。
「貴方が隣にいると、・・・・・・楽しくて。わたしの旅はもっと惨めなものであったはずなのにな」
の言葉尻に、自嘲が滲んだ。
「惨めとは」
幸村の問いに、一度眼を伏せる。
「・・・・・・以前、鬼退治は主に命じられたのだと、言っただろう」
「そう伺い申した」
「それは嘘ではない。だが真実は、・・・・・・わたしは、主に捨てられたのだ」
「捨てられた?」
「・・・・・・わたしは、さる国の、殿さまに仕える一族の末裔。父には永らく子ができず、一族はそこで途絶えるものと、誰もが考えていたその折、すでに老いて子を成せなかった父の妻は、若い娘を買って、父の子を孕ませた。娘の名は桃、桃がその命と引き換えに産んだ子がわたしだ。待望の赤子はしかし男子ではなかった。おなごは一族を継げない、だからわたしは男子として、母の名をもらって桃太郎として、父の亡きあとも殿さまに仕えてきた」
表情のない顔で、は言う。
「わたしにはそれしか、生きる術がなかった」
老い先の短かった父の妻もそのうちに亡くなった。に残ったのは一族の培ってきたものを守り、そして主君に尽くすという使命、それだけだった。武術を身に付け勉学に励み、ただただ主君の役に立とうとしてきた。
「だが、殿さまにはもう、我が一族は不要だったのだ。一族は父の代で途絶えるとふんで、我らの領地は他の家臣に与えられる予定だったそうだ。それなのに一族を継ぐわたしが現れた。わたしは初めから、殿さまには邪魔な存在だった・・・・・・、それに気が付くのが、遅すぎた」
幼いころから、幾度となく命の危険に晒されてきた。家中の者から刃を向けられたことも、食事に毒を盛られたことも、一度や二度ではない。自分の身は自分で守らなければいけないと、こころと身体に刻んで生きてきた。
――それらが全て、他でもない主君の差し金であったのだと知ったのは、折しも城に上がれとの命令が下る前日のことだった。
今でも思い出す。
あの日、呼び出された城の謁見の間の、寒々しさ。
「わたしを厄介払いするために、殿さまははるか遠方の、実在するのかもわからぬ鬼を退治せよと、お命じになったのだ」
そう命じる主君の、もはやこちらに何の興味も無いというような眼。
「国にはもう、領地も屋敷も何もない」
は俯いたまま、膝の上で拳を握りしめる。
「鬼を、・・・・・・殺すこと。それだけが、わたしが生きる、理由だ」
風が吹いて、木々がさわさわと音をたてた。
黙っての話を聞いていた幸村が、口を開く。
「では、宿願叶って鬼を殺したのち、そなたは如何されるのでござる」
は、俯き加減に炎が揺れるのを見つめたまま、口を閉ざした。
自分でも、理解している。鬼を殺せば最早、生きる意味などないことを。
理解していても、それでもこれ以外に方法は無いのだ。
他に生きる方法を、は知らない。
「――という名は、父上殿がおつけになられたのか?」
唐突に、幸村がそう言った。
は小さく眉を動かして、顔を上げて幸村を見る。
「・・・・・・何故、その名を」
「すまぬ、そなたが寝言で言っていたのを聞いており申した」
しばしの間幸村の鳶色の双眸を見つめて、は視線を外した。
「・・・・・・そうだ、父はわたしを、そう呼んでくれた」
「その名を、某も呼んでもようござろうか」
「・・・・・・好きにしたらいい」
の平坦な声に、幸村はにこりと笑う。
「ならば、にはやりたいことや行きたい場所はないのだろうか?」
その笑顔を見つめながら、はゆっくりと、瞬きをした。
やりたいこと、行きたい場所。
そのようなものは、無い。
考えても、何も出てこない。
「・・・・・・わかっては、いるんだ。わたしはどうしていいかわからなくて、ただ示された道を進んでいるだけ。己の意思などどこにもない、愚かなことだ」
幸村が、怪訝な様子で首を傾げる。
「意思ならば、あるではないか」
「・・・・・・?」
何を言われたのかわからなくて、は幸村を見つめる。
視線の先、幸村が当たり前のことを話すような口調で、言う。
「先ほどは、某とともにいて楽しいと言っていた、それはの意思なのでござろう」
「・・・・・・」
は、口を噤む。何と答えていいのか、わからなかった。
幸村が、そのの顔を覗きこむようにして、笑う。
「だから、某がこうしてずっと一緒におれば、はずっと楽しいのではないか?」
「・・・・・・は?」
耳を疑って、は眉を動かした。
何を言っているのだ。
「ずっと一緒」?
「鬼がの生きる理由なら、鬼がいなくなればは本当にひとりになってしまう、だからこの幸村が、ずっとの傍に在ろう」
「・・・・・・何、を、・・・・・・そもそも、貴方には、然るべき生き方が、帰るところが、あるのだろう」
やっとのことでそう言えば、幸村は笑顔のまま頷く。
「うむ、の隣の此処こそが、某の帰る場所となろう」
言われた言葉を理解するのに、一呼吸分の時間が必要だった。
「な・・・・・・っ、何故・・・・・・!これも団子の恩義とでも言うつもりか」
わずかに頬を赤らめて、は幸村を睨む。
それでも幸村は、穏やかな笑みを絶やさない。
「これまで桃太郎殿の傍に在ったは、団子の恩義にござったが、これからの傍に在るのは、――への恩義にござる」
それを聞いて、は幸村と出会ったときのことを思い出す。
魂を響き合わせることこそ団子を食すときの作法、この恩義に報いなければ団子の魂にも報いえぬ、――そのようなことを、この男は熱弁していた。
は意識して仏頂面を顔に取り戻し、鼻から息を吐く。
「・・・・・・つまり貴方はわたしを食べようとでも言うのか」
幸村は、笑顔のまま、何も答えなかった。
そういえばこの男に皮肉が通じるはずはないのだったと思い至って、は視線を外す。
その口元には、ほんのわずかではあったけれど、笑みが宿っていた。
夜も更けて、月明かりが木々の隙間から差し込んでくる。
火はすでに消してある。身体を丸めて小さな寝息を立てているに身を寄せるようにして眼を閉じていた幸村が、ふいに瞼を持ち上げた。
ひく、とわずかに耳が動く。風のものとは違う、葉擦れの音をひろう。
ゆるりと半身を起こすと、暗闇にいくつもの光が浮かび上がった。
獣の、眼だ。
「・・・・・・ようやく、深く眠れるようになったのだ」
取り囲むようにこちらをうかがっている獣たちに、幸村は静かに言う。
「の眠りの、邪魔を致さんでくだされ」
雲に隠れたか、月明かりが消える。
全くの暗闇の中、
――炎を宿す黄金色の双眸が、ぎらと光る。
それを見て、獣たちは一様に、音を立てずにその場から逃げだしていった。
月明かりが再び、幸村を照らす。
幸村は周囲を満足げに見回して、くあと欠伸をすると、の頬をそっと撫でて、瞼を降ろす。
かくしてその日、ふたりの姿は鬼ヶ島と呼ばれる島の砂浜にあった。
小舟をつけたこの砂浜以外は鬱蒼とした森に覆われた、小さな島である。
「ここが・・・・・・」
呟いて、は左手の親指で刀の鯉口に触れた。
何故だかわからないが、本能のように悟る。
「此処」は、「ひとの領域」ではない。
鳥か獣か、――あるいは鬼しか、踏み入ることを許されない、そう感じる。
ばさりと大きな羽音がして見上げると、一羽の鴉がこちらに飛んでくるところだった。
すぐにでも鬼に出くわすのかと身構えていたは、小さく安堵の息を吐き、
「ったくもー、どこにいってたのさ!」
「・・・・・・!!」
鴉が、人語を話した。
そのことに身構えたは、さらに大きく眼を見開く。
こちらに舞い降りた鴉が、地に降りるその瞬間に、ひとの姿に変化したからだ。
黒い羽を散らして躍り出るように現れたのは、鮮やかな暁の色の髪の、若い男だった。
「出かけるときは帰りの予定を教えて行けって何度言わせンの!?」
鴉とまったく同じ声色でそう言う男を、は視線で追う。
何だ、これは。
まさかこの男が鬼なのか。
――鬼には大きな牙と鋭い爪があるという。爪はともかく、鴉に牙があるのだろうか。
「そりゃアンタが簡単にどうこうなるとは俺様も思ってないけどね!人間に関わったらろくなことになりゃしないんだから、その辺本当にわかってンの?」
そして、漸く思考が追いついてくる。
この男が先ほどから話しかけている、相手は。
「ああもう、すまなかったと言っておろうが!お前最近五月蠅いぞ」
「五月蠅いと思うんなら、行動を改めてくんないかな!」
さきほど、この男は「出かけるときは」と、言った。つまり、「此処」から、外に出たということなのか。
「此処」は、鬼ヶ島。
鬼の、棲む、場所。
「・・・・・・貴方、は・・・・・・」
まさか。
愕然とが見つめる先、鴉だった男が今気づいたと言わんばかりにこちらを見た。
「なぁに、『コレ』」
「客人だ、丁重にもてなせ」
いささか不貞腐れたように、幸村がそう言う。
眼の前の光景が、理解できない。
否、その考えは瞬時に頭に閃いたのだが、それをこころが拒絶しているのだ。
・・・・・・まさか、貴方が。
言葉を失ったに、幸村が笑ってみせる。
「ここは、ようこそおいでくださったと、言うべきなのか」
まさか、そんな。
何か言おうとして、
「ったく、何拾ってきたのさ」
眼前にいるはずの、鴉の男の声が、真後ろから聞こえた。
――うなじに、鈍い衝撃。
「ッ、ぁ」
刀を抜くどころか、気配も何も感じなかった。
ただ急速に、の視界は暗闇に沈んでいった。