その夜、浅い眠りについていた幸村は、ひとの呻き声に目を覚ました。
明かりの無い部屋は暗いが、窓からの月明かりがあるから幸村の眼には室内を見渡せた。
半身を起こしてみると、眠る前に見たときのまま、壁に背を預けて、刀を抱くようにして座って眠る桃太郎がいる。呻き声は彼女の口から漏れ出ていて、うなされているようだった。
そうっと身を起こし、己が被っていた布を手に、桃太郎に近寄る。
その布を、時折小刻みに震える細い肩にかけようとして、
「――ッ!!」
電光石火、跳ねるような動きで桃太郎が立ち上がった。鞘から完全には抜き切っていない刀の刃が、幸村の首に触れたところでひたりと止まっている。
ひゅうひゅうと、喉の奥から息が漏れるような呼吸を繰り返して、青白い顔色の中で双眸だけが狂気じみて光って、幸村を睨みつける。
「桃太郎、殿」
「・・・・・・あ」
幸村の声が届いたのか、瞬きをした桃太郎の眼に生気が戻る。
きん、と刃が鞘に収まる涼しげな音が響く。
ふらりと、桃太郎がこちらを見上げる。
「・・・・・・何だ」
「いや、その。寒いのだろうと、思うて」
持っていた布を差し出せば、桃太郎は力なく首を横に振った。
「不要だ。寒くない」
そのまま視線を落とした桃太郎に、幸村は眉を下げて嘆息する。
そして、ふわりと、その布を桃太郎の肩にかけてやった。
「っ、要らないと言った、」
「明日はまた早くに出立するのでござろう、きちんと眠られた方がよい」
そのまま幸村は踵を返し、桃太郎と反対側の壁際に腰を下ろす。
瞼を降ろせば、桃太郎の身じろぐような衣擦れの音、そして、
「・・・・・・ありがとう」
消え入りそうなその小さな声に、幸村は満足げに口角を上げた。
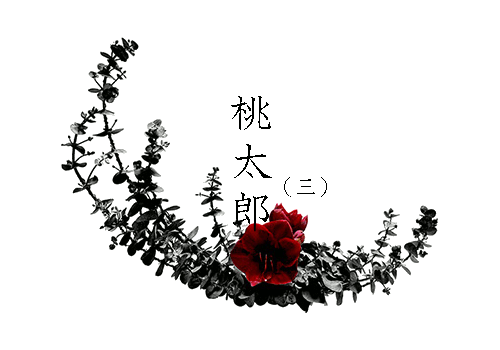
それからしばらくの時が、過ぎた。
前の晩を過ごした宿場町からわずかに進んだところ、街道の端の木陰にたたずむその姿を見つけて、幸村は手を振りながら声をあげる。 「桃太郎殿っ、水をもらってきましたぞ!」
「ああ、手数をかけた、」
駆け寄れば、こちらに気づいた桃太郎がそう言って、わずかに、目元を緩めるのが見えた。
出立前に飲み水を調達するのを失念していて、桃太郎はどこか途中で手に入ればいいとそのまま進もうとしたのを、今日は日差しが強いからと幸村が町に戻って水を手に入れてきたのだ。
幸村が竹筒を差し出せば、桃太郎はそれを受け取ろうと手を伸ばして、そして気づいたように、その手を止める。
それを見て、幸村は「ああ、」と竹筒を引いた。
「申し訳ござらぬ、つい慌てて」
そう言って、竹筒の中身を一口、口に含む。飲み込んでから、改めて桃太郎に竹筒を差し出した。
「・・・・・・すまない」
「こういうときは礼を申すものと、某は思いまするぞ」
「・・・・・・ありがとう」
うむ、とうなずいて、幸村は竹筒を受け取った桃太郎を見つめる。
――桃太郎についてわかったことが、いくつかある。
ひとつは、彼女は常に、周囲をひどく警戒しているということ。
今幸村が持ってきた水をすぐに受け取らなかったのは、毒見をしていなかったからだ。桃太郎は、他人から食べ物や飲み物を受け取らない。初めに同じように水を渡そうとして拒否されたときにそのことに気づいて以来、幸村はいつも彼女の前でまず自分が口に入れて見せてから、それを渡していた。幸村に限ったことではなく、町に立ち寄れば茶屋や宿屋の客引きがあったが、桃太郎は声をかけられてもそれに取りあわず、自分で選んだ店や宿に足を向けている。確かに客を騙すような宿も、世にはあると聞くから、その対応は正しいのかもしれなかった。そして夜になれば、宿にしろ野宿にしろ、眠るときは横にはならずに刀を抱いていて、何か近づけばすぐに反応するのは、すでに幸村が身をもって経験したとおりだ。
そしてもうひとつ、その警戒心からかもしれないが、桃太郎は基本的に他人と関わろうとしない。店や宿などでの必要最低限以外の会話を、桃太郎が他の誰かとしているところを、幸村は見たことがない。だが彼女はひとと会話をしないわけではない。幸村が話しかければいつも答えてくれる。
「それから、桃太郎殿、そのまま動かんでくだされ」
「何だ?」
歩き出そうとしてその足を止めた桃太郎の結い上げた髪に、幸村はすっと手を添える。
「何を、」
「うむ、やはり似合うておりまする」
「?」
桃太郎が懐から鏡を取り出して自分の姿を確認し、そして顔を上げた。
「・・・・・・何の、つもりだ」
表情のない顔で、こちらを見据える。
その髪には、一輪の花が飾ってある。
先ほど水を汲みに行った折に、道端で見かけた花だ。決して大きくも、華やかでもなかったが、桃太郎によく似合っていると、幸村は思う。
「いつだったか、かんざしというものを、教えていただき申した。その花が、かんざしに似ておったゆえ」
「・・・・・・言ったはずだ、簪はおなごが髪を飾るものだと」
「桃太郎殿はおなごにござろう」
「・・・・・・」
幸村がそう言えば、桃太郎はふいと視線を外した。
表情の変化は乏しいが、わずかに眉根を寄せたその表情はしかし、不機嫌ではないのだと幸村は知っている。
このひとは、まるで鏡のように、敵意を向けられれば容赦をしないけれど、こちらが善意を示せば善意で返してくれる。そして行き倒れていた幸村を助けたことを考えれば、決して冷血漢だというわけではない。根はとても優しいひとなのだと思う。
――そして、もうひとつ、これは早いうちに気が付いて、そして幸村が疑問に思っていることがある。
「今日もずいぶんと、急いでおられるのだな」
「先を急ぐと、言ったはずだ」
桃太郎の足取りはいつも早い。体格差を考えれば幸村が付いて行くのに何ら問題ない速さではあるが、この細い身体のどこにそんなに持久力があるのかといっそ感心してしまう。日暮れどきに宿が近くにあれば屋根のある部屋で休むが、そうでなければ山中だろうと野宿を辞さず、ただひたすらに前だけを向いて、鬼退治のことだけを考えているように見える。
何が、彼女をそこまで駆り立てているのだろう。
幸村はそう思いながら、今日も桃太郎の後をついて歩く。
その夜も、宿の部屋で、桃太郎はうなされていた。
握りしめて眠る、その刀の間合いに踏み入れば起きてしまうので、幸村はその外側に腰を下ろして、桃太郎を見つめている。
彼女はずいぶんと眠りが浅いようで、明け方になれば間合いに関わらず幸村が動いた気配で目を覚ます。
そして、夜半にはこうやって、うなされていることが多い。
何の夢を、見ているのだろう。
――ひとの感情の機微はまこと難しいものだと、幸村は思う。
毎日桃太郎の傍にいて、少しは彼女のことが理解できたように考えていたけれど、でもまだまだわからないことだらけだ。
だが、わからないということが、悪いような気はしなかった。
どういうことを考えているのだろう、何が好きだろう、どうしてほしいのだろう。それを考えることは、幸村にとってはとても楽しいことだった。
もっと知りたい。
もっと近づきたい。
ああ、
――・・・・・・腹が、減ったな。
ぼんやりと考えた幸村の耳に、その声が、届いた。
「――ちちうえ・・・・・・、は、・・・・・・」
ひくり、と幸村の耳がわずかに動く。
桃太郎の声だ。俯いたままの彼女の口から届いた、言葉。
・・・・・・「」?
もう少し聞こえるだろうかと幸村が身を乗り出したところで、桃太郎がすいと顔を上げた。
部屋が暗くて顔色はよくわからないが、表情は無い。
虚ろに開かれた眼が、幸村の姿を認めて、ゆるりと瞬きをしてから光を取り戻す。
「・・・・・・何をしている、早く寝るべきだ」
その声が、口調ほど固くないのを感じ取って、幸村は立ち上がる。
迷いなく桃太郎の間合いに踏み入って、そのまま腰を下ろした場所は、彼女の隣。
幸村の動きを目で追っていた桃太郎が、温度の無い声色で、言う。
「・・・・・・何のつもりだ」
「某はここで寝まする」
幸村はそう言って、瞼を降ろす。
生きものは、己の領域に他者が入り込むのを厭うものだ。
桃太郎も、幸村が動かないとなれば、彼女自身が身を起こして離れていくのかもしれない、そう幸村は考えていたけれど、彼女はわずかに身じろいだだけで、結局その場を動かなかった。
着物越しに伝わる彼女の体温が、幸村にはとても暖かく、心地よいものに感じられた。