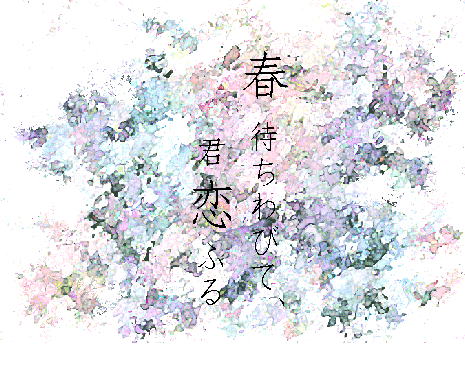
(中編)
陽が暮れて月が昇り始めたころ、大坂城本丸御殿の一室では三成、吉継と幸村が夕餉を終え酒を酌み交わしていた。
「石田殿、大谷殿にも、此度は色々と取り計らいいただき、恐悦至極にございまする」
幸村はそう言って、三成と吉継へ頭を垂れた。
甲斐は躑躅ヶ崎館に前触れも無く豊臣家の使者が現れたのが先月のことだ。
勝頼から呼び寄せられた幸村が躑躅ヶ崎に急行すると、使者が携えていたのは豊臣秀頼からの書状だった。曰く、幸村に官位を授けるという。幸村は驚いたし、武田の家老方には面白く思っていないような向きもあったが、上杉との同盟が評価された結果だと勝頼が判断し、叙任を受けることとなった。
父・昌幸も同じ位階を持ってはいたが、まさか自分もそのような立場になるとは思っていなかった幸村は、朝廷に働きかけてくれた豊臣家と三成に礼をすべく、勝頼に願い出て内々に上京してきたのである。伏見の城では三成と吉継がすでに幼い秀頼との面会の手はずを整えてくれていて、全て滞りなく豊臣の家長と面談ができた。
その後は二人とともに大坂へ移動し、今日は朝から大坂城に詰める要人たちとの顔合わせを行った。政務で多忙だろうに、吉継は一日幸村を伴って回り、先述の要人たちとの取次も取り計らってくれたのだ。それは大変ありがたいことではあったのだが、吉継が何かにつけて「我が娘婿になる男よ」と言って憚らなかったので、その都度幸村は面はゆいような心持になって顔を赤らめたのだった。
頭を下げる幸村に、吉継は目元を笑みの形に歪めた。佐助あたりが見れば、「底が知れない」と評するような笑みだ。
「ヒヒ、そう畏まるな。それにしても長旅ご苦労であった、もっとゆるりとしてゆけばよいものを」
「そうは参りませぬ、東国にももう春がやってきますゆえ。奥州やその周辺国が動き出すとも限りませぬ」
対する幸村は、吉継の表情に裏を読むようなこともせず、当然のようにそう答えた。
それを聞いて、吉継は鷹揚に頷く。
「なるほど、東はぬしらに任せておけば安泰よ。なんとも頼もしき同胞(ほらから)だ、のう三成」
吉継がそう言って傍らを見れば、それまで特に口をはさむでもなく手酌で杯を傾けていた三成が、その鋭い視線を幸村へ向ける。
「……貴様は、上杉を抑えてみせた。それに値する評価をしたまでだ」
「もったいなきお言葉、必ず我が主にも伝えまする」
御館が燃え落ちたあの乱以降、上杉謙信はいよいよ政の表舞台から退いたようだった。はっきりと家督が譲られたわけではないという忍びの報告ではあったが、現在の上杉は景勝を棟梁とした体制が整えられ、混乱から立ち直りつつある。「越後の龍」の血族は健在だ、甲斐武田とともに奥州の伊達や遠州の徳川に睨みを利かせることができるだろう。
これで東の備えは万全。あとは西、――今日一日で聞いたところによれば鎮西の島津・大友、四国の長曾我部と、それぞれ同盟が成立する見通しらしい。中国の毛利とはすでに同盟済みであるのは、石田との同盟前に幸村も佐助から聞いたところである。
そう考えると、日ノ本の趨勢は豊臣に傾いているように感じられた。徳川と同盟しているのは今のところ伊達のみ、数の上ではどう見てもこちらの有利である。
……数の有利が必ずしも戦を決するものではないが。
考えながら杯を口に寄せた幸村を見計らったように、吉継が口を開いた。
「――して、真田の。ぬしから預かりうけておるあの娘ならば、息災であるぞ」
「げほっ」
盛大に酒を吹いた。三成が不快げに眉を動かすのが見える。慌てふためいて懐から手拭いを引っ張り出しながら、幸村は呻くように言った。
「お、大谷殿っ!?」
「うん?今日一日の気がかりはそれではなかったか?」
吉継は至極面白そうに肩を揺らす。
「なに、心配は無用だ、あの娘の性根の太さは本物よ、あれならどこでもやってゆけるであろ」
染みが付かないようにと畳を叩くように拭っていた幸村はそれを聞いて、眉を下げた。
「……左様に、ございまするか」
「そういえば三成は、あの娘に稽古をつけてやったのではなかったか」
「なんと、石田殿が?」
幸村が眼を丸くすると、三成は「フン」と鼻から息を吐いた。
「乞われたからな。あれは、風の使い方がなっていない。動作も判断も全てが遅い。諦めも悪い、……面倒だ」
「と、まァ、このような塩梅(あんばい)よ」
三成の様子が、その言葉ほど棘がないように見えて、幸村は「左様で」と笑む。
はどちらかと言えば、周りの環境の変化に強い方ではない。鎌之助をつけたとはいえ他に知る者のいない大坂の地で難儀しているのではなかろうかと幸村は考えていたのだが、その心配は杞憂に終わりそうだ。
粗相の跡をあらかた拭い終えて一息ついた幸村に、吉継が引きつるように笑う。
「ヒヒ、どうだ?今宵会いに行く気があるなら、この岳父(ちち)が案内してしんぜよ」
「な、……ッ!!??」
今度は酒を噴くには至らなかったが、しかし幸村は眼を白黒させた。
すでに刻は夜だ。こんな時間に男が女の元を訪れるなどというのは、というかそれを(養子とはいえ)父親が扇動するというのは、
「は……っ」
喉元まで出かかった「破廉恥」という言葉をなんとか飲み込むことができたのは、呆れたように三成が酌を置いたからだ。
「……刑部」
窘めるような声色だった。吉継は悪びれもせずにヒヒと笑う。
「いやすまぬ、スマヌ」
多くを語らないが、今のは自分に対する助け船だったのではないかと、幸村は思った。石田三成と言う男は、やはり悪い人物ではない。
「しかし顔くらい見せて行ってもよいのではないか」
笑いを収めた吉継に言われて、幸村はわずかに逡巡した。
「……いいえ、明日は堺の湊を見に行くつもりなれば。明後日も朝には発ちますゆえ」
幸村の答えに、なぜだろうか三成が、ひくりと眉を動かした。
吉継は幾分面白くなさそうな様子で吐息する。
「左様か。ならばあの娘は寂しがろうなァ」
先ほど吉継がを「性根が太い」と言ったことを考えれば、それは皮肉だ。
だが幸村はその言葉を正面から受け止めた。
寂しい思いをさせていることに間違いはないだろう。できることならば予定の隙間を縫ってでも(さすがに夜半に赴くことはできないが)顔を見せるべきなのだろうと思う。だが、今の自分には未だ、その資格は無い。
……すまぬ、。
今少し、耐えてくれ。徳川家康を討ち、天下に誇れる男に成った暁には、必ず迎えに行くから。
幸村は吉継、三成をそれぞれ見据えて、頭を垂れた。
「……ええ、はああ見えて繊細なれば、石田殿、大谷殿、どうぞをよろしゅうお願い申しあげまする」
――風になる、夢をみる。
意識ははっきりとしているのに、己の姿が見えない。手を伸ばしてもそこに腕はなく、ただ、風だけが動く、そのような。
ざあ、という音が鳴る。
葉擦れによく似たそれは、満開の桜の花びらが奏でたものだ。風にのって、吹雪のように、薄紅が舞う。
――ふと、熱を感じた気がして、そちらに意識を向ける。
……桜の木々の向こうに、幸村の、姿が見える。
もう少し近くにと思うが、うまく視線を動かせない。
声をかけようかと考えて、しかし今の状態では口も無ければ声を震わせる喉も無いのだと気付く。
この、風で、わかってくれるだろうか。
バサラの力には、それを扱う術者の色のようなものが滲む。は、幸村の炎を見間違えない。あるいは彼も、そうではないだろうか。
……考えるうち、幸村の傍らに、もうひとり、人物が現れる。
華やかだが決して華美すぎない打掛、背に流れる髪は艶やかで、所作の一つひとつがうつくしい。顔が、ここからではよく見えないが、そのいでたちはどう見ても、名のある家の姫君だと思われた。
幸村が、姫君に、笑いかける。
ああ、ここにいてはいけない。
一刻も早くここを去らなければ。
ざわざわ、ざわざわ、木々の音だけが大きく、耳の周りで渦を巻く。花びらが吹雪のように舞い上がって、視界を遮る。
ここにいてはいけない。どこか遠くへ。どこでもいいから。
早くはやく、この場から、逃げなければ――!
「……、」
視界に薄靄がかかっているようで、幾度か瞬きを繰り返す。
そうすれば見知った天井が見えて、はぼんやりと吐息した。
「……夢か」
喉が掠れて声は出なかった。のそりと身を起こすと、室内を見回す。
まだ夜明けまでに時間がありそうだ。昨夜はなかなか寝付けなかった。この感じでは眠っていたのは一刻ほどだろうか。
脳裏を薄紅の花びらが流れていく。
「……馬鹿だな、わたしは」
幸村の傍にいた、誰もが認めるような姫君。
あれは、己の劣等感が生み出した、幻だ。
自分よりも幸村に相応しい女性が、世にいるのではないかと。
……馬鹿馬鹿しい。
幸村が一言でも、そんなことを言ったことがあったか。
自分で勝手に作り上げた幻に、自分で勝手に嫉妬するだなんて。
本当に、馬鹿だ。
その日、淀は朝早くに大坂城を発ち、京は東山の豊国神社を詣でていた。死後「豊国大明神」として神格化された秀吉が祀られている社で、月に一度は淀も足を運んでいる。伏見の城にも足を伸ばして我が子の様子を見、いつもならばそのまま伏見で一泊するところであったが、今日ばかりは早々に伏見城を辞してきた。予定していたことだったので大坂を出てはきたが、どうにもの様子が気がかりだったからだ。
輿の小窓から外を眺めていた淀は、とある商家の前を過ぎようとしたときに止まるよう指示した。
「いかがなさいました?」
「あそこの、あれ。近くで、見たいわ」
供の侍女に言って、使いを遣ると、商家の旦那が恭しくこちらへやってくる。
旦那が並べる品を一通り眺めて、淀は再び侍女に言った。
「これの、色違いは、ないかしら。できれば、紅の色が、いいわ」
春の陽気に包まれた泉州・堺の湊は、人々ごった返して大変な賑わいだ。物売りの威勢の良い声がそこここから響いてくる。聞けば今日たまたま市がたっているということではなく、ある程度季節にもよるとはいえだいたい一年中この賑わいらしい。
幸村は佐助を伴って、湊の街並みを歩いている。甲斐や信濃に海は無いが、商人が集まる町は栄えるというのは亡き信玄も国づくりの基盤としていた考えだ。こうした賑わいを肌で感じ、学ぶこともまた、今後の甲斐・信濃の繁栄のためになるだろうと、今回上方を訪れるにあたって計画していたことだった。
「かの織田信長は、堺衆より鉄砲を仕入れていたと聞く」
「一度に何千丁も作らせたってね」
「確かに鉄砲はひとつふたつではなく数多く揃えることでその力を発揮するだろうな」
思案顔で言う幸村に、佐助は意外そうに眉を持ち上げた。
それに気づいて、幸村が問う。
「何だ?」
「いやなんつうか、大将は鉄砲なんざ嫌いなのかと思ってたから」
武士に鉛の玉が当たるかとか言ってたじゃん、頭の後ろで腕を組んだ佐助が言うと、幸村は生真面目に頷いた。
「うむ、俺ならば避ける」
「ああそう」
呆れ混じりに相槌を打った佐助は、「あ、でも」と付け加える。
「念のために言っておくけど、そんな何千丁も鉄砲仕入れるようなお金、うちにはないからね。てか、別に弓でもよくない?連射できるし矢のほうがどう考えたって安いし大将みたいな気合いで避けるような相手以外には有効だし」
「確かに連射はできぬ、弾も安くはない。だが鉄砲には、修練が要らぬ」
佐助は釘を刺したつもりだったが、幸村は思案顔のまま続ける。
「弓引くよりも弱い力で撃てる。俺のような、常日頃から鍛錬を積んでいる者でなくとも、引き金さえ引けば大きな力を得ることができる。これは、例え高価であっても、鉄砲を揃える理由になるだろう」
確かに今の俺の手持ちでは無理だがな、考えるのは自由だ、照れ隠しのように言い添えた幸村を、佐助はわずかに見開いた眼で見つめていた。
幸村の言うとおり、弓を引くには大きな力が要る。矢を的に当てるにはそれ相応の修練が必要で、「それ相応の修練」ができるのは幸村のような武家に生まれついた者のみで、戦で主力となる歩兵の多くはそのような立場にない。彼らに突然弓を持たせても、矢を飛ばすことは難しいだろう。
……でも、その全員に鉄砲を持たせたら。
敵方を近づける前に、先行して攻撃ができるのは、合戦において何よりの利点になる。
傍らを伺い見れば、幸村の視線はすでに甘味処に向いているようだった。その横顔を、佐助は見つめる。
……ほんと、恐ろしい御仁だよ。
鉄砲が戦に使われるようになってはや数十年。もともとは異国から伝えられたというその武器は、日を追うごとに改良が重ねられ、軽量化されてきた。今はまだ遠距離攻撃の主力は弓だが、豊臣の台頭の後は合戦の規模もその際に動く金銭の額も桁違いに大きくなってきている。つまり、かつての魔王のように何千丁もの鉄砲を揃えるということが可能になるということだ。恐らくはこののち十年とたたず、幸村の言うような歩兵が鉄砲を構える戦が当たり前になる世がくるだろう。だが今の時点でそれを理解できる武士が、この日ノ本にいったい何人いるだろうか。
「……っと」
佐助の視界に、見知った姿が映った。満開を迎えた桜の木の幹に隠れるようにしてこちらを窺う人影がある。
「大将、ちょっと外す。すぐ戻るから」
「うむ」
「言っとくけど団子は一日一本だからね」
「わかっておる」
お前は俺を何だと思って、とかぶつくさ言う主を置いて、佐助はごく自然な動きで人混みの間をすり抜けるようにして歩くと、目指す桜の木に近づいた。
「こんなとこで何やってンの、お前」
気配を殺してそこに居るのは鎌之助だ。同じく佐助も気配を消す。往来の人々は、二人のことをまるで見もせずに通り過ぎていく。
「甚八さんに、今日はこっちに来られるって聞いたもので」
「へェ?お前甚八あんま得意じゃないんじゃなかったっけ」
揶揄するように言うと、鎌之助が口元を曲げた。
「俺の話はいいんすよ、じゃなくて、さんのことっす」
鎌之助が姿を現した時点で絡みのことだろうとは思っていたが、予想よりも鎌之助の様子が沈んでいたので、佐助は柳眉を持ち上げた。
「ちゃんがどうした?」
問うと、鎌之助は言葉を探すようにしながら昨日からのの様子を話し始めた。
どうやら女性としての己の在り方に悩みがあるらしいこと、そしておそらくはそれが理由で幸村に会いたがらないこと。
「――ってわけなんすけど、幸村様的にはどうなんすかね」
の身に急を要する何かがあったというわけではないと理解した佐助は、若干肩の力を抜いた。
「んー、ちょっといま大将も意固地になってっからねー」
間延びした答えに、鎌之助が不満げに口を尖らせる。
「えー……」
「仕方ないよ、今の大将には甲斐と信濃がかかってる、考えなきゃいけないことが山ほどある」
「っすけど、あれじゃあさんが見てらんないっすよ」
「ちゃんもねぇ……、そこはどーんと構えりゃいいのに、ま、そういうとこが女の子なのかねぇ」
甲斐に来たばかりのころはまるで周り全てが敵であるかのような、殺伐とした気配を纏っていたが、複雑な乙女心などというものを持ったのだ。なんとも微笑ましい話ではないか。
「笑い事じゃないっすよ」
佐助の表情を見て鎌之助が釈然としない様子で言う。佐助は「あのなあ」と眉を下げた。何こいつめんどくさい、ちゃんに似てきたんじゃねぇの。
「実際笑うくらいしか外野にできることはねーの、知ってるか?他人(ひと)の恋路を邪魔するヤツは馬に蹴られてあの世行きってね」
「べつに邪魔しようなんて思ってねっすよ」
なおも鎌之助は納得する様子が無い。佐助は吐息して、視線を往来へ向けた。
「どっちにしろ年内には全部終わるだろうから、今はまあいいんじゃない」
「……終わる、って」
「徳川との戦。あんまり後回しにする理由も凶王サンには無いみたいだし?」
それを聞いて、鎌之助がごくりと生唾を飲み込むのが見えた。
徳川に反する勢力の地盤はほぼ固まったと言える。ならば石田三成のあの性格だ、今すぐにでも家康の首を獲りたいというのが本音だろう。
「さくっと徳川を斃して、祝言さえ挙げれば、あとはあの二人のことだ、なんとかするでしょ」
あっさりと言い放つ佐助に、鎌之助が渋々という様子で言う。
「そういうもの、っすか」
「そーいうものなの、お前はこんなとこで油売ってないでちゃんのご機嫌とりでもやってきな」
話はこれでおしまいとばかりに佐助は踵を返す。背後で鎌之助が何か言いたそうにしていたが無視した。
「ご機嫌取りって、そんなの幸村様しかできるわけないじゃないっすか……」
往来を城へ戻る鎌之助の足取りは重い。
どうやら幸村の方からに会おうという気はないらしい。これではも落ち込んだままだ。何か、自分にできることはないのだろうか。
「……、ん?」
ふと露店の店先に珍し物を見て、鎌之助は人をかき分けながらそちらへ向かった。近づいてみて、「それ」に眼を輝かせる。
「ねえおっちゃん、これいくら?」
声をかけられた店主と思しき男が、鎌之助の恰好を見て馬鹿にしたように笑った。
「お侍さんの稼ぎじゃなんぼなんでも手ェの届くようなモンやおまへんで」
「いいから、いくらなんだよ」
多少前のめりになって問うと、店主が胡散臭そうにこちらを見ながら金額を答えた。それを聞いて、鎌之助はぐいと口角をあげる。
「わかった、絶対俺が買うから明日まで置いといて。他の奴に売らないでくれよな?」
店主の両肩を掴んで「頼むぜ?」と念を押してから、鎌之助は駆けだした。
無理ではない金額だが如何せん時間が足りない。急がなくては。
大坂城の桜は満開を迎えた。
暖かな日差しの降り注ぐ二の丸の石畳の広場にも、ときおり吹く柔らかな風が薄紅の花びらをひらりひらりと舞い上げていく。
「……」
袴姿で木刀を正眼に構えたは、間合いの外に無造作に佇む三成を真っ直ぐと見据えている。
二人とも無言で、先ほどから一寸たりとも動いていない。ただ、触れれば切れるような気配だけが、二人の間に凝っている。
――否、動かないのは身体だけで、その実、思考では激しい攻防を繰り返している。
三成を相手に受け身になると、その速さと手数で必ず押し込まれる。斬撃を処理しきれなくなって字の如く身を削られることとなる。
だから、先ずはこちらが動く。
初めから足元で風を爆発させて、その風に乗って間合いを詰める。袈裟懸けに一撃、当然のように三成が受け止めるべく木刀を持ち上げる、しかしそれはあくまで「斬るふり」で、斬りかかった体勢を風を使って無理やり傾ける。本命は下から掬うような一撃。三成の足を狙って、入ったかと思った瞬間、その痩身が掻き消える。後ろ、と判断して刃を振りぬく勢いのまま身を反転させて、しかし三成の姿はそこになく、次は上、と見上げるころには振り下ろされた刃が己の脳天に達して、
……だめだ。
指先ひとつ動かさないままそこまで想定して、内心首を横に振る。
以前にも三成に言われたことだ。判断が遅い。もっと速く、動かなければ。
視線の先、現実の三成が、わずかに刃先を動かした。それを合図に、は一歩を踏み出す。
「――ッ!!」
正面からでは、先ほどの思考での打ち合いと同じことになる。それではいけない。三成の間合いに踏み込んで、低い姿勢を保ったまま木刀を薙ぐように振り払う。当然受け止められると思っていたのに、三成は動かない。まさかこのまま決まるのか。そう思考した、その一瞬が命取りだと、何度も身をもって叩き込まれたはずだったのに。
「!!」
刃が三成を捉えるその瞬間、まるで妖術か何かのように三成の姿が消える。
違う、三成は己の動きにバサラを使わない。ならば妖術などというもののはずがない。人間の動きだ。追えないはずは、
「遅い!」
鋭い声が飛んで、あっと気づいたときにはの身体は石畳に叩きつけられていた。風で受け身をとることもできなかった。全身を襲う衝撃に、痛みよりも驚きの方が大きい。
……何が、起こった?
目線だけを上げれば、三成は元と同じ場所に、元と同じような姿勢で佇んでいる。
消えた三成がどこへ移動していたのか、何をどう打ち込まれて自分は地に臥したのか、には何一つ見ることができなかった。
感情を覗かせない声が、頭上から降ってくる。
「眼に頼るなと言ったはずだ。貴様の剣は後の先をとる速さだけしか能がない。その風は何のためにある」
そう、相手が動いてからその攻撃を予測して先回りするのがの戦い方。足りない力を速さで補っている。そのための風。
……違う。
自分の身体をより速く動かす、確かにそのために風を使う。だが風の使い方は、それだけではない。
――『速さを求めるなら、正しく場を認識しろ。常に周囲の把握を怠るな』
初めて三成と打ち合いをしたときの、彼の言葉を思い出す。
の風は、周囲の気配を辿ることにも使える。それだけに意識を傾ければ、かなりの範囲で人の動きを察知することができる。もちろん戦闘中に「それだけに意識を傾ける」などということはできないが、それでも自分の周りの気配なら、常に辿れるはずなのだ。
刀を構えると、無意識に相手の動きを目で追ってしまう。追いきれるならそれでもいい。だが三成を相手取るならば、見てからでは遅い。
「それができないと言うなら、戦場で野垂れ死ぬことを許可する」
ついてもいない血を払うように木刀を振って、三成がそう言った。
それを聞いて、は身を引きずるように起き上がる。
遅れてやってきた打ち身の痛みは噛み殺して、木刀を構える。
「もう一本、お願い申し上げる」
耳元で、風が唸る。もっと速く、もっと広く。この場の全てを見逃さないように。
わたしはもっと、
……もっと強くならなくてはいけない!
の視線の先、こちらをじっと見つめていた三成が、ふいに木刀を降ろした。
殺気に似た気配が、霧散する。
「……三成殿?」
眉を動かして声をかけると、だらりと降ろした腕に木刀を提げた三成の視線がを射抜いた。
「気を散らす者を相手にする時間は、私には無い」
「!」
気を散らす、――集中していないと、三成は言っているのだ。
集中。しているはずだ。今日は朝から、余計なことを考えたくなくてこうして木刀を握って、
「あの男も、貴様も、何を考えている」
「っ、」
ぎくりと、は肩を強張らせた。
何を考えているのかと問われれば、何も考えていないとしか答えられない。余計なことを考えないようにするので精いっぱいで。――つまり余計なことを考えているということだ。
三成は今回幸村と会っているはずで、「あの男」というのは恐らく、幸村のことなのだろう。
幸村が、何か言っていたのだろうか。三成は何を知っているのだろう。
どくどくと、心の臓が音をたてている。それを見透かすように、三成が言う。
「私は嘘を何よりも厭う。貴様の腹の内にあるのがそれでないと確かめてから、剣をとれ」
それだけ言い捨てて、三成は踵を返した。は何も答えることができず、ただ遠ざかる背に稽古の礼として頭を下げるのみだった。
袴姿のままふらふらと自室に戻ったに侍女たちが気遣わしげな視線をくれて、「疲れただけだ」と言い置いて部屋に入った。背後で襖が締まった音を聞いてから、かくりと膝を折って腰を下ろす。
来たばかりの頃に比べれば、ずいぶんと物が増えた。もともと物を持たないの部屋は小田原であれ上田であれがらんと殺風景だったのだが、大坂城大谷屋敷内にあるこの部屋には衝立に掛けられた打掛や、流行りの絵巻、裁縫道具などが整然と並べられている。着物は五助が、その他の小物は淀が用立ててくれたものだ。
その淀は、今朝から出かけているようだった。夕暮れまでには戻ると言っていたが、まだ戻っていないらしい。
「……鎌之助、は、……いない、か」
風で探るが天井裏や付近にも彼の気配ない。鎌之助は今日佐助に会うようなことを言っていたから、そちらからまだ帰っていないのだろう。
自室の周りには誰もいないと確認して、は座り込んだまま膝を抱えた。額を膝頭につけるようにして、細く息を吐く。
嘘、と三成は言った。
腹の内にあるもの。
それは、が今心に抱えている、もやもやとした何かだ。
……不甲斐ない。
おなごらしさなどなくても、うつくしくなどなくても、幸村の傍らで戦場を駆けるだけの力がある、それでいいのだと、思ったのに。
結局自分は、その力ですら、まともに鍛えることもできないのだ。
なんという体たらくだろう。
幸村に会いたくないなどと言いながら、それでも彼のことを考えることをやめることができず、その結果多忙の隙を縫って稽古をつけてくれた三成にまで迷惑をかけて。
昔は、こんなことなどなかった。今の自分は、かつてが取るに足らぬと見下してきた大人そのものだ。くだらないことに固執して、妬んで、
……わたしはこんなにも、弱い人間だったのか。
膝を抱える両の拳にぎりりと力が入る。
「、あ」
その痛みに我に返る。恐る恐る顔を上げて掌を見下ろせば、爪が食い込んだ痕がくっきりと残っていた。まだ血が滲むほどではなくて、感触を確かめるように握ったり開いたりしながら少しだけ安堵の息を吐く。
いけない、いけない。
これで掌に傷でも作れば、鎌之助や淀に心配をかけるし、何より五助に見つかると厄介だ。剣の鍛錬を禁じられかねない。
だいたい何をどう考えたところで、明日には幸村は大坂を発つと聞いている。
だから、これでいいのだ。このまま何事も無く、明日も流れていくだろう。
……これで、いいんだ。
両手で自分の頬をぺちりと叩く。しっかりしろ。
自分に喝を入れてから、は立ち上がると、替えの着物の準備を侍女に頼むべく、襖を開いた。
結局その晩は淀も鎌之助も姿を現さず、はまたも寝付けない夜を過ごしたのだった。