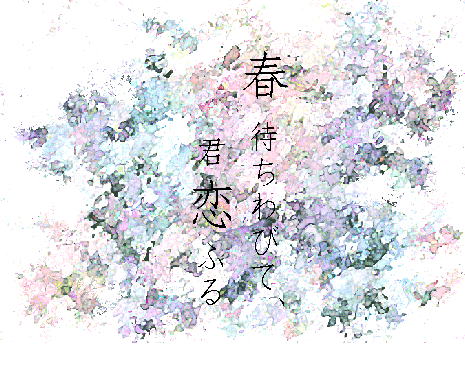
(後編)
「……まあ」
翌朝、いつものように朝餉の時刻にのもとに現れた淀が、開口一番「ひどいかお」と言った。
はばつが悪そうに視線を逸らす。
「……その、昨日はあまり、寝られなくて」
「昨日『も』、なのでしょう」
間髪入れずに言われて、はぐっと言葉に詰まった。
その様子を見つめて小さく吐息すると、淀は傍らの侍女に持たせていた小さな紙包みを受け取って、の眼前に腰を下ろした。
「淀殿?」
「これ。あげるわ」
「え」
手を出してと言われるままに差し出したの掌に、淀が包み紙を開いて取り出したそれを置いた。
それは、平打ちの組紐だった。
鮮やかな深緋(こきひ)の、組み目が艶やかな、見るからに上等なものだと知れた。
「あの、淀殿、これは、」
「組紐」
「いやあのそうではなくて、」
「姫の、髪に合うと、思って」
いつもの調子で訥々と言う淀に、は慌てる。
「まさか、わたしのために、……買っていただいた、のか?」
「私が、盗んだ、って、いうの?」
「そんなことは言ってない!」
思わず大きな声が出て、はさっと顔を赤らめる。
「っ、その、」
「よかった」
淀がそう言って、ふわと笑った。
「少しは、元気、でた?」
「っ!」
「うーわー、まじっすか、淀さんに先越されるとか」
聞きなれた声がして、どこから入ったのかそこに鎌之助の姿があった。
「鎌之助!」
「……何度も、言うけど。姫君のお部屋に、伺いも無く入るなんて、悪」
わずかに眼を細める淀に、鎌之助は一瞬閉口したが、すぐにぐいと眉を引き上げた。
「次から気をつけますから、今だけすんません」
鎌之助が淀に対して強く出るのは珍しい。なりゆきを見守っていると、鎌之助は懐に突っ込んだ手をずいとへ差し出す。
昨日の朝、偵察に出る前に見かけたときと比べればずいぶんとくたびれた様子の鎌之助が差し出したのは、その彼の恰好からは及びもつかない、小さく小奇麗な布巾着だった。葡萄茶(えびちゃ)色の、
「……まさか、縮緬(ちりめん)……?」
絹糸の変わり織であるその布地は、そうそうお目にかからない高級品だ。
も間近で見るのは初めてだった。淀から受け取ったばかりの組紐をそうっと膝の上に置くと、巾着に手を伸ばす。
「いやこれはなんていうかただの包みで、大事なのは中身っす」
「中身?」
受け取ると、中に何か入っているようだった。ころりと丸い何かが、ひとつ。
「なんかもー、まさか淀さんに先越されるとは思ってなかったんで、二番煎じもいいとこなんすけど、まぁ開けてみてくださいよ」
そう言われれば拒む理由も無いので、は巾着の紐を解いて中を覗く。
「……?」
白い、丸い、何か。石だろうかと、指でつまんで取り出してみる。
「あら、金平糖」
おっとりと淀が言って、その言葉の意味を理解した瞬間はぎょっと眼を見開いた。
「こっ、」
驚いて言葉に詰まる。
金平糖、だと!?
も噂には聞いたことがある。南蛮渡来の砂糖菓子だ。砂糖というだけでそもそも大変高価なものだが、この金平糖に至っては一粒で城が買えるなどと実しやかに噂される、とにかく希少な高級品である。
もちろん、はこれまで眼にしたこともなかった。
その菓子が、今、眼の前に、ある。
「それ買う金を稼いでたらちょっと時間かかっちゃって、一晩も空けてすんませんっした」
「稼いで、って、」
いったい何をどうしたら、金平糖が買えるだけの金銭を一晩で稼げるのか。
淀も同じように思ったのか、二人して鎌之助を見つめると、鎌之助は照れくさそうに笑う。
「ちょっとがんばったんすよー、俺!ほら、食べてくださいっす!」
「今か!?」
「だってせっかく買ってきたんすから、食べてるとこ俺が見たいんす!」
「そう、なのか」
そこまで言われては断ることもできない。
は意を決して、金平糖の粒を口へ運んだ。
ざらりとした舌触り、そして。
「……あまい」
今まで口にしたことのあるどの食べ物とも違う味だった。口の中で転がすと、ほろほろと甘さが舌の上で広がっていく。
その甘さが、どうしようもなく、優しくて。
「ちょ、え、さん!?」
鎌之助が明らかに狼狽えた声をあげ、淀が「あら」と小首を傾げる。
二人の反応で、は我に返る。鼻の奥が痛い。視界が急速に滲んでいく。
「っ、」
いけないと思った時には、巾着を持つ手にぽたりと涙が落ちていた。
「ぅあ、さん、不味かったですか?あれでしたら吐き出してください!」
さあとばかりに掌を差し出されて、そんなもったいないことは死んでもできないとは顔を逸らす。
「ち、ちが、おいし、から」
すまない、小さくそう呟いては涙をこらえようと瞬きを繰り返す。なのに。
「っ、う、」
嗚咽まで出てきて、慌てて自分で口を塞ぐ。どうして。二人の前でこんなみっともない。恥ずかしい。
「……姫、本当は、真田どのに、会いたかったんでしょう」
唐突に淀がそう言って、は反射的に首を横に振った。違う。会いたくない。こんな恥ずかしいところ、見られたくない。
「ほんとはそうじゃないんすよね?幸村様に来てもらって、きれいだって言ってほしかったんすよね」
鎌之助までそんなことを言いだして、いよいよは涙を抑えきれなくなった。俯いて、ぎゅうと手指を握る。両手にはそれぞれもらったばかりの、組紐と巾着袋が握られたままだ。
「ちが、だって、ゆ、きむらどのは、あいにきて、くれな、っ」
幸村には幸村の都合がある。それが当然なのだ。そのことに不満なんて、
「今俺と淀さんしか聞いてないから。言っていいんすよ、素直に」
鎌之助の声がして、頭を撫でられた。想像していたより、大きな手だった。
素直に。
言われた言葉が、心に落ちる。
そうだ、自分は難儀な性格だから、素直であろうと心掛けてきたはずなのに。
「ふ……っ」
まとまらない思考が、ついに堰を切る。
そう、本当は、
「っ、きて、幸村殿に、きて、ほしかっ、」
――本当は、幸村に、来てほしかった。
大坂に来たというなら、イの一番に会いに来てほしかった。着物が似合ってないのではないかとか、おなごらしい所作を覚えきってないとか、色々戸惑うところはあったけれど、でも幸村が来てくれて一言「似合っている」と言ってくれれば、それでよかった。他でもない幸村がそう言うなら、はそれを信じられる。
……その考えが、嫌だった。
まるで幸村に寄りかかっているような考え方だ。判断を全て幸村に委ねるかのような、その考えが、は嫌だった。
だから、自分がもっと、おなごとして恥ずかしくないようにならないといけないと思って。
「どう、して、きてくれなかった、のだろう、っ、わた、わたしばかりが、会いたい、みたいで、いやだ、」
もしかしたら幸村は、が想うほどのことを想ってくれていないのではないか。そう考える自分にも嫌気がさした。幸村のことを信じられないと言っているのと同じである気がして。
「幸村、どのは、わたしに、……あいたく、ないの、だろうか」
自分で口にしたその言葉に、喉の奥が痛くなる。勝手な言い分だとわかってる。自分のほうこそ会いたくないと言ったのに。
「……そうね。本来ならこういうときは、殿方から、顔を見せに、来るものよ」
淀の穏やかな声が聞こえる。
「俺も、そう思うっす。でも、幸村様は今ちょっとたてこんでるみたいで」
「許嫁の姫君を、泣かせておいて、何にたてこんでるの?」
その声は穏やかだが有無を言わせぬ凄みがあった。鎌之助がかすかに身じろいだのを、は気配で感じ取る。
しばし逡巡してから、鎌之助は言った。
「その、幸村様は、さんに会いたくないわけじゃないっす。たぶん、むしろ、会いたがってると、思います。だって幸村様、さんのことすげえ好きっすよ?ただ、会ったら舞い上がっちゃって、他のことが疎かになりそうだからって、その……意地になってる、って長が」
それを聞いて、はぐいと顔をあげた。もうぐしゃぐしゃで見れたものではないだろう、だがそれももう今更だ。
「なん、だ、それはっ。すきなのに、他のことが、疎かに、だと?か、っ、勝手なっ」
ひとりでぐずぐずと考えていたわたしがばかみたいではないか。自分のことは棚に上げて、は唇を震わせる。
鎌之助は困ったように「それは、そうなんすけど」などと言葉を濁す。
そうっと、の頬に、淀が触れた。彼女の手には懐紙があって、それでの涙を拭ってくれている。
「そうね、勝手だわ。本当に、殿方というのは、見栄を張るのが、お好きだこと」
呆れたようなその言葉は辛辣だ。鎌之助も黙り込んでしまう。
「いつだって、殿方の意地だとか、見栄だとか、そういうものに、泣くのは、おなごのほう」
「淀、どの」
が眼を瞬かせて、淀を見やる。
相変わらず読みづらいぼんやりとした表情。
「でもね、姫。そういうとき、おなごは嫌な顔をせず、殿方のその意地や見栄を、たててあげないと、いけないの」
「そんな、」
そんなの不条理だ。は思った。どうしてこちらが我慢しなければいけないんだ。
の心の声を聞いたかのように、淀が笑む。
「それが、おんなの、甲斐性なのよ」
甲斐性。その言葉に、はいまだ涙を溜めた眼を淀へ向けた。
淀はと視線を合わせて、頷く。
「殿方というのは、ほんとうに、くだらないいきもの、なのよ」
「……幸村殿は、くだらなくなんか、ない」
ずっ、と洟をすすりながら、が唇を尖らせる。それを見た淀が、「ええ、」と答える。
「姫は、そんな真田どのが、すきなのでしょう。ならば、多少のことは、眼をつぶって、あげなさい」
「……」
涙を溜めた眼を瞬かせて、は黙り込んだ。
鎌之助が、にっと口角を上げる。
「で、さん。幸村様はさっき、大手門から発たれました。今ならまだ、近くにいます」
は顔を上げて、しかしうろりと視線を彷徨わせる。
「……だが、そろそろ五助が来る頃合いだし、」
毎朝朝餉のころに顔を見せる五助には、を監視する役もある。がいないと知られたら、最悪同盟に影響が出かねない。
だが、淀が当たり前のように言う。
「少しの間なら、私がごまかして、おくわ」
「ね、さん」
鎌之助にも促されて、はふたりの顔を交互に見つめた。
「……」
そして、ぐっと口を引き結ぶ。
「……淀殿、鎌之助、……すぐに戻る」
すっくと立ち上がると、は衣装入れから袴を引っ張り出す。鎌之助の前であることを感知しない様子で小袖の裾をたくしあげて袴を履きはじめたので、鎌之助はあわてて顔を逸らした。
「っ、俺、馬ひいてきますから」
「いい、要らない」
「え、でも」
手早く帯を締め直して、もらったばかりの組紐で髪をひとつにまとめる。金平糖の巾着はそっと懐に忍ばせる。口の中で、最後の甘い味がほろりと溶けていく。
身だしなみを整えると、はばたばたと広縁へ歩を進め、ふとそこで足を止めて、振り返った。
「さん?」
「ふたりとも、本当に、ありがとう」
そう言うの口元には、確かな笑みが宿っている。
「ええ、どういたしまして」
淀がのんびりと答えて、は踵を返すととん、と広縁から飛び降り、
「あ、さん草履、」
鎌之助の言葉をかき消すように、ごうと風が吹いて、部屋の衝立をがたがたと鳴らした。
文字通り飛んで行ったを見つめて、鎌之助がぽつりと言う。
「そっか、その手があったんでした」
「あなたも、のんびりしてる場合じゃ、ないでしょう?姫を、ひとりで、城から、出すつもり?」
淀の言葉に手の中の草履を見下ろした鎌之助は困ったように眉を下げる。
「っ、でも、」
「ここのことは、いいから」
言われて、鎌之助はがばっと頭を下げた。
「すんません、ありがとっす淀さん!」
言い残すが早いか、鎌之助は軒先へと跳んで姿を消す。
途中足場にでもしたのか、桜の木が揺れて、ひらひらと花びらが舞った。
「……若い、って、いいこと、ね」
一人残った淀はそう言って立ち上がると、まずは風で散らかった部屋の片づけを始めた。
大坂城二の丸大谷屋敷、湯浅五助はしかつめらしい顔を崩さないまま、主と碁を打っている。
「……吉継様。そろそろ姫君の元へ伺う刻限ですので」
障子の向こう、陽の昇り具合を気に掛けながら五助が言うと、吉継は目元を笑みの形に歪める。
「やれ、五助。たまにはゆるりと碁を打ちたいというわれの気休めに付き合うてはくれぬのか?薄情なことよ」
何か面白がっている主の様子に、五助はこれ見よがしな息を吐く。
「だいたい何故朝から碁なのですか」
「ヒヒ、言うたであろ、気休めよ、キヤスメ」
「……」
碁石を戻し終えた吉継が、五助を見つめて引きつるように笑う。
「ほれ、もう一局。なにしろ碁でわれの相手が務まるのはぬしのみよ、われの気のすむまで付き合え」
「……」
五助はもう一度ため息を吐くと、指先で碁石を摘まみ上げる。
大坂の城下町を過ぎて、幸村の一行は京へ続く街道に入りつつあった。幸村を先頭に、騎馬でわずか三騎。忍びである佐助と甚八は表に姿を現していないが、街道脇の桜の木々の間を並走している。ここからまずは京に入り、その先は近江へと東海道を進んで甲斐へ戻る手はずとなっていた。
ここまで町を抜けてきたこともあって、幸村は馬を比較的ゆったりと進めている。まだ朝早いからか街道に他の通行人の姿は無い。昼になれば暑いほどの陽気となるのだが、またこの時刻では少し肌寒いと感じる。
――此度の京・大坂への遠出は、充実したものとなった。
何よりまず、これまでその名前すらあまり聞こえてこなかった豊臣秀頼に会えたのは大きい。豊臣の家長が如何なる人物か、気になってはいたのだ。如何に三成が内政を取り仕切っているとはいえ、彼はあくまで豊臣の一家臣に過ぎない、そのことは以前より主である勝頼も気にかけていたようだった。
満を持して相対した秀頼は、理知的な印象の少年だった。あと数年もすれば、立派な将となるのだろうと、幸村は思う。
……否。あの方が真に豊臣を背負うようになるころには、この乱世は終わっているのかもしれない。
徳川を斃せば、規模で豊臣に敵う勢力はもはや無い。ならば、そう遠くない将来、決戦の末にはいよいよ、
――天下統一。
その言葉が脳裏を過ぎって、幸村は無意識に手綱を握る手に力を籠めた。
……そういえば。
対面した秀頼の母君が、現在大坂の城にいるらしい。なんでもその女性が、に作法を教えているという(以前佐助が言っていた、「花嫁修業」とやらだ)。
ふいに眼の前をひらりと薄紅が舞い落ちていく。
見上げれば、満開の桜の花びらが、時折風に揺れてざわりと音をたてている。
……は、どうしているのだろう。
同じ城に居ながら、顔を見ることはなかった。
いや、自分が会おうとしなかったのだ。
昨日は堺を訪れていて城に戻ったのは夜半であったし、会う時間がなかったといえばそうなのだが、それでもその気になれば顔を見に行くことくらいはできたのだ。
だが幸村は、それを、しなかった。
……不甲斐ないところを、見せたくなかった。
越後での乱を経て、幸村は己の未熟さを改めて思い知った。あの乱について、には結果だけしか伝えていない。上杉景虎の謀反、それを上杉景勝が制した。彼女に伝えたのはそれだけだ。同郷である景虎のことをが気に掛けるかもしれないから、というのは建前だ。本音は、情けない立ち回りしかできなかった自分のことを知らせたくなかったのだ。
の、あの真っ直ぐとした双眸に映る「真田幸村」は、もっと強く、立派な武将でなければならない。
「……許せ、」
呟くと、まるで答えるように、桜の木々がざわざわと鳴った。
花びらが、視界を躍る。
ああ、風だと、思う。
どこまでも透明で、清廉で、綺麗で、気難しいところもあるけれど、本当はとても優しい、
「……え……?」
思わず手綱を引いて馬を止めた。ざわざわと桜の鳴る音は止まない。
「幸村様?」
背後から問う声、しかし幸村は答えない。
まさか、と口の中で呟く。
幸村は、この風を、知っている。
ありえないはずだ、ここはもう大坂の町ではない。そもそも彼女の身の上は表向きには大谷家の姫君だが、その実は同盟の人質。そうそう城を出ることはない、そのはずだ。
だが、この、風は。
その名を紡ごうと、幸村が口を開いた、そのとき。
「――幸村殿――――ッ!!!」
力の限りに叫んで、は纏う風の向きを変えた。
空から城下を探したが目指す姿が見つからず、焦燥に駆られたところで街道にさしかかる騎馬を見つけた。背に負う二槍を、自分が見間違えるはずがない。
さすがに町の外まで探しに行くわけにはいかなかった。よかった、間に合って。考えながら風を駆る。
思えばこうして飛ぶのもずいぶんと久しぶりだ、戦闘中に突発的に身体を浮かせるのとは違う、継続した力の行使はそれなりに体力を使う。そう考えた瞬間、
「え」
唐突に足元の風を掴み損ねる。しまった、という思考が固まるより前に、上体を起こそうとして失敗する。これまで手足のように動かせていた風が、読めなくなる。
「っ!」
とうとう決定的に体勢を崩して、飛んできた勢いのままの身体は宙に投げ出された。
眼下の桜の木々に頭から突っ込む。
主に寝不足による力の低下だと判じて、は早々に諦めた。なんのことはない、あとは地に叩きつけられる寸前に浮き上がる風を起こして衝撃をやり過ごす、そうすればたいした怪我も負わないだろう。五助に見つかると面倒だから、顔は庇わなくては、
――がっしと、身体を掴むように支えられて、は眼を丸くした。
蹄の音、「どう!」という力強い声、それに反応してか嘶いて上体を持ち上げた馬が、動きが止まる。
「……あ」
馬鹿みたいに間の抜けた声が出た。
ひらりひらりと、視界を花びらが舞っていく。桜の木々が風に揺れていて、自分が突っ込んできたところの枝が折れているのが見える。その視界に映る、
「……幸村殿……」
漸く思考がついてくる。ここは馬上で、幸村の腕の中。
を見下ろす幸村も、眼を見開いていた。運よく幸村の腕の中に落ちた、というのはいくらなんでも出来過ぎた話だろうから、おそらくは幸村が、とっさに助けてくれたのだろう。
「……、……なのか」
呆けたような声だった。
は眼を細める。
「わたし以外の誰だというのだ」
「いや、その」
幸村は口ごもって視線を泳がせ、やがて気づいたようにの顔をまじまじと見つめた。
「……何か」
「顔色が、よくない」
それに、と言って、幸村は左腕一本での身体を抱えなおし、右手をそうっとの頬に伸ばした。なぜだかびくりと肩を震わせたの頬に触れた幸村の掌が、どうしようもなく暖かい。頬に添えられた手の親指が、の左の眼尻をなぞる。
「赤く、なっておる」
表情を動かさないように、顔に力を入れた。
泣いたことを、幸村に悟られてはいけないと、思った。
「その、近ごろあまり、寝れなかったから」
寝不足のせいだと答えれば、幸村は「そうか」と頷いた。
「大坂もここ数日で急に温くなったと聞いておる、風邪を引きやすいというからな、養生いたせ」
「……わかって、いる」
どうやら幸村はそれで納得してくれたらしい。余計な心配をかけずにすんだと安堵する一方、の心には釈然としないような感情が凝る。
「それにしても、ひとりなのか?裸足ではないか、いったいどうして」
幸村の声に、は口を引き結ぶ。
貴方が、会いに来てくれないから。眼が赤いのも本当は、貴方に会いたくて泣いたから。
口をついて出そうになったその言葉を、飲み込む。
淀が言っていたではないか。
男の見栄をたててやるのが、おなごの甲斐性。
「……わたしが、」
それでもわずかに逡巡した。意を決して、は真っ直ぐと幸村を見上げる。
「わたしが、貴方に、会いたかったのだ。だから来た」
「……っ」
幸村が、目を丸くする。
「幸村殿?――ぅわ」
がばり、と抱きしめられた。
暖かい腕の中。相変わらず力加減が容赦ない。少しばかり息苦しいが、今は我慢しよう。
なぜなら、ここは、がこの世で一番すきな場所なのだ。
「あまりそういうことを言うてくれるな」
頭上から、唸るような声が、降ってくる。
「……このまま連れて帰りたくなる」
頬が熱くなるのが、自分でもわかった。
「そ、ういう、わけには、いかないだろう、」
「うむ、だから、……しばらく、こうしていてくれ」
ぎゅう、と抱きしめられる腕に力が籠る。
「、……会いたかった」
「っ」
よかった。幸村も、同じように想ってくれていたのだ。
なんだか、ぐだぐだと悩んだ自分が本当に馬鹿みたいだ。
ばかみたいで、なんだか。
「……、?笑っておるのか?」
なんだか恥ずかしくて、見られたくない。
は答える代わりに、幸村の背に腕をまわした。
幸村の従者二人はそれぞれ心得た様子で、少し離れたところで馬を降りると水をやったり背を撫でたりしている。
それらを桜の木の枝から眺めるのは、佐助と甚八、そしてを追ってきた鎌之助だ。鎌之助の手には、の草履がある。
甚八の表情はよくわからないが、佐助は珍しく頬を緩めていて、鎌之助も何やら嬉しくなった。
「ま、よくやったよ、お前は」
佐助の声に、鎌之助は顔を上げる。
「お前をちゃんにつけたのは、正解だったな」
「!」
真田忍びの長は、めったなことでは配下を褒めない。
佐助の視線は幸村とに向いたままだったけれど、鎌之助は顔を真っ赤にして頭を下げた。
風が吹く。
桜の花びらが、吹雪のように舞っていた。