きんと冴えわたる、朝の透明な空気の中に、ふと、陽の暖かさを感じたとき。
肌を裂くようだった風が、緑のにおいを運んできたとき。
すべての息吹を拒むかのようなつめたい世界に、命あるものの息遣いが聞こえてきたとき。
絢爛の春は、それでいて残酷だ。
春が来るということは、世が動くということ。
すなわち、また戦が始まるということだ。
いつの日か春を、そのあたたかさといのちの芽吹きを手放しに喜ぶことができる、そんな世が来るのだろうか。
その答えを、はまだ持たない。
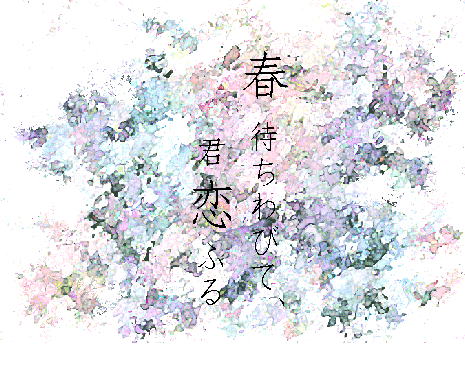
(前編)
じわり、風の冷たさが緩んだと思ったら、あれよと言う間に春はこの大坂の城も飲み込んだ。一斉に蕾を膨らませた桜の花びらも開き始め、今日で八分咲きといったところだ。このままの陽気が続けば、明日明後日にも満開になるだろう。
ずいぶんと暖かくなったので、近ごろは障子を開けて桜の蕾を眺めながら食事を摂るようになった。その日も薄紅の色が飾る庭を眺めながら淀とともに朝餉の膳を前にしていたは、それを聞いて動きを止める。
「……、幸村殿、が?」
にわかには信じがたく、わずかに眼を見開いてそう言えば、報告をあげた鎌之助が、膝をついたまま勢いよくこくこくと頷く。
「はいっす!昨夜の時点で城下には到着されてて、今日には城に来られるって」
「ずいぶんと急な話だな」
まさに寝耳に水。事前の連絡はなかったのかと聞くと、鎌之助は申し訳なさそうに頭を下げた。
「すんません、俺のところに連絡がきたのも今さっきでして。たぶん幸村様は今回お忍びで来てるんじゃないかと思うっす、大坂(こっち)もそれを知ってるのは石田と大谷だけらしいんで」
「……とにかく、真田どのは、こちらに来られるのね。大変、それなら、姫は、お会いする準備を、しなきゃ」
駆け込んでくるなりこちらの返事も待たずに「さん大変っす!」とまくしたてた鎌之助の無礼さに眉をひそめていた淀は、しかし気を取り直してに向き直った。
「その打掛じゃ、少し地味だわ、そうね、菖蒲か椿か、紅梅、……いえ、せっかくだもの、桜のものが、いいかしら」
その言葉に、ようやくは瞬きをして、持ち上げたままだった椀を膳に置く。
「……淀殿、あれはわたしには華やかすぎると思うのだが……」
最近新たに設えられた着物を思い浮かべて困ったように眉を下げるに、淀は不思議そうに首を傾げた。
「何、言ってるの。あれは春のものよ、今着なくていつ着るの」
「……いや、その、そもそも、幸村殿がわざわざ大阪に来られるというのは何か用向きがあってのことだろう?まさかわたしに会うためではあるまい」
そんなことのために、例え忍びの小介に影武者を任せていたとしても国を空けるはずがないと、が鎌之助を見れば、鎌之助は面白くなさそうに頷いた。
「っす。こないだ『左衛門佐(さえもんのすけ)』とかいうの任命されたじゃないっすか、なんでもそのお礼だとか挨拶だとかで上洛してて、それで大坂(こっち)にも寄られるっていうんで」
鎌之助の言う左衛門佐とは、朝廷の官職のひとつである。
朝廷の官職は、元々はもちろん帝に仕える公家の役職だ。しかし戦乱の世が続くにつれ朝廷の力も廃れ、都の公家たちも生活に困窮するようになってからは、金や実力があれば公家でなくても位階や官職が手に入るようになり、名誉を欲する武家の者が任命を受けることも珍しくは無くなった。豊臣秀吉が公家の最高位である関白職を任ぜられていたのはその最たるものと言えよう。事実秀吉の死後も、豊臣家にはある程度の官位叙任権が朝廷から認められている。大谷吉継の刑部や石田三成の治部もそうした官職の名だ。
幸村が左衛門佐を拝命したというのはも聞き及んでいる。先日豊臣の家長・秀頼の使者が甲斐を訪れ正式に叙任を受けたという。
秀頼の使者とはいっても、幸村の叙任を主導したのは三成だったらしい。京の伏見城に居を置いている秀頼はまだ年若く、実質上政権の中枢は三成が担っているから、何も不思議なことはない。
左衛門佐はの位階は従五位下。刑部少輔や治部少輔と同格であり、それはつまり三成が幸村を己と対等と評価したということだった。
「向こうが使者たてて済ませたんだから、お礼参りとかいらないと思うんすけどね」
鎌之助が些か不満げに言う。「別に幸村様の主が石田ってわけじゃないんすから」という鎌之助の言葉はあながち誤りとはいえない。朝廷ではなく豊臣家が主導して幸村に官位を授けたということは、「真田は豊臣の一員である」と内外に知らしめるようなものだ。本来幸村が背負って立つのは武田の家であり、評価されるならばそれは武田家の当主・勝頼であるべきなのかもしれなかった。それについては己に面識があるものを正しく評価する三成の姿勢が見て取れるようであったし、武田家はすでに信玄の代に朝廷から上位職を任じられているから筋が通っていないこともなかったのだが、釈然としない鎌之助の考えもわからなくはない。
「大坂の滞在は三日、って聞いてます。豊臣のえらいさんに挨拶回りして、あとはこの辺の視察したりとか」
詳しいとこまではまだよくわからないと鎌之助が付けたして、それを聞いたは短く吐息した。
「物見遊山に来られるわけではないのだから、なおさらわたしのところに寄られる暇などないだろう」
そう言って箸を持ち上げるの様子が、どこか安堵しているかのように見えて、淀はゆるりと視線を動かす。
「……姫は、許嫁どのに、会いたく、ないの?」
問われたは眼を丸くする。
会いたくない、だと?
「まさか。幸村殿の顔が見られるなら、それに越したことは……」
それに越したことはない、そう澱みなく言うはずだった言葉は、しかし喉の奥にひっかかって出てこない。
……なんだ?
今も幸村の笑顔を、思い浮かべることができる。抱きしめられた腕の中の暖かさも。
思い出すと、心の臓がきゅうと震えるような気がする。切なくて、そして、
……痛い。
どうしてだろう。自分でもわからず、はただ視線を下げる
「――おはようございまする、姫君」
平坦な声がして、は顔を上げた。広縁にいつもどおりのしかつめらしい顔つきで、ひとりの男が膝をついて控えている。湯浅五助という、義父・吉継の家臣だ。
「おはよう、五助」
の身の回りの世話(という名目の、その実は人質であるの監視)を吉継から仰せつかっているということで、毎朝この刻限に挨拶に現れる。
五助は室内を見回して、眼が合ったのか鎌之助が威嚇するように彼を睨む。それには取りあわず、視線をへ向けた。
「本日のご予定でございますが、」
「ああ、五助、今日は姫は、こちらで一日縫い物よ」
五助の声を遮って、淀が言った。確かに今日は特段の予定はなかったはずだが、淀が答えるのは何故だろう。
と同様のことを考えたのか、五助は怪訝そうな視線を淀へ送ったが、淀はぼんやりとした表情を少しも変えない。
「……、承知仕りました」
根負けしたかのように五助は頷いた。そもそもこの城内で、世継ぎの母君たる淀に逆らえる者はそういない。
五助は淀からへと顔を動かす。
「明日の、剣の稽古ですが、三成様が都合をつけてくださるとのことです」
「! そうか」
はわずかに身を乗り出した。三日に一度、顔や眼に見えるところに傷を作らないことという条件で許された鍛錬、明日はその日だった。同じ刀を武器(えもの)としている三成に、これまでも幾度か教えを乞うている。剣の腕としては、では全く歯の立たない相手で、いつも厳しい叱責を受けているが、そのどれもが理に適ったことであるので、は師としての彼を尊敬していた。
「手数をかける。三成殿にも、よろしく伝えてくれ」
御意、と短くこたえて、五助は立ち去って行った。室内に張りつめた緊張の糸が、緩む。
「あいつほんと、もう少し愛想とかないんすかね」
鎌之助が口を尖らせるのをは苦笑で応え、そのふたりを見つめながら淀が襖の向こうに控える侍女たちに声をかける。
「姫が、着替えるから。準備して」
「……本当にあれを着るのか?」
五助の来訪で話題が逸れたと思ったのに、淀は何一つ気にしない様子で小物類の準備の指示を出していく。
そして静かだがどこか有無を言わさない強さを秘めた表情で、に言った。
「お迎えの支度は、しておきましょう。真田どのが、お忙しいなら、なおさら、いつ来られるか、わからないもの」
鎌之助が「そうっすよ」と淀に賛同する。
はどう答えていいかわからず、曖昧な表情で頷いた。
春らしい薄紅の色を基調にした打掛は、最高級の唐織物で仕立てられたものだ。手がけた職人の腕は確かで、煌びやかでありながら派手すぎない気品が感じられた。小物類を含めて全身着飾ったの姿はまるでこれから嫁入りしようかという出で立ちである。
――そう、あまりに華美だった。
淀が着るなら、まだわかる。彼女は豊臣秀吉の側室で、太閤亡きあとも天下にその名を轟かす豊臣家の世継ぎの母君だ。既婚であるということから、このような可愛らしい柄の着物は選ばないかもしれないが、それにしたってこのような装束は豊臣家の奥方でなければ、所領が百万石に近づくような大大名家の姫君が身に纏うものであって、たかだか敦賀六万石程度の規模でしかない大谷家の、まして自分のような男女(おとこおんな)が着るようなものでは、断じてないはずだった。
「はー!さん似合いますよ!きれいっす」
着替えの間外していた鎌之助が戻ってくるなり感嘆の声を上げ、どう答えてよいかわからなかったはどこか不機嫌そうに呟いた。
「……いつにもまして、身動きがとれないのだが……」
「我慢なさいな、おなごはそうやって、着飾るものよ」
自らの着替えを手伝った淀殿は対照的に満足気な様子で言う。
「それに、姫。褒められた時に、お礼を言わないのは、悪よ」
言われては「うっ」と声を詰まらせて、そしてぐぎぎと軋む音をたてそうな動きで鎌之助を見ると蚊の鳴くような声で言った。
「……鎌之助。ありがとう」
「いやっ、そんなっ、お礼言ってもらうようなことじゃないっす!でもほんと、さんて人を褒めるのは得意なのに自分が褒められるの苦手っすよねー」
「そういえば、そうね。下働きの子に、気立てが良いとか、普通に言うのに」
鎌之助と淀が口々に言うのをそれぞれ視線で追ってから、は眉根を寄せる。
「……それが正当な評価なら、わたしだって褒められたら嬉しい、と、思う」
例えば、戦で武功をたてるとか。小田原の北条家に仕えていたころはそれこそ、兜首(かぶとくび)を幾つ挙げたとか、味方の危機を救っただとか、そういった眼に見える戦果を認められるのは誇らしいことだった。
……だが、今は。
「淀殿も、仰ったではないか、わたしはややを産めるような、おなごらしい身体つきをしていないと。十年以上も男をやっていた身体はそうすぐにどうなるものでもあるまい、だから、こういった装いも、わたしに似合うとは……思えなくて」
考えながら言うと、鎌之助が困ったような表情をした。
それを見て、ははっと口を噤む。
今の言い方はよくない。これではせっかく褒めてくれた鎌之助の言葉を真正面から否定してしまったようなものだ。
それでも、考えてしまうのだ。
戦うことを第一に鍛えた身体は、女性らしい丸みとは無縁で、以前侍女たちを怯えさせてしまったように生々しい傷痕が多い。刀を握り続けた手指はお世辞にも綺麗だとは言えないし、そして、顔だって。
……淀殿のようなおなごらしい美しさのほんの少しでも、わたしにあれば。
そうっと窺うように、淀へ視線を向ける。
わかっている、これは醜くてくだらない、嫉妬心だ。
かつて小田原で、若輩の自分が重用されていることを面白く思っていなかった、あの大人たちと、自分は何も変わらないのだ。
大谷家の姫である以前に、ひとりの武人であると、大坂に来たばかりの頃義父の家臣である五助に言った。ならばこれでいいはずではないか。たとえおなごらしい美しさや可愛らしさと無縁でも、自分には剣の腕がある。戦う力がある。いざとなれば幸村の隣で、戦場を駆けるだけの力があるのだ。それでいいと、何故納得できない。
……どうして、
己の器はこんなにも、矮小なのだろう。
黙り込んでしまったを見つめる淀は、ぼんやりとしたいつもの様子を変えない。
「あなたのいまの身体じゃ、ややは産めない、確かにそう言ったわ。でも、それと、これは、別の話。おなごは誰だって、きれいに、うつくしく、着飾っていいの。幸い私やあなたは、それができる立場にあるもの」
「しかし……」
「いいこと、姫。あなたが、もっとうつくしくありたいと、思うなら、それを咎めることは、誰にもできない。うつくしくあろうと、努めるならば、おなごは誰だって、それを誇って、いいのよ」
誇る。今の自分には、分不相応な言葉だと思いながら、しかしこれ以上反論するのも淀に対して失礼で(何しろ対等であるかのように接してもらっているが、家柄や立場は淀の方が明らかに上なのである)、には是と答えることしかできなかった。
それからというもの、侍女たちのどこか浮き足だった様子を肌で感じながら、は自室でただ座して一日を過ごした。淀と縫い物をしながらも、足音が聞こえる度に片づけて部屋を整え、しかし全く関係のない者の足音であったとわかっては緊張が緩んで吐息することの繰り返し。
鎌之助は何度も様子を探りに行っていたようで(はそのような偵察は不要だと言ったのだが鎌之助は聞かなかった)、幸村がわずかな供だけを連れて城に入ったところまでは把握できたが、その後の動きは杳として知れなかった。
そして、夕餉を運ぶ女中たちの動きがせわしなくなってきた頃。
その日幾度目かの偵察から戻った鎌之助はの姿を見て「あれっ」と声をあげた。
「さん、もう脱いじゃったんですか?」
きらびやかな打掛を脱いでいつもの小袖姿に戻っていたは、鎌之助の姿を認めて小さく笑う。
「鎌之助、ご苦労だった。なに、もう日も暮れる、今日はもう来られないだろう」
「まあ、そうかもしんないっすけど」
せっかくかわいかったのになあ、という鎌之助のつぶやきは聞こえなかったふりをした。
そのことに鎌之助は気づいたかもしれないが、気にする風もなく膝をつく。
「幸村様は大谷と一緒に大坂をまわってたみたいっす。長も来てるみたいなんすけど取り込んでるみたいで、明日にでも会いに行ってみます」
「……いや、幸村殿も佐助も忙しいのだろう。貴方にそこまでしてもらわなくとも、待っていればいいのではないか。会わなければならない理由もないのだし」
「さんそれ本気で言ってるんすか?」
鎌之助が膝を進めてそう言うので、は首を傾げた。
「嘘を言って何になる」
「や、だって、幸村様が来てるんすよ?」
「それはわかっているが」
「もうしばらく会ってないじゃないすか、顔も見てないじゃないっすか」
「そうだな」
「なら、寂しくないんすか?すぐそこにいるんすよ、会いたくないんすか!?」
鎌之助の語気に、はわずかに眼を見開いた。
少しばかり落ち着きがないところがあるものの、いつもを気遣ってくれるこの男が、そのに対して眉をつり上げたのはこれが初めてだ。
の反応に我に返ったのか、鎌之助は飛び退くように後ずさるとがばりと平伏した。
「っ、すんません!」
「いや、いいんだ」
顔を上げてくれとが言えば、鎌之助はおずおずと頭を上げながら口を開いた。
「ほんと、すみません。さん、なんか今朝から、……幸村様が来るって俺が言ってから、あんまり元気がなさそうだったんで、是が非でも幸村様にお会いされたほうがいいんじゃないかって、……ほんと差し出がましかったっす」
はその言葉を租借するように、ゆっくりと瞼を降ろす。
「……心配をかけて、すまなかった」
「そんな、さんが謝ることじゃないっす」
「いいや、今日は朝から貴方にも淀殿にも失礼なことをしてばかりだ」
そう言って、は瞼を持ち上げる。
「鎌之助。すまないが、しばらくひとりにしてくれないか」
その言葉に、鎌之助は何事か言おうと口を開きかけたが、の表情を見て口を噤むと、もういちど頭を下げて部屋を出て行った。
そういえばこういうとき、佐助や甚八であれば音も無く姿を消すものだが、律儀に襖を閉めて出ていくところなど、鎌之助が忍びらしくないところだとは思う。
音も無く閉じられた襖を見つめて、は小さく息を吐く。
鎌之助の言うとおりだ。今朝、幸村がこの大坂に来ていると聞いたときから、自分はどうも様子がおかしい。妙に胸が苦しくて、すわ幸村が来たかと部屋を片づけるたびに内心冷や汗をかいた。まるで、悪事が見つかった童子のように。
――幸村と、顔を合わせるのが、怖い。
それが、様子がおかしい理由だと、は考えていた。
自分でも妙な話だと思う。
北条から武田へ戻された黄梅院の従者として甲斐の地を踏んで、幸村と出会って。
はじめのころ、高飛車な態度を崩せなかった自分とはあまりにも違う幸村を、苦手だと思ったことがあった。それでも怖いとは思わなかった。いつでも真っ直ぐな彼に惹かれて、己の恋心を自覚して、しかし叶わぬものだと理解した。ひとりで悩んで、ねじくれた感情を幸村にぶつけて、喧嘩をしたこともあった。がどんなに無礼な物言いをしたって、喧嘩をした後ですら、彼はに手を差し伸べてくれた。いつだって、絶対に、を見捨てなかった。
――そして、幸村の隣が、の居場所になった。
出会って一年ほど、ほとんど毎日を彼の隣で過ごして、辛いことも苦しいこともあったけれど、確かに笑うこともあって。
――石田三成との同盟のため、大谷吉継に養子入りするという名目で大坂に残ることになって半年足らずが経つ。
鎌之助に言われなくても、寂しいと思うことがあった。会いたいと思うこともあった。
……それが、どうして。
幸村に会うのが怖い、その理由は、どのような顔をして会えばいいのか、会って何を話せばいいのか、それがわからないからだ。
あれほど毎日一緒にいたのに何故、と考えれば、あの頃は毎日が必死だったからだと、思う。
桶狭間での今川の敗北、北条攻め、本能寺で魔王・織田信長が横死してからは勢力を拡大する豊臣に対抗するべく薩摩に赴いた。いつでもやらなければならないことがたくさんあって、は幸村と常に同じ方向を向いていて、話すにしたって話題など決まりきっていたし、多少物言いが無礼でも恐らく幸村は気に留めずにいてくれたのだ。
それが、今は。
淀に教えを乞うようになって、は自分が至らないことを日々思い知っている。
立ち居振る舞いに教養、何においても女としての自分は欠けたところだらけだ。
そんな自分が、女の恰好(なり)で、幸村の、――だいすきなひとの前で、どう振る舞えばいいのかが、わからない。
……いや、わからないのでは、ない。
失敗するのが、怖いのだ。
いまだに着物の裾を踏むことがあるし、縫い物もろくにできないし、日々の奥の務めや雑事に関わることは淀から学びつつあるが、そういったものはわざわざ幸村に話すことでもないし。
何か粗相を働いて、それで幸村に幻滅されたら。
……もう少し、女としてまともに見られるような状態になるまで、幸村には会いたくない。
それが、本音だ。
だが、鎌之助が言ったことも、正しいと思う。
他でもない幸村が、同じ城の中にいるというのに、会いたくないなどと思う自分は、なんという不届き者なのだろう。
「……よくない、な」
これでも自分のことはよくわかっているつもりだ。
悪い方悪い方へ考える、良くない癖が出てきている。
もうすぐ夕餉の膳が運ばれてくるはずだ、それまでに落ち着いて、きちんと食べなければ。
これ以上鎌之助にも淀にも、心配をかけるわけにはいかない。
部屋から出た鎌之助は、その真上にあたる屋根の上でぼんやりと胡坐をかいて、今日最後の西日に眼を細めている。
「……わかっては、いるんすよ」
ぽつりとつぶやく。
の様子は、あきらかにおかしい。自身もそれを自覚しているようだった。
原因といえばおそらくは、昼間に着替えたときにが淀へ吐露した女というものに対する劣等感ではないかと思う。
「オトメゴコロ、ってやつなんすかね」
正直なところそれは、鎌之助には理解の及ばない物事だ。
鎌之助から見れば、は十分にきれいだと思うし、今日の着飾った格好などは「めっちゃかわいい」と内心感嘆したのだ。
……それをうまく、伝えることができなかった。
佐助ならきっと、上手にの話を聞いて、なにがしかの助言をすることだってできただろう。今は所用で外している淀だっていい。そもそも淀が相手なら、だって心情を口にしたのだ。
それは恐らく、にとって淀が、名実ともに身分の高い人物だからだろう。自分より立場が上の女性にならば、それがたとえ無意識であれ、頼ることもできるのだ。
「っつうか、幸村様がさっさと顔見せに来てくれて、さんのこと一言かわいいって言ってくれるだけでいいんすよ」
何も難しく考えずとも、それで全て解決する。
ぶつくさと呟きながらそこまで考えて、両手を背後について空を見上げる。「あー」とか情けない声が出た。
鎌之助は佐助ほど、うまくの話を聞いてやれない。淀ほどの身分も立場もない。
もちろん、幸村になどなれはしない。
自分は途方もなく、役立たずだ。それは自分でもよくわかっているだ。
……悔しいなあ……。
頭上を鴉が一声「カア」と鳴いて飛び去って行く。その鳴き声にすら馬鹿にされている気がした。