あそこは、この海の世界の終わり。
あの先には何があるのだろう。
「旦那ァ、またここにいたの」
声がかかって、幸村はそちらを振り向いた。ゆらり、と一筋長く伸ばした髪が揺れる。
「佐助」
すい、と幸村と同じ高さまで泳いできた佐助が、眉を下げる。
「ほんとに飽きないねぇ。そんな上ばっか見てて何が楽しいの」
「佐助は興味がないか?あの光の見える、この世界の終わり。その向こうに何があるのか」
「何言ってンの、忍びの俺様の興味の対象なんて、主のアンタ以外にないんだから」
「そうか。――あの先は、人間たちの世界だ。我らではない、者たち。強者も多くおることだろう。そう思うと奮うではないか」
このあたりは、海流が穏やかだ。
頬を撫でていく水の感触が、心地よい。
だがあの先には水がない。
替わりに風なるものが吹いていると聞く。
佐助が溜息を吐いたのがわかった。
「俺様には理解できないよ、人間なんか関わり合いにならない方がいい。あいつらは平気で嘘をつくし、同族だって殺せるんだ」
「それはわかっておる、だが――」
尚も言いつのろうとした幸村の視線の先。
小さく小さく、だが確かに見える。
「佐助、あれは何だろう」
「あれって?」
あの光のある方だ、と指差す先、この世界の終わりに近いところ、一見幸村や佐助と変わらない姿かたちだが、
「え、なにアレ胴の先が二股ってまさか」
「――人間だ!」
言うなり、幸村は弾かれたように泳ぎ出す。
「あ、ちょ、旦那!」
瞬発的な遊泳速度で、幸村に敵うものは、この国にはいない。
佐助はがりがりと頭を掻いて、本日何度目かの溜息を吐いた。
どうせ一介の人間ごときが、この海の世界において、真田幸村の敵となろうはずがないのだ。
ごうごうと耳のそばを水が奔る音がする。
幸村は目指す先を見据えたまま、背の槍に手をかけた。
この海の国は、強大な王の支配下にあるとはいえ、常に平和であるわけではない。
ごく稀ではあるが、反対勢力からの攻撃を受けることもあるため、幸村は常に槍を携えている。
近づくにつれ、その者の姿が明らかになる。
初めて見る、人間だ。
佐助が言った通り、胴から先が二股に分かれている。蛸や烏賊など、足が分かれている者はこの国にもいるが、二股というのは見たことがない。
さらに、その身体には
身に纏っている珍妙な装束は泳ぐに適しているとは到底思えず、これではここで生きてはいけまいと思った。
そう、人間はこの海の中では生きていけないらしいのだ。
触れられる距離まで近づいて、幸村は槍から手を離した。
その人間には意識がなく、ゆっくりと沈んでいる。
思わず手を差し出し、その身体を支えた。
この人間は、このままにしておいたら死ぬ。
そう思うと、いてもたってもおられず、その細い身体を抱きしめて、幸村は上へ跳ぶように尾鰭を動かす。
この人間を死なせてはいけない、それだけを思って、
世界の終わりを目指した。

波の音が、聞こえる。
自分は、何をしていたのだったか。
確か、海の見える崖で、鍛錬をしていて。
それがどうなって、今に至るのか――
思い出そうとして、しかしものを考えるのが酷く億劫だ。
身体が、動かない。
なんだかとても、眠い――
「・・・・・・り!・・・・・・のだ!!」
何か聞こえる。
なんだろう、と意識をそちらに向ける。
「しっかりするのだ!!」
その瞬間、喉の奥が苦しくなった。
「――がッ、げほ、ごほッ、」
水を吐き出す。潮の臭いが鼻につく。
あらかた水を吐き出すと今度は肺が空気を欲して、息を吸おうとするのに咳き込んでうまく吸えない。
「大丈夫、もうここは海のなかではござらぬ、ゆっくり呼吸するのだ」
声が聞こえて、背中をさすられる。
なんだか安心して、漸く呼吸が落ち着く。
ひゅー、ひゅー、と自分が息をする音が、聞こえる。
身体の感覚が戻ってきて、自分が誰かに抱きしめられているとわかった。
眼を開ける。
その視界に飛び込んできたのは、鮮やかな、紅。
焦点があって、それが魚の鱗であると気付く。
・・・・・・魚?
そう思って視線を上げる。
自分を抱きしめているのは確かに人間と同じ腕で、目の前には逞しい胸板、目線を上げると人間と同じ顎、
――眼が合った。
優しい、鳶色の瞳。
見惚れるというのはこのことであるかと、思った。
なんてきれいな男だろう。
「ッ、も、申し訳ござらぬ、」
突然そう言って、男が手を離し、海へ飛び込んだ。
そこで漸く、自分の置かれている状況がわかる。
そこは、砂浜の波打ち際だった。
足元を、穏やかな波が打ちつけては引いて行く。
全身がずぶぬれで、身体が重いのは服が水を含んで重くなっているからだと理解した。
そして、少し離れたところからこちらを見ている、わずかに顔を赤らめた彼の姿。
上半身は、人間の男。年のころは自分とそう変わらない、青年だった。
だがその、人間でいえば
「あの」
声をかけると、びくりと肩を震わせた。
「貴方が助けてくれたのだろう。礼を言う。わたしの名は、。貴方の名を、聞いてもいいだろうか」
彼は少し迷うようなそぶりを見せ、口を開こうとして、突然口元を抑えると、海に潜ってしまう。
すぐに顔だけ海面から出して、言った。
「某は、ここでは息ができぬゆえ、これで失礼いたしまする」
それだけ言い置いて、小さな水飛沫をたてて潜っていった。
最後にちらりと、見事な紅色の尾鰭が、見える。
「・・・・・・」
魂が抜けたように、は「彼」が消えた海面を眺めていた。
「さまッ!」
背後から声がかかる。声で自分の従者だと判断した。
「一郎」
「ちょ、生きてますか!?ああもう、鍛錬に気を取られて海に落ちるとか、もうほんとマジ勘弁してください!」
「すまない」
一郎に助け起こされながら、はつぶやいた。
「助けて、もらったのだ」
「え?」
一郎が聞き返す声には答えずに、思いを馳せる。
お伽噺だ。
その昔、とある国の王子が船から海に落ちたとき、半人半魚の美しい女がそれを助けたという。
「・・・・・・その名は」
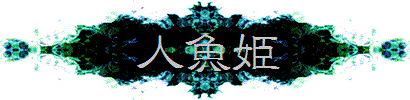
「世界の終わり」の向こうは、息ができない苦しい世界だった。
それでも、あの太陽が、眩しく光っていた。
ふうわりと頬に感じたあれは、風というものだ。
あたたかく、きらきらした、「向こうの世界」の全てのイメージが、そうして彼女に繋がる。
なんて美しいおなごだろうと思った。
その深い色の瞳から、眼が逸らせなかった。
名前を聞いた。
。
そのことばを思うだけで、胸の奥が苦しい。
自分は何かの病ではないのかと思う。
彼女にもう一度、会いたい。
「・・・・・・それで私を訪ねたというわけかね」
この国の外れ、海藻の森に囲われて薄暗い場所。
水の流れがなく、すべてが
「左様でござる。この海の魔術師と名高い貴方なら、某が人間の世界に行く方法をご存じではないかと」
「ふむ。確かにこの久秀、その方法を知らぬわけではない」
「なんと!」
「だが、何事にも代償が必要だ」
「代償・・・・・・、何でござろう」
聞き返すと、松永久秀と言う名の魔術師はその黒く長い鰭をずらりと動かし、幸村の眼前までやってきた。
「まずは、卿の声」
「声?」
「ああ。卿も一度行ったのならわかるだろう、あの世界では我らは呼吸ができない。その呼吸をするために、声を発する器官を代償にする」
「声が出なくなる、ということでござろうか」
「その通りだ」
幸村は頷いた。彼女にもう一度会えるなら、声など。
「問題はござらぬ」
「結構。それでは、もう一つ」
「代償が、他にもあると申されるか」
魔術師は鷹揚に頷いた。
「なに、今の卿には簡単なことだ。この薬は、真実の愛を必要とする」
「・・・・・・愛?」
聞き返した幸村に見えるように、硝子の小瓶を掲げて見せる。その中には、赤黒い液体が入っている。
「これは人間の血液だ。これを飲めば、確かに卿は人間となる。しかし、愛を得ることが叶わなければ、その身体は泡となって消えるのだ」
「消える、だと」
幸村が眉根を寄せると、魔術師の黒い尾鰭が、幸村の身体を包むように蠢く。
「おや。卿は彼女を我が物にしたいと思ったのだろう」
「そのような、ただ今一度会うことが叶えばと」
くつくつと、笑う声が聞こえる。
「同じことだよ、真田幸村。我らは欲望に忠実だ。彼女にもう一度会うだけで卿は満足するのかね。違うだろう?今度は声が聴きたい、名を呼んでほしい、そして触れたい――そう思うはずだ」
幸村は唇を噛む。
「ッ、そのような、ことは」
「何、恥ずべきことではないのだよ。それこそ愛のかたちだ」
魔術師の眼が、笑みのかたちに孤を描いて歪む。
「さァ、どうする?この薬で人間となり、愛を得るか?それともこの海の底で、何一つ変わらぬ毎日に身を
そうして、
幸村は硝子の小瓶を手に取った。

謁見の間で、は主を前に膝をついていた。
「先だっては海に落ちたと聞いたが、大事ないのじゃな?」
「は、ご心配をおかけし、申し訳ござりませぬ」
王座に腰掛ける老王は、うむとひとつ頷く。
「それは僥倖。今そなたの身に何かあっては困るからのう。それはそうと、そなたまだそのような格好をしておるのか。ドレスを見立てたじゃろうに」
「・・・・・・ドレスは、動きづらいのです」
は自分の男装を見下ろして言う。
しかし老王は渋面のままだ。
「ならぬぞ、。そなたは養子とはいえ、この国の姫じゃ。そして婚儀を控える身じゃ。姫らしゅうせぬか」
「・・・・・・」
は一切表情を動かさず、口を引き結んだ。
はそもそも、この国に仕える騎士のひとりだった。
女風情がと陰口をたたかれることは常であったが、その誇りだけを胸に戦ってきた。
世はまさに群雄割拠。この国も、いつ他国から攻め入られるかわからない。
国王は国の安定を保つため、隣国と同盟を結ぶことに決めた。
年若い王が治める隣国は、領土が広く、勢いもある強国である。
同盟のため、その王と婚姻を結ぶことにした老王にはしかし、子どもがいなかった。
そのため、城内で唯一の若い女であったに白羽の矢が立ち、王の養子としてこの国の姫になったのは先月のこと。
そこから先はの意思とは全く関係なく、来月に控えた婚儀の準備が続いていた。
政略結婚など珍しくはないことくらい、も知っている。
そもそもは結婚したいとも思っていなかったから、愛だの恋だのということには関心がなかった。
ただ、これまで騎士としてこの国に仕えたことが、結局は何の役にも立たなかったのだと思い知らされる毎日に、辟易としていた。
この国を守るため。そのための婚儀。
それがに残された、最後の矜持だった。
それなのに。
あの日から、彼の姿が頭から離れない。
あの、鳶色の瞳。
彼は、海の世界の住人だろうか。
見事な紅の鱗が、脳裏を過ぎる。
「――聞いておるのか、」
王より声がかかって、は我に返る。
「は」
「とにかく、まずは女らしい立ち居振る舞いを身に着けるのじゃ。よいな」
「・・・・・・は」
海の世界はどのようなところだろう。
ここよりは、自由なのだろうか。
――とかく、この世は生きづらい。
謁見の間を後にして、は海に面した回廊を進む。
あの日以来、海辺を見るのが癖になっている。
こうして見ていれば、また彼が海から顔を出すのではないかと思われて。
「・・・・・・重症だな」
自嘲の笑みが口の端に浮かぶ。
いったい彼が何だというのだ。
来月にはもう、この海ともお別れだというのに。
婚約者とは、一度顔を合わせた。
若く聡明で、見目も麗しい。不幸な政略結婚を強いられる姫君が多いこの世において、自分は恵まれているのだと理解はしている。
そうやって、婚約者の顔を思い浮かべてみても、結局はあの彼に意識が向かう。
ひとつ息を吐いて海から視線を戻そうとして、
「――?」
視界の端に何か見えてた。
ここからでは遠い。
あの、砂浜の波打ち際。
人が、立っているように見える。
まさか。
判断の前に、は駆けだした。
回廊を飛び下り、柵を飛び越え、砂を蹴立てて走る。
その姿が近づく。
彼だった。
あの時の、紅の鱗はなく、そのかわりに人間の足で、砂浜にたっている。
彼がこちらに気づく。
その顔が、輝くように笑う。
ああ、なんて顔で笑う男だろう。
波に濡れていない砂の上で立ち止まって息を整える。
彼が恐る恐る、という風に一歩踏み出し、二歩目はもう駆け足になって、を抱きしめた。
「わ、」
飛びつかれてさすがに驚いたがたたらを踏む。
しかし彼はぎゅう、とを抱きしめる腕の力を緩めない。
「あの、先日助けてくれた、貴方、だな?」
こくり、と彼が頷くのがわかる。
「もう一度会えればと、思っていた。先日は助けていただいた礼も満足にできず、申し訳ない」
そう言うと、今度は彼が首を横に振る。
「でも、貴方はここでは呼吸ができないと言っていたではないか、なぜまた来たのだ」
彼が押し黙る。
の肩に両手を置いて、身体を離し、こちらを覗き込むように見つめてきた。
「・・・・・・もしかして、わたしに会いに来てくれたのか」
抱きしめられたのだからそれくらい自惚れてもいいだろうかと思ってがそう口にすると、彼は笑顔でうなずく。
彼の口が、二、三度動く。声はない。彼が落胆したように眉を下げる。
それに気づいて、問う。
「貴方、声が・・・・・・?」
彼が頷く。
は嘆息する。
「そうか。名を聞こうと思っていたのに、残念だな」
そう言うと、彼は少し驚いたように眼を開く。
は口の端を上げる。
「意思の疎通はできそうだから、そう困ったことではなかろう?だが貴方のことは何と呼べばよいかな、」
溺れたところを助けてくれた、海の国の美しいひと。
その単語が、の頭に浮かぶ。
「では、貴方のことは人魚姫と呼ぶことにしよう」
彼が困ったような顔をするのがわかったが、としてはこの名はぴったりだと思われたので、彼が話せないことをいいことにそう決めた。
なぜだか、これまでになく楽しい気持ちになって、すこし笑った。
201206025 シロ@シロソラ

