
9月28日(金)午後7時37分
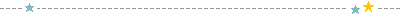
「――はい。・・・・・・はい。それは承知しております」
契約管理課長である片倉小十郎は、週明けの月例会議のための資料をパワーポイントで作成しながら、ふとパソコンの画面右下の時計表示を見た。そしてデスクトップのディスプレイ越しに、向かいの席の部下が完全な無表情で電話応対しているのを見つめる。通話が始まってすでに二十分以上が経過している。
「――それは先ほども申し上げたとおりです。・・・・・・いいえ、規則だからではありません。お客様の権利の保護のためです」
経理部門ではないから九月末の半期決算の処理もすでに終えていて、金曜日ということもあってかフロアには人影もまばらだ。契約管理課もほとんどの課員がすでに退社し、デスクを向い合せに並べたこの「島」に残っているのは課長の小十郎と向かいの席ののみ。全国に点在する支社もだいたいは営業を終了しているのだろう、終業間際の夕方以降からフロア中で鳴り止まない電話も今はもうこのが応対しているもののみで、そのおよそ感情を覗かせない声が小十郎にもよく聞こえていた。
本社ビルのワンフロア全体を占めるこの部署は、全国の支社の営業支援を主な業務としている。新商品が発売される際にはその詳細の研修を行ったり、商品内容に関する資料を作成したり、顧客との間でトラブルが発生すればその対応支援も行う。必然的に問い合わせの電話は顧客よりも支社の営業担当者が多く、そして当然ながら彼らは一般的な営業時間中に顧客への営業活動を行っているため、電話照会は終業時間後であることも少なくはない。そして、最前線で営業活動を行う彼らと、直接顧客対応をすることが少ないこちら本社部署では、折り合いがつかないこともままある。「現場のことを何もわかっていない」は営業担当者たちの常套文句で(それが事実であることも少なくはないので彼らの言うことは一理ある)、ともすると顧客のクレームよりもクレームじみた電話がかかってくることもあるため、主に事務職の若い女性スタッフなどは「変なものに捕まらないうちに」と定時ぴったりに退社する者が多い。
「・・・・・・ええ、それは何度申請いただいても認可できかねます」
は、そうした「事務職の若い女性スタッフ」の分類の中では変わり種だった。
入社七年目という年次は寿退社が多いこの会社の事務職としては年長の方で、実際若いスタッフが多いこの契約管理課でも課長の小十郎に次ぐ年長である。新卒で入社してからこの部署でずっと働いているため、去年の春に他部署から転任してきた小十郎よりよほど業務知識が豊富で、小十郎自身も確かに頼りにしている。年中いつでもジャケットにパンツという、本社の事務職の、所謂OLらしい華やかさとは無縁ないでたちも、一層彼女を頼りがいがあるように見せている、のだが。
「――はい。・・・・・・ええ」
はじめは左手で受話器を持っていたはずだが、いつの間にか肩と耳で受話器を挟んで、パソコンのキーボードを打ちながら応対している。褒められた態度ではないが、もはや展開されている会話が「時間の無駄」レベルなのだろう。
小十郎はしばしキーボードを打つ手を止めて、の顔を見た。美人の部類に当てはまるのだろうが、化粧気が少ないうえに表情の変化にも極端に乏しいので、淡白な印象を与える、しかし個人的にはとてもきれいだと思っている顔立ちだ。
クレームじみた電話をかけてくるような相手は、往々にして「女の声」を侮るものだ。こういう場合はがつんと「男の声」で言ってやった方が簡単に引き下がったりもする。
一目でも、がこちらを見れば、「替われ」とジェスチャーするつもりだった。
だがはパソコンのディスプレイや手元の資料を見るだけで、頑としてこちらを見る気配がない。
いつもそうなのだ。
他の若いスタッフたちは、手に負えなくなれば小十郎に電話を転送してくる。もちろん役職者として、そういった電話の対応も小十郎の仕事のひとつであるから、それについて何か苦言を呈するつもりは全くないのだが、だけはそういうことをまったくしない。決裁権が課長以上の役職者にある案件については例外だが、大抵のクレーム対応は一人でやってのけるし、後輩たちの電話を引き継いで助けていることもある。
責任感が強いのは、決して悪いことではない。ないのだが。
「――課長、ですか?」
声が聞こえて、小十郎はぴくりと眉を動かした。
が、ちらりとこちらを見る。
しかしこちらがジェスチャーするまでもなく、するりと視線を外した。
「課長は今外しております。それにこれは上位者に話をされたからといって認可できるようなことではありません。――はい、そうです。それでは失礼いたします」
生真面目に、相手が受話器を置くのを待ってから、は静かに受話器を置いた。
相変わらず表情を変えない彼女に、小十郎は声をかける。
「――おい」
「はい」
用事があって呼ばれたと思ったのかが立ち上がりかけたので「座っとけ」と制する。
「お前、あんまりしつこかったら俺に電話回せ」
「課長のお時間をいただくほどの用件ではありませんでした」
まっすぐと、小十郎を見つめてはそう答える。身も蓋もないその言い方に、小十郎は短く吐息する。
「・・・・・・それにしたって、それで残業時間伸ばしてたら本末転倒だろうが。お前今月も残業時間ぎりぎりだぞ」
折しも月末、小十郎は夕方ごろに課員の残業時間を確認したところだったので、ほとんど無意識にそう言ってしまってから、しまったと気付く。
それまで完全に無表情だったが、わずかに表情を動かした。小十郎が気づくのに半年かかった彼女の表情の変化。
「・・・・・・申し訳、ありません。以後、気を付けます」
かすかに眉根を寄せたは、そのままマウスを数度動かしてパソコンの電源を落とした。時計はすでに午後八時を指そうとしている。
鞄を手に立ち上がり、課長席の横まで来ては頭を下げた。
「それでは、お先に失礼し致します」
「・・・・・・ああ、気を付けて帰れ」
もう一度丁寧に礼をして、出入り口の方へ歩いて行く淡いグレーのピンストライプのジャケットの背姿を見送りながら、小十郎は溜息を吐いていた。
また、やってしまった。
彼女を叱責しようと思ったわけではなかったのだ。
ただ、少しはこちらを頼るように言いたかっただけなのに。
「・・・・・・上手くいかねぇもんだな・・・・・・」
ぽつりとつぶやいてから、首を回したら、驚くほどいい音がした。
10月1日(月)午前8時30分
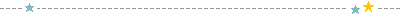
結局土曜出勤までしてようやく仕上がった会議の資料を確認しながら、小十郎は向かいの席に視線を投げた。
はまだ出社していない。
珍しいことだった。始業は九時だからそれまでに来れば遅刻ではないが、は大抵八時ごろには席にいることが多い。小十郎の出社時間とだいたい同じである。会社の最寄駅までの地下鉄で鉢合わせることも多いのだ。
何とはなしに、久しぶりに締めたネクタイに手が行った。九月末でクールビズは終了し、今日からはまたネクタイ・上着着用の毎日である。十月に入ってもまだ日中は暑く、ネクタイを嫌がる同僚も多いが、小十郎はネクタイが嫌いではない。むしろ気が引き締まるようで好きである。今日のネクタイは先週買ったばかりの新品だった。
はもしかしたら体調不良かもしれない、と小十郎はデスクの引き出しを開けながら考えはじめる。
めったなことでは有給を消化しない彼女は、年に数度病欠する。季節の変わり目にひく風邪であることが多いようだが、何にしろ普段から無理のし過ぎなのだ。きっと発熱するまで病院になど行かないのだろう。しっかりしているように見えて、特に自分のことには無頓着なのがの困ったところである。
九時前から月例会議だが、戻ってきても出社していないようだったら家に電話をした方がいいだろう、確か連絡先一覧はこの辺にしまったはず、と引き出しの中を見ていた小十郎の耳に、悲鳴のような声が飛び込んできた。
「えー!さんどうしたんですかー!?」
「・・・・・・おかしいか?」
「え、ちょ、めっちゃかわいーですー!ていうか美人!」
「わ、ほんとだすっごいキレイですさん!」
戸惑うような声は聞き間違えるはずもなくのもので、それを囲むような声は色をつけるならまさに「黄色」。
頭を上げて見てみればそれは自分の部下たちとわかって小十郎は眉をひそめた。
「おいお前ら、朝から何を騒いで――」
やがる、と続くはずだった声が、途切れた。
群がる後輩たちに囲まれるようにしながら、がこちらに歩いてくる。
気が付いた他の課の者たちもどよめいていた。
程よく身体の線を出す、淡い色の薄手のニット。ふわりと広がる膝丈のスカートからのぞくのは、ストッキングに包まれているとはいえ初めて眼にするすらりと細い足で、そのまま華奢なヒールのエナメルのパンプスに続いていく。いつもは首の後ろでひとつにまとめているだけの髪は下ろされていて、緩やかなカールが顔の周りを彩っていた。
すう、との眼がこちらを見る。小十郎は女性の化粧に関する機微には疎いのだが、それでもさすがにわかった。今日のは、いつにも増してきれいな顔をしている。元から長いがさらに長くカールした睫毛、うっすらとピンク色の頬。
「・・・・・・おはようございます、課長」
いつもと同じく課長席の横まで来て、はそう言って頭を下げた。
「・・・・・・おう、おはよう」
若干言葉を失いながらもそう答えれば、はいつものように向かいの席につく。相変わらずの無表情、しかし小十郎の視界は明らかにいつもより華やいでいる。
ふと、がこちらを見た。
ひたり、とその視線が小十郎の胸元を見て止まる。
「・・・・・・どうかしたか?」
聞かれたことが意外だったのか、はわずかに表情を動かした。
「・・・・・・その、ネクタイは、――新しい、ですか」
どこかぎこちない、中学生の英語の例文みたいな問いに、小十郎は少し面食らった。
「ああ、先週買ったところだ」
は小十郎のネクタイなぞクールビズの4か月間は見ていなかったはずだ。なのにわかるのか。
驚きながらそう答えると、しかしは「そうですか」とよくわからない返事をし、それ以上のネクタイに関する言葉はなかった。
何なのだろう。
そう思っていたら内線が鳴った。会議の開始時刻を過ぎても会議室に来ない小十郎への催促の電話で、慌てた小十郎は立ち上がりざまに会議資料をぶちまけてしまった。
10月2日(火)午後3時15分
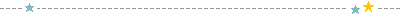
「あー、噂の美人サンだー」
間延びしたような声を聞いて、小十郎は決裁書類から顔を上げた。
向かいの席のが仏頂面で見上げているのは、システム管理部門の猿飛佐助だ。このフロアのシステムを担当しているので、小十郎も何度かシステム開発でやり取りしたから見知っている。信じられないことに地毛だという明るい髪の毛が目立つ、何とも軽薄な印象の男だった。
「すまない、佐助」
「いーってこれくらい。ってかちゃんが締め出しなんて珍しいねェ」
言いながら佐助はのパソコンのキーボードを滑るように打っている。
午後一番の会議が終わって戻ってきたら、昼休みと合わせて数時間触れなかったパソコンがスリープ状態になっていた。普通に起動時と同じパスワードを入力すればロック解除されて通常通り使用できるのだが、何を慌てたのかはそこで三回連続でパスワードを誤り、完全にロックがかかった自分のパソコンにログインできなくなってしまったのだ。小十郎の知る限り、が自分のパソコンにロックをかけてしまったのは初めてのことだ。彼女らしからぬミスである。
そういうときはOA機器関連のトラブル対応を一手に担うシステム担当者の出番で、先ほどが自分で連絡していたのだが、社内パソコンのロック解除くらいなら遠隔操作でもできるものを、猿飛佐助がわざわざここまで足を運んできたのは単にフロアが近いという理由だけだろうか、と小十郎は考えている。
「これはアレかな、最近やたらとかわいくしちゃってることと関係あんのかな?」
「・・・・・・関係など、ない」
むすりと答えるの今日の格好は柔らかな素材のブラウスにタイトな膝丈スカート。スカートの腰回りにフリルが付いているのは、今年流行のなんとかというデザインらしい。先ほど部下が言っていたのを小十郎は聞いていたのだが、一度聞いただけでは覚えられなかった。国民的竜退治RPGに出てくる魔法みたいな名前だったと思う。今日もゆるく巻いている髪は、下ろしたままだと顔にかかって邪魔だったのか、可愛らしいデザインのクリップでハーフアップにまとめている。
「えー、でもさ、おんなのこがおしゃれするときって、気になる人がいるときなんでしょ?」
くるくると、の背に流れる巻かれた毛先を指先に巻きつけながら、そう言った佐助を、はぎらりと睨んだ。
「!」
その表情に、小十郎はわずかに眼を見張る。
表情の変化に乏しい彼女が、明らかな敵意を剥きだしにするように誰かを睨むなど、初めて見たからだ。は基本的に、他人にあまり関心を抱かないらしいと小十郎は理解している。だから相手に対して笑いかけることはほぼないが、怒るということもまずしない。そのが、眼に見えて感情を表情に現したということは、彼女にとって猿飛佐助は少なからず関心のある人間ということだ。その頬がわずかに赤いのは、化粧のせいか、それとも。
「そういうことでは、ない」
「ふーん?」
佐助はの髪から手を離すと、しゃがみこんで覗くようにの顔を見上げる。
「ね、なんか悩んでるならさ、相談乗るよ?」
「――猿飛」
小十郎の声に、肩を強張らせたのはだった。
「のパソコンは直ったんだろう」
無意識だったが、ドスの効いた声が出た。佐助が大仰に肩をすくめる。
「相変わらず怖いお人だね、片倉の旦那」
そう言って立ち上がると、佐助はぽんぽんとの頭を軽く撫でる。
「じゃ、ちゃん、また何かあったら呼んでちょーだい」
じゃあね、と言って、ついでに小十郎の方に何やら意味ありげな視線を投げてから、佐助は歩き出す。
その背に、我に返ったが声をかける。
「佐助、ありがとう」
礼を言われた佐助がにへらと笑って手を振って行った。
「、」
「騒がしくして申し訳ありません、課長」
何か言う前にがそう言ったので、小十郎は息を吐いた。
「・・・・・・あいつとは、仲がいいのか」
吐息交じりのその問いに、は一瞬視線を泳がせる。
「いえ、特にというわけでは。さす、――猿飛は、同期ですので」
「・・・・・・そうか」
それ以上、小十郎は何も聞かなかった。
ただ、先ほど、去り際の猿飛佐助が投げてよこした視線を思い出す。
あの野郎、一丁前に威嚇していきやがった。
何のつもりなのだか、そう思いながら決裁印を書類に押し、
「・・・・・・あ」
我ながら間の抜けた声が出た。「片倉」の判が、「課長」欄の隣、最終決裁者の「部長」欄に押されている。
「・・・・・・すまん佐藤、これもう一度打ち出してくれるか」
「え?あ、もー何してるんですか課長、成り上がりですかぁ?」
部下の苦笑に、何も言い返せなかった。
10月3日(水)午後8時40分
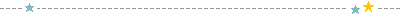
オフィス街の一角にあるそのバーでは、いつも大型のスクリーンにヨーロッパのサッカーチームの試合を映している。ワールドカップ開催時や、日本代表の試合のときは、予約が必要なほどに混むのだが、そうでなければ平日の夜はある程度空いているので政宗がこの店を選ぶことは多かった。世界中のビールを広く揃えているところがいいらしい。
「――で?そこまでハッキリ喧嘩売られててめぇ黙ってンのか小十郎」
ヒューガルデンのグラスを空にしてから、政宗は眉をひそめてそう言った。
伊達政宗は、会社の創業者一族の御曹司である。片倉家が代々伊達家に仕えてきたこともあり、小十郎にとっては歳の離れた弟のようでもあり、忠誠を誓う主人でもある。社内の年次だけで言えばと同期の若手であるが、すでに営業と総務の部署を経験し、この春からは広報部に配属されている。将来を有望視されているのが誰の眼にも明らかなのは、小十郎としても鼻が高いところであった。
「別に喧嘩など売られてはおりません、政宗様」
こちらはいつもと同じプレミアムモルツのグラスをテーブルに置いて、小十郎は淡々とした声色で言った。小十郎は海外のビールにあまり興味がない。日本人がおいしいと感じるのは国産ビールに決まっていると信じているクチだ。
「You kidding!喧嘩じゃなかったら何だってんだ。――まぁ猿のことはいい、それよりだ。聞いた話じゃずいぶんと変わったらしいな?俺も見てみたいもんだ」
「・・・・・・自重なさってください。そうでなくともそういう輩が多いおかげで、も困っているのです」
が謎の変貌を遂げて今日で三日目。
今日は裾からレースがのぞくゆったりとしたニットに七分丈のパンツ。パンツスタイルの方が見慣れているので何故だか安堵したのもつかの間、その分露出する細い足首のきれいさにどきりとした。そして何より、大きめの襟ぐりから見える鎖骨。今日も小十郎は押印の位置を間違えた。
厄介なのは噂を聞きつけて何かとこちらに用事を作ってやって来る野次馬だ。今日は朝からサービスセンターの前田の風来坊が来たのを皮切りに、開発の長曾我部やらあの経理の毛利まで顔を見せた。経理は絶賛決算処理中のはずだ、何やってるんだ。その全てに無表情に応対していただが、内心やはり何かあるのか、らしくないミスを連発していた。報告書に誤字があったり、折り返しの電話番号を聞き誤ったり。
「何があったのかはわかりませんが、あれでは見ておれません」
そうでなくとも、は責任感が強く、そしてプライドの高い性質だ。自分のミスで自分を責めているのに間違いなかった。あまり思いつめなければいいのだが。
「そんな悠長なこと言ってる場合か」
政宗の声に、小十郎は顔を上げる。
「は元が『ああ』だから軽い気持ちで近寄るヤツはいなかったわけだが、それが蝶に化けたってンなら話は別だ。いらん虫が湧いて出るだろうし、それに小十郎、俺の同期の真田を知ってるか?」
「昨年度、全社営業成績一位だった真田幸村ですか」
今年はどこの支社にいるのだったか。年度初めの社報で写真を見たのを思い出す。
「That's right.あの野郎は内定のときからを狙ってンだぞ」
「・・・・・・は」
「猿のヤロウは真田のツレだ、の周りをうろうろしてンのはそういうことかもしれないな?」
政宗が視線をこちらに流してきた。小十郎は俯き加減に、テーブルに置いたままのグラスを見つめている。
その様子に痺れを切らしたように、政宗が頬付けをつきながら口を開いた。
「――なぁ、小十郎。いい加減なんとかした方がいいんじゃねぇ?このままだとはかっさらわれるぞ」
「・・・・・・がそれでいいのなら、」
「あーのーなー、それじゃぁお前はどうするんだよ」
小十郎は小さく吐息して視線を上げる。
「そもそも私はに対してどうこうしようとは、歳だって離れておりますし」
その答えに、政宗はじとりと半眼で小十郎を見つめる。
「なんだお前仙人か聖人か?惚れた女が誰にfuckされようが合意の上ならいいってか!」
「な!政宗様、そのような言い方は、」
「どんなにキレイに言ったところでつまるところはそういうことだろうが。それとも何か?俺の右目は女ひとり口説けないような腰抜けだったのか?」
言い返そうと開いた口から息だけを吐いて、小十郎は一度口を閉じた。ビールのグラスを傾ける。
「・・・・・・、あまりけしかけないでください。私自身、戸惑ってはおるのです」
観念したようなその言い方に、政宗はにいと口角を上げた。
「迷うことなんざ何もねぇよ、お前は俺の知る限りこの世で二番目にいい男だ、それではそういう人間性をきちんと理解して、正面から向き合おうとする女だ。ホラ、何の問題もねぇかねーか」
「一番目」が言うんだから間違いねェよ、と言って政宗が笑う。何の根拠もないのに自信に満ちていて、そして聞いている側にもそれを信じさせるのがこの伊達政宗の持つカリスマ性だ。
小十郎は口元に笑みを浮かべた。諦めたような、それでもどこか清々したというような。
「・・・・・・政宗様は大人になられましたなぁ」
「しみじみ言ってンじゃねーよジジイか」
10月3日(水)午後9時7分
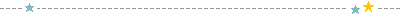
駅ビルの地下に入っているコーヒーチェーンで本を読んでいたは、自分を呼ぶ声に顔を上げた。
「ちゃん!お待たせしてごめんなさい!」
「姫、」
カフェオレとドーナツの載ったトレイを置いて向かいに腰を下ろした友人に、はわずかに眉を下げる。
「相変わらず忙しいようだな」
「こんなのへっちゃらです!・・・・・・とはいえ約束を三十分以上も過ぎてしまいました・・・・・・」
「気にするな、それほど待ったわけではない」
姫、というあだ名で呼んでいるこの友人は、現在は別々の業種で働いているが、学生時代からの付き合いだった。
「――それで、ちゃん!本当に見違えましたねぇ」
「そうだろうか。おかしくはないか?」
「バッチリです!夏の間特訓した成果ですねっ」
ドーナツを頬張りながらガッツポーズをとる姫に、は小さく笑った。
化粧の仕方も、髪の毛の巻き方もこの友人に教わったし、洋服を買いに行くのにも付き合ってくれたのだ。
「ああ、姫のおかげだ」
「やだっちゃんたら!恋する乙女が輝くのは古今東西の理ですっ!――それでどうですか首尾は!上々ですか!?」
身を乗り出すように問われて、は曖昧に頷く。
「ああ、どうだろう・・・・・・、なんだか、日に日に機嫌を損ねているような気がする」
「えっ、どうしてですか?」
「すべてがわたしに起因するものではないのかもしれないが・・・・・・、どうもな、課長も普段なら絶対しないようなミスを繰り返しているし」
言いながら、は思い起こす。提出した書類の検印が漏れていたり、場所が間違っていたり。目の前で自分たちが騒がしくしているからだろうと思う。今日は朝から現れた同期の慶次が「想い人は誰なのか」としつこくて追い返すのが大変だった。サービスセンターは朝が忙しいんじゃなかったのか。そんなこんなで自分もミスを連発し、それもあってだろう、眼の前の席の課長の眉間の皺が日増しに深くなっているような気がする。誓って、そんな顔をしてほしかったわけではないのだ。
「・・・・・・そうそう、上手くはいかないものだな」
「何言ってるんですか、今のちゃんはほんっとーにかわいいんですよ?自信持ってください!」
ふん、と鼻から息を吐きながら姫がそう言うので、は小さく頷いた。
「・・・・・・そうだな」
自分のミスに関しては、本当に自分の不注意以外の何物でもないのだ。慣れない格好に舞い上がっている証拠である。こんなことではいけない。ミスさえなければ、課長の機嫌も直るかもしれない。
片倉小十郎という人物は、人相こそあまりいいとは言えないが、誰より誠実で真面目で、頼りになる男だ。彼に憧れる女性は多く、それでも自分を見てほしくて、振り向いてほしくて始めた変身計画だ。
「もう少し、頑張ってみるよ」
そう言うと、姫はとびきりの笑顔で応援してくれた。
10月4日(木)午後6時20分
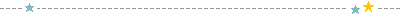
今日もこんな時間になってしまった、と思いながら、はエレベーター横の休憩スペースで、ぼんやりと自販機を眺めていた。財布は持ってきているが、まだ開けていない。何を飲もう。気分転換には炭酸が欲しかったが、生憎ゼロカロリーのコーラが品切れだ。
それにしても、今日はずいぶんと集中して仕事ができたように思う。妙なミスはしなかったし、週明けから溜まっていた仕事もだいたい片付けられた。昨日姫と会えたのがいい刺激になったのかもしれない。
課長も、今日はなんだか調子がいいみたいだったし。
つらつらと考えていたら、小銭の音がした。ちゃりちゃりと自販機に飲み込まれていく音、そして並んでいる飲料見本のボタンが一斉に光る。
「え、」
「好きなのを選べ」
低い声、がばと振り返ると、
「課長!」
小十郎がそこに立っていた。
「ほら、いらんのか?」
自販機を指さされて、は眼を見開く。
「ですが、」
「おごりだ。って百何十円で偉そうには言えないがな、ほら選べ」
「っ、はい、」
自販機に向き直る。落ち着けと念じてからボタンを押す。がこん、と商品の落ちてくる音。
「・・・・・・お前そんなもん飲むのか」
が取り出したリアルゴールドを見て、小十郎は苦笑した。なんだか気恥ずかしくて、は視線を逸らす。
「・・・・・・炭酸が。飲みたかったので」
「そうか」
続けて小銭を入れて、小十郎がボタンを押す。がこん、と落ちてきたブラックコーヒーを取り出して、その場でプルタブを開ける。
「ありがとう、ございます」
「ああ」
例によってこの時間にはもうすでにフロアに残っている人数は少ない。休憩スペースに二人きりで、しばらく無言で缶の中身を飲んでいた。
コーヒーをぐいと飲み干して、小十郎は口を開く。
「」
「はい」
「お前何かあったか。悩みがあるなら聞くぞ」
「・・・・・・」
黄色い缶を握りしめたまま、が動きを止めた。
それを見て、空き缶を専用のごみ箱に放った小十郎は吐息する。
「・・・・・・こういう言い方は違うな、」
そう言って、小十郎がの目の前に立った。
は決して小柄ではないが、ヒールを履いている今でも小十郎を見上げる形になる。
「俺がお前と話したいんだ。、明日夜暇か」
「――!」
が眼を丸くした。
表情の変化に乏しい彼女に会って、初めて眼にするこの表情は「驚愕」を意味すると捉えていいだろう。
だが小十郎には、退く気はない。
「どうだ?」
聞くと、は一度瞬きをしてから、まっすぐと小十郎の眼を見つめ返してきた。
「――はい、暇です」
その視線はまるで、決闘を申し込む挑戦者のようだった。
10月5日(金)午後10時3分
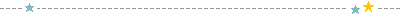
会社のあるオフィス街から地下鉄で一駅、小十郎が選んだのはビルの地下にある隠れ家イタリアンだった。表通りからは一本中に入ったところにあるので人通りは少ない。店主が顔なじみで味に信頼がおけること、そして「若い女性はイタリア料理が好きだ」という一般論を信じたのだが、の様子から料理に外れはなかったようで安心した。おいしいものを食べているときが、今まで見た中で一番いい表情をしている。もっと色々な表情を見てみたい、という欲が湧いた。
ただ、二人ともワインが飲めなかったのには苦笑した。小十郎は洋酒が苦手で、酒なら元来ビールより日本酒派だ。それを言うとメニューにずらりと並ぶワインが飲めないことに申し訳なさそうにしていたが顔を輝かせた(と思われるごくわずかな表情の変化だった)。も日本酒が好きだと言う。どこの地酒が美味しいかという話題に花が咲いた。二人の意見は「黒龍の大吟醸が一番」で一致し、それなら置いている店を知っているから今度行こうとごく自然な流れで誘うことができた。
他愛のない話をした。
同期の話、仕事の話、趣味の話。は仕事中と同じように、どこかぶっきらぼうにも聞こえる、しかしきちんとした言葉運びで話した。小十郎にもそれなりに女性経験といえるものはあるのだが、初めて食事に誘った女性とこんなに穏やかに会話ができるのは初めてだった。一年半の間、毎日顔を合わせてきたからかもしれない。
小十郎が己の趣味である家庭農園の話をすると、は困りきった(ように見える)表情であまり野菜が得意ではないと話した。食べられないものがあるわけではないが、例えば菜の花や山菜、ゴーヤなど、癖の強い野菜は苦手らしい。そんなものは調理しだいでどうとでも美味しく食べられるのだ、知らないのはもったいなさすぎる。他にも、は自分に頓着しないその性格ゆえか、休日もあまり外出しないのだと知った。修学旅行以外で旅行をしたこともないと言い、これは彼女を連れださなければという妙な使命感も生まれた。これからの季節なら、紅葉狩りがいいかもしれない。京都や奈良、箱根なんかもいいと言ったら、そのどこにも行ったことがないという。決して行けない距離ではないのに京都を知らないというのは、日本人としてやはりもったいない。
出不精である代わりに、は音楽を聞いたり本を読むのが趣味なのだそうだ。最近の気に入りを教えてくれた。音楽は洋楽やロックにクラシック、本は推理ものから歴史もの、ハウツーや漫画まで、ふだん小十郎の生活範囲内では接することのないものばかりだった。こうして自分の知らないことを知っていくのも悪くない。
そうして色々な話をして、しかし肝心なことは言い出せずに時間が過ぎた。あっという間だった。は門限などないと言ったが、女性を深夜まで引き留めるのはさすがに忍びない。
「――ごちそうさまでした、課長」
支払いを済ませて店から出ると、先に上がっていたが丁寧に頭を下げた。ぽつぽつと立つ街灯がぼんやりと照らす路地に人通りはない。危ないから店内で待っていろと言ったのに。
風が吹いて、ふわりとのワンピースの裾が揺れた。今日のはシフォン素材のワンピースで、動くたびにふわふわと揺れてどこか儚げで危うい印象を受ける。そして朝からどうしても眼が行っていたのは、髪の毛をまとめて上げているために露わになっている、白いうなじだ。先週までのは髪をまとめると言っても首の後ろで一本にくくっているだけで、今週になってからは下ろしているかハーフアップだったので、そのうなじを見るのは初めてだった。まるで水鳥のような、きれいなうなじは、正直なところ心臓に悪かった。
また風が吹く。日中はまだまだうだる暑さだったが、朝晩の風はずいぶんと涼しくなってきた。
「・・・・・・寒くないか」
「いいえ、お気遣いありがとうございます」
即答したの表情を見て、小さく息を吐くと、小十郎は鞄からストールを取り出した。今夜の為に仕事を前倒ししようと今日は早朝から出てきたのだが、家を出るときに存外肌寒かったので首に巻いてきたものだった。の目の前に立つと、ふわりとストールを首筋にかけてやる。が驚いたように眼を見開いて小十郎を見た。
「・・・・・・そうやってやせ我慢して結局風邪ひくのがお前の悪い癖だ」
首に巻かれた、ダークグリーンのストールを、が恐る恐るという風に手を伸ばして触れる。
「・・・・・・、申し訳、ありません」
「いや、謝らせたかったわけじゃねぇ」
いつもこうだ。どうも自分は、きつく物を言い過ぎる。だからが委縮するのだ。
きちんと、言葉にしなければ、伝わらない。
「――俺が。お前のそのうなじを、他の誰にも見せたくなかったんだ」
風に揺れるストールを、まるで子猫か何かのようにつついたりしていたが、その言葉に顔を上げる。小十郎を見つめる眼が、丸い。
「・・・・・・え・・・・・・?」
「だいたい今週のお前は毎日毎日心臓に悪すぎる。俺を殺す気か」
が完全に動きを止めた。
腕を伸ばす。その細い腰に触れた瞬間だけ身じろいだの、ヒールがコンクリートを打つかつりという音、
抱きしめる。
「お前がきれいなのは元からだが、それを振りまかれていらん虫を寄せ付けるのは頂けねェ。お前を、誰にも渡したくねぇ」
腕の中に、すっぽりと納まってしまったは、ぴくりとも動かない。
「なぁ、、――」
名前を呼んで、小十郎は一度から身を離した。ただし腕はその腰に回したまま。逃がすつもりは毛頭ない。
街灯が照らすは、薄暗くてもはっきりとわかるほど真っ赤だった。それこそ首筋まで赤くて、こんなはもちろん見たことがなかった。
もっと、見たことのない表情があるのだろう。
「俺は、お前に惚れてるんだ」
それを全て、知りたい。色々なものを見て、知って、感じて、それでこの表情がどう変わるのか、見たい。
「俺の傍に、いちゃくれねぇか」
ゆっくり十数える間、は固まったままだった。瞬きひとつしない。
その様子を見つめて、小十郎は嘆息し、腰に回していた腕を持ち上げた。固まったままのの頭を、優しく撫でる。
「・・・・・・すまん、お前を困らそうと思ったわけじゃない」
駅まで送る、地下鉄でいいか――視線を逸らしてそう聞こうとして、離しかけたその腕を、が唐突にがしりと掴んだ。
「っ、?」
驚いて振り返る。
小十郎の左腕を両手で掴んいるは、いまだ真っ赤な顔のまま、こちらを見つめている。
ストールが、風にはためく。
「・・・・・・これは、夢、ですか」
中学英語の例文のようなぎこちない口調。
「わたし、は。課長に、振り向いて、ほしくて。ずっと、」
声が、震えている。泣くのではないかと思って焦る。
「、」
「わたしも、貴方が、すきです」
小十郎の言葉を遮るように、はそう言った。
その言葉の意味を考えるのに一秒、
「ッ!」
もはや制御など効かなかった。
やや乱暴にその腕を引いて抱き寄せて、有無を言わさず唇を奪った。
驚いたの手から、鞄が滑り落ちる。
ここが公共の路上であるとか、色々な手順をすっ飛ばしてキスをしているとか、そういったことが全て頭から弾け飛んだのを、小十郎の中にわずかに残っていた理性が火事場の馬鹿力を発揮してなんとか回収してくれた。
口を離すと、呼吸を止めていたのか、が苦しげな息を吐く。
危なかった。
もう少しで、何をしだすかわからなかった。
「・・・・・・いいんだな、」
首を屈め、抱きしめたその耳元で囁くように言う。
「もう俺は、お前を離しゃしねぇぞ」
顔は見えない腕の中、が笑ったような気配。
その細い両腕が、自分の背中に触れたのがわかった。
「わたしも、貴方を離しません、――小十郎さん」
参った。
こいつは敵わない。
が落とした鞄と、家まで送るタクシーを拾おうという思考が生まれるまでには、もう一度理性が馬鹿力を発揮するだけの時間がかかった。
10月9日(火)午前9時55分
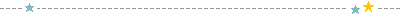
世間は連休明けであったが、システム担当は休日こそ稼ぎ時だったりする。休みで誰にも触られないうちに新しいシステムを導入したり、既存のシステムのメンテナンスを行ったりしているからだ。猿飛佐助も例外ではなく、昨日の祝日は通常通り会社に出ていたので、連休明けだという感覚はない。普通に通常運転で、朝から来月本番の新しいシステムの演算とにらめっこである。
「佐助」
よく知る声が自分を呼んだので、「なあに」と甘い声で答えて振り返った。
「・・・・・・あれ、ちゃん、かわいいかっこはもうやめたの?」
そこに立っていたのは予想通りのだったのだが、その姿を上から下まで見て佐助は怪訝そうにそう言った。
ダークグレーのジャケットと揃いのパンツ、中はライトブルーのストライプのクレリックシャツ。
「ああ、やはり仕事中は動きやすくて集中できる恰好が一番だとわかった」
いつもの仏頂面ではそう答えながら、書類の束を佐助に手渡す。システム開発の仕様書で、部署間で定めた締切は明日だったが期日前に持ってくるところはさすがらしい。笑顔で受け取りながら、佐助はおや、と思う。
今のはどうやら上機嫌だ。同じ仏頂面の中でもそれくらいの感情の機微を読める程度には、佐助はと付き合いが長い。
その顔には、先週ほどの華やかさはないとはいえ、きちんと化粧が施されている。瞬きをすれば音がしそうなほど長い睫毛、色味はなくても艶やかな唇。髪は以前と同様後ろでひとつにまとめているだけだが、以前は無愛想なヘアゴムでくくっているだけだったのに、今日はそこにリボンを模した髪飾りがついている。毛先も緩く巻かれている。
「・・・・・・どうかしたか」
思わずじっと見つめてしまったのがばれて、佐助は「なんでもないよ」と笑ってから仕様書に視線を落とした。
担当者欄に「」の判、その横に「片倉」の検印。
「ちゃん、何かイイコトあった?」
わざと仕様書から視線を上げずに問うと、が身じろいだ気配。本当にこの子わかりやすい。
「――」
背後から声がして、が振り返る。
「課長」
「会議だ、行くぞ」
「申し訳ありません、すぐに。――佐助、不備があったらメールしておいてほしい」
「はいよー」
ひらひらと手を振って、慌てたように「課長」の元へ歩くの背を見送っていたら、「課長」がこちらに視線を投げてよこした。
「!」
その視線はすぐに外され、二人はエレベーターの方へ歩いて行く。
佐助は振っていた手で頬杖をついて、息を吐いた。
「片倉、小十郎、ねェ・・・・・・」
先ほどの視線。
威嚇と言うよりは、牽制。
コレは俺のモノだ、とかそういう。
そもそも会議なんて会議室集合が普通なはずで、わざわざ他部署のフロアまで部下を迎えにくる課長がどこにいるというのだ。
「何を勘違いしてるのか知りませんけど」
独り言をつぶやいて、佐助は仕様書を放るように自席に置くと立ち上がった。
「猿飛?」
気が付いた上司から声がかかったので、にへらと笑う。
「タバコいってきまーす」
「・・・・・・程々にな」
うぃーっす、と返事をしながら、佐助は歩きだす。ライターあったっけ。切らしてたっけ。ていうかタバコ自体持ってたっけ。まあいいや途中で開発寄って、鬼の旦那にでもせびるとしよう。
「ちゃんが幸せならそれでいいのよ俺様は」
口から漏れ出たその声は、連休明けの慌ただしいフロアの喧噪に溶けて消えた。
(fin.)
+戻+
・・・はれんち裏話はこちら