※ご注意くだされ※
若干どす黒系小十郎と、真っ黒佐助注意報。
ひたすらはれんちです。
もはや「風花」設定はログアウト・・・。
本編のプラトニックな感じ(?)を大事にされたいかたはブラウザバック!
なんでもOKという心の広い方は、スクロールどうぞ↓
10月5日(金)午後10時15分
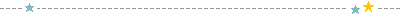
これは、出来過ぎた夢だと思った。
家に帰って、寝て起きたら、全て泡のように消えてしまう気がした。
10月5日(金)午後10時35分
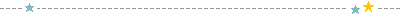
金曜日の夜、そして繁華街からは外れたところであることが拍車をかけたか、通りで待っていても中々タクシーが流れて来ず、結局携帯でタクシー会社に電話して呼び寄せることになった。
十分ほどで参ります、とオペレーターは答えたが、その十分をすでに十分経過している。
ぴたりと身を寄せるように右手で肩を抱いているを見下ろす。
「寒くないか?」
「大丈夫、です」
十五分ほど前まではその間に人ひとりが通れるくらいの間を開けて立っていたに、今と同じ質問をしたら、今と同じ返事と同時に小さなくしゃみが聞こえた。問答無用で抱き寄せて今に至る。やはりこいつの「大丈夫」は信用してはいけないと心のメモに綴ったところで、漸く一台のタクシーがやってきた。「予約」という文字と、聞いていた通りの番号が光っているのを見て、小十郎は左手を上げる。
二人の前で扉を開けたタクシーに、先にを乗せてから、身を屈めて乗り込む。
「お待たせいたしました。どちらまで?」
運転手がこちらを向いてそう聞いてきた。小十郎は隣のを見る。
「家は地下鉄沿いか?」
いつだったか聞いたことがある最寄駅を口に出して聞く。それまで小十郎の顔を見つめていたが、顔を俯けた。
「?」
首に巻いたままの小十郎のストールの裾を、両手でぎゅうと掴んでいる。
具合でも悪くしたのかと思って、その顔を覗きこむ。
「どうした?」
「・・・・・・、です・・・・・・」
顔を真っ赤にしたが、小さな小さな声で、何事かを呟いた。
「何だ?」
聞き取れなくて、耳をの口元へ向けた。
がもう一度、蚊の鳴くような声で呟く。
その言葉を聞いて、わずかに眼を見開いた小十郎は、姿勢を戻して運転手に行先を告げた。
告げた名は、繁華街の中心部にある、四つ星のホテル。
それを聞いたが、わずかに身じろぎしたのがわかった。しかしタクシーが走り出すと、ストールを握りしめていた左手がおずおずと小十郎のジャケットの裾を掴んだのを見て、小十郎は一つ息を吐くと、の腰に右手を回してこちらに身体を引き寄せる。そしてそうっと頭を撫でてやった。
10月5日(金)午後11時45分
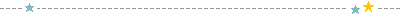
――『帰りたくない、です』
愛しい女が、顔を真っ赤に染めてそう言うのに、「帰れ」と言える男がいるなら教えてほしいと思う。
先にシャワーを済ませた小十郎は、バスローブ一枚の格好で、壁一面を切り取った窓から見下ろせる夜景を見つめている。
都会の夜空に星は少ないが、こうしてみれば地上が星空のようだ。
ちらりと視線をバスルームの方に投げる。中では今まさに、がシャワーを使っているはずだ。一糸まとわぬ彼女の姿を想像しかけて、バスルームから視線を逸らした。
広いベッドルーム。スイートである必要はないが、ツインルームで高層階のものをと告げれば、フロントの係員は上品な笑顔で「なんとか」ツインというこの部屋を案内した。セミダブル、もしかしたらダブルサイズかもしれないベッドが二つ。それでもまだ無駄に広い空間。仄暗い部屋の中で、いやに白く浮き上がるようなシーツ、そこに乱れる彼女を思い浮かべるだけで、己の欲が熱を持つのがわかる。
・・・・・・その大胆さは、意外だった。
も年頃である。そういう経験のひとつやふたつあったって何ら不思議ではないし、女が男を誘うことがふしだらだとかそんな昭和な倫理観を小十郎は持っているわけではないが、それでもまさかがああいうことを言うとは思わなかったのだ。
それも、想いを告げあった、その夜に、である。
――否、もしかしたら。
単純に、「家に帰りたくない」だけだという可能性もある。親と喧嘩中とか。品行方正な彼女が親と揉めるところは想像がつかないが、そうだと言われたほうがまだ納得しやすかった。
仮にそうだとすると、ホテルに連れ込んだのは早計だ。やはり帰した方がいいのかもしれない。
窓ガラスに映る自分の顔を見て、吐息する。
「いかんな、どうにも」
のこととなると、思考がひとつもふたつも抜け落ちてぶっ飛びそうになる。
ありがたいことには自分に好意を抱いてくれているのだから、ゆくゆくは「そういうこと」もしたいと思うのは男の性だが、別に今日今すぐどうこうしようなどとは小十郎も思っていなかったのだ。
先にシャワーを使えと言った時の、「課長が先に使ってください」と答えたあの緊張しきった顔。どう見たってこういうことに慣れているとは思えない。
「・・・・・・お待たせ、いたしました」
ぎこちない声に振り返れば、そこにバスローブ姿のが立っていた。化粧を落とした淡白な顔立ち、その感情を映さない瞳が小十郎にひたりと当てられている。
あまりにじっと見つめられたので、小さく笑いながら小十郎は言う。
「俺の顔になにかついているか?」
「いえ、その」
ゆっくりと、が瞬きをする。よく考えたら部屋のライトを付けていなかった。窓から入り込む夜景の灯りだけでも室内はぼんやりと明るいから忘れていた。どこか青白い室内において、白いバスローブ姿のは、肌の白さも相まってどこか幻想じみている。本当にそこにいるのかわからなくなるような。
言葉を選ぶように、が口を開く。
「課長――小十郎、さんが。あまりにきれいで、見惚れました」
「!」
似たようなことを考えているとは思いもよらず、小十郎は面食らってから破顔した。
「――は、ッ、お前一体俺をどうしたいんだ」
言いながらに歩み寄り、その身体を抱きしめる。すん、と鼻から息を吸えば、自分と同じにおいがした。このホテルの備え付けの、イタリアだったかのブランドのボディーソープの。
悪くない。だが、
「なあ、。やっぱりお前、今日はもう帰れ」
ぎくりと、腕の中での身体が強張った。
一度身を離して、その顔を覗きこむ。
小十郎を見上げるその顔は、まるで叱られた子どものようだ。安心させるように頭を撫でながら、小十郎は言う。
「親が心配するだろう」
その言葉に、の顔から表情が抜け落ちる。
「・・・・・・両親は、いません」
「旅行中か?」
「いえ。二人とも他界しました」
あくまで平坦な声色だった。その言葉に、小十郎の、の頭を撫でていた手の動きが止まる。
「・・・・・・それは、悪いことを聞いたな」
「いえ」
は小十郎をまっすぐと見上げたまま。その瞳の奥の感情が、読めない。
「じゃあお前、今どうしてるんだ。親戚とかと暮らしてんのか?」
「いえ、一人暮らしです」
「一人?」
「はい。大学を出るまでは里親に面倒をみてもらっていましたが、社会人になったときに独立と言う形をとって」
「一人ってお前・・・・・・」
小十郎はため息を吐く。に生活能力があるかどうかは別としても心配で仕方がない。自分に頓着しないのことだ、自己防衛の意識も薄そうである。セキュリティはきちんとしたところに住んでいるのだろうか。いや最近はオートロックが完備したマンションでも油断はできない。
「お前は俺を心配させる天才だな」
もう一度抱き寄せて、その頭に顎を置いて、小十郎は呆れたように言う。
もぞりと動いて、が口を開いた。
「申し訳ありません」
「いや謝らせたかったわけじゃねぇよ、俺が勝手に心配してるだけだ」
「・・・・・・ありがとうございます」
その言葉に、小十郎はふ、と笑う。
「わかった。じゃぁ帰れとはもう言わねェ。だから今日はもう寝な」
「ぅあ」
ひょいとを横抱きに抱えると、驚いた彼女の口から変な悲鳴が漏れた。
そのままベッドに降ろして、自分はもう一つのベッドに足を向け、
「待っ、」
そのバスローブを、が引いた。
「何故ですか、わたしでは、――相手に、なりませんか」
小十郎は息を吐いて、に向き直る。先ほどから溜息を吐いてばかりだ。
「馬鹿野郎」
その、先ほどから――バスルームから出てきたときから、強張ったままの細い肩に手を置く。
「こんなガッチガチに緊張してるくせに何生意気言ってやがる」
そして、その頭をくしゃりと撫でた。
「お前のこころの準備ができたら、いつだって嫌というほど抱いてやる。だから無理はするな。今日はもう寝ろ、な?」
「・・・・・・」
黙りこくったを、納得したものと判断して小十郎は手を離し、
――どん、と身体を衝撃が襲った。
「っ」
どこか動物的な動きで、一挙動で立ち上がったが、両腕で小十郎を突き飛ばしたのだ。
体格差から考えて、いつもならば耐えられたであろう小十郎の身体は、不意打ちによろめいて後ろのベッドに尻餅をついた。
「、何を」
ベッドに浅く腰掛けるような体勢になった小十郎の眼前に、が立つ。窓から入り込む淡い街の光だけが彼女の身体を照らしている。
逆光で表情がよく見えない。
「どう、――!」
どうしたと、そう続くはずだった口を、身を屈めたの唇が封じた。
まるでぶつけるように、無遠慮に押し付けられた、――気が遠くなるほどやわらかな、唇。
驚いて眼を見開けば、至近距離にの顔。その眼はぎゅうと力を入れて閉じられている。眉間にまで皺を寄せた様子は、およそ恋人とキスをする表情とは程遠い。
それでも、己の唇に触れる、その柔らかさは動かしようもない現実。
その感触だけで、収まりかけていた熱が再び頭をもたげるのがわかる。
これはまずい、そう思い至っての身体を離そうと腕を持ち上げたところで、唇が離れて行った。
目の前で、の双眸が光っているように見える。その底に、炎のような輝きを宿して。
「?」
「・・・・・・侮らないでください・・・・・・!」
眉を持ち上げて、こちらを射抜くような強い視線で、が唸るようにそう言った。
その苛烈な視線、そしていつもよりもわずかに低い声に、ぞくりと背筋が粟立つ。
なんて女だ。
強く、しなやかな。――気高い獣のような。
小十郎が動きを止めた隙に、は小十郎の足の間に膝をつく。バスローブの前を割り、下着を引き摺り下ろす。
「ッ、おい!」
虚を突かれた小十郎が狼狽えたような声をあげ、しかしは無言のままそこに顔を近づけ、
「っ」
その一瞬だけ、驚いたようにわずかに肩を震わせてから、
「、やめろ!」
勃ち上がり始めていた小十郎のそれに口を付けた。
10月6日(土)午前0時8分
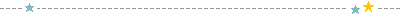
「・・・・・・ん、む・・・・・・ぅ」
モダンクラシックを基調とした調度の揃う、無駄に広いその室内に響くのは、粘性の感じられる水音と、
「ふ、・・・・・・んぅ」
己の足の間に顔を埋める愛しい女の、鼻から抜けるようなくぐもった声。
どうかしてしまいそうだと、小十郎はせり上がる感覚に耐えるように眉根を寄せる。
やめろと言った。初めの内こそ彼女を離さなければとその頭を掴んだ。
しかし見かけの割に力があるのか、まるで獲物に食らいついた獣のようにが口を離すことはなく、小十郎はあっさりと陥落した。
視線を落とせば、は小十郎の昂ぶりを中ほどまで口の中に納めて、根元に指を這わせている。
技巧など知らないのだろう、園児の落書きのように無遠慮に、予想のつかない動きで自身に絡みつく熱い舌、それとは対照的に恐る恐ると言う風に触れてくる細い指の、彼女にその自覚はないことはわかっていても焦らされているように思える感触。
この状況でまだ抵抗できる男がいるなら、そいつはそれこそ以前政宗が言っていた聖人か仙人だ。
そして小十郎はもちろん聖人でも仙人でもないごく一般的な、健全な男だ。
「――ッ、く」
先端を舌が掠めて、思わず声が漏れた。ぴくりと反応を返し、質量を増したそれに気が付いたが、そこを狙って舌を這わせてくる。
ぞくぞくと、眼に見えない小さな虫が、背筋を這っていくような感覚。
頭の中にまだ残っているひとかけらの理性が、声を張り上げる。
いけないと。彼女を止めろと。
実際に奉仕をされてやはりと確信する。はこういったことに不慣れだ。彼女の性格から考えて、おそらくは何か思いつめて、とにかく自分とことを成さなければならないと、そう考えているに違いない。
そう思えば、ただ一心不乱に小十郎を咥える、その必死な様子にも合点がいく。
「む、ふぅ、・・・・・・ン」
じゅぷ、と音をたてたのはの唾液か、己の先走りか。
――をここまで駆り立てているのは、何だ。
何がにここまでさせている。
休みなく動く頭を優しく撫で、その髪を指に絡ませながら、考える。
こういったことに不慣れであるならば、ただ単純に快楽を欲しているわけではないはずだ。
そう、そんな単純なものではない。
が纏う気配はもっと根の深く、――切実な。
祈るような、縋るような、離れ行くものをその場に留めようとしているような。
何を?
彼女は何に祈り、何に縋り、何を引き留めようとしている?
――この、俺を。
その思考が、小十郎の中で音をたてる。与えられる快感に翻弄されそうになっていた理性が、踏みとどまる。
――この俺が。離れていくのではないかと、
パズルが組みあうように、思考がひとつの筋となる。
を突き動かしているのは。
――恐怖、だ。
何故だ?
日付で言えばすでに昨日のことになるが、小十郎とは言うなれば交際を始めたばかりだ。想いを通じ合ってから、まだ数時間しかたっていない。
なのに、彼女は何を恐れているのか。
という女について、考える。
広く深い業務知識を持ち、事務職に必要な迅速・性格な業務遂行を常に行っている彼女を頼りにする者は部署内にも多い。変貌を遂げた今週は他部署からも野次馬が現れた、それほどに彼女は周りから慕われている。
ただ本人は常に無感動な様子で彼らに接しており、積極的に周りと関わろうとするところを見たことが無い。話しかければ返事はするが、必要以上の会話はしない。上司である小十郎にもまず頼らないように、他の誰かを頼りにすることはない。・・・・・・一人だけ例外が思い浮かんだが、今はそこには触れまいと明るい色の頭のその姿を頭から消す。
その様子を、小十郎は「自分に無関心」なのだと考えていた。自分自身に関心がないから、周りからどう思われるかということに興味がない。だから周りと関わらないのだと、言ってみれば極端なマイペースなのだと考えていたのだ。
だが、そこにもう一つの可能性を加えてみる。
は、他人と関わることに恐怖を感じているのではないか。
恐怖というのは行き過ぎた表現かもしれない、言い方を変えるなら、自分自身を守ろうと周りとの間に壁を作っているのではないか。
先ほど、には両親がないと聞いた。いつごろ、どういった理由でなのかは知らない。ただ、そのことがに深く根を下ろしている可能性は多分にある。
が恐れているのは、
――親しい者との離別。
「ッ」
歯が当たっての頭を撫でていた手がひく、と震えた。
が口に含んだまま、こちらを見上げる。
潤んだ瞳が、不安げに揺れている。
「すまねぇ、大丈夫だ」
だめだ。
この状態のを前に、これ以上あれこれ考えるのは不可能だ。
の暖かい口腔内でいまだ存在感を増し続ける、男の欲のなんと浅ましいことだろう。
一度落ち着かなければ、まともに話もできそうにもない。
「・・・・・・っ、、もう少し・・・・・・奥まで咥えられるか」
その頬に掌を滑らせて、小十郎は言う。劣情に、声が掠れる。
は無言のまま、言われた通りに口を進める。喉のあたりだろう、先が押し付けられるように擦れる感覚が、電流のように全身を突き抜ける。そのままがつりと奥を突きたくなる衝動をなんとか抑え込む。
「苦しい、か・・・・・・?」
がふるりと首を振る。その動きからすら快感をもぎ取ろうとする己が恨めしい。
「そのまま、吸って、根元の方は手で、・・・・・・そう、」
こんなときまでは仕事中と同じだ。道筋さえ示せば、あとは自分で邁進できる。
「――ッ・・・・・・!」
それまでぼんやりとしていた感覚が、明確な刺激となって走り抜ける。
腹の底に血が溜まっていくような感覚。
上体を支えるためにベッドについていた右手が拳を作る。シーツに皺が寄る。
――だめだ、もう、
「、ッ、離せ、出るから、」
切羽詰まった動きでを剥がそうと腕を伸ばす、しかしは抵抗するように小十郎の腰に抱きつき、さらにぢゅうと吸い上げる。
「馬鹿、お前、――ッく、・・・・・・ッ!!」
耐えようとしたが無駄だった。精道を欲が駆け上がる感覚、
「ふ、ッ」
その欲を、の喉に叩きつける。
がそれに驚いたように、口を離す。
それでも収まらないそれが勢いよく吐き出した欲の残滓が、の顔を汚していく。
「ッ、は、」
小十郎は肩で息をして、そして眦を釣り上げる。
「馬鹿野郎吐きだせすぐ!」
ティッシュはあっただろうかと考えた、その目の前で、の喉がこくりと動いた。
無意識に、小十郎は動きを止めた。
己の放った白濁で顔を汚した愛しい女が、
「・・・・・・お前飲みやがったのか」
「はい」
「はいじゃねぇよ・・・・・・」
潤んだ双眸がこちらを見上げる。
この。
馬鹿野郎。
長い息を吐いて、小十郎はの身体を抱き上げ、
「っあ」
驚いたようなの声は無視していささか乱暴にベッドに押し倒した。
「」
大きく開かれたその瞳に、自分の顔が映り込むほどの距離。
「いいんだな?」
聞くと、は躊躇せずにこくりと頷く。
「はい」
――もう考えるのは、やめだ。
小十郎は聖人でも仙人でも、ましてや精神カウンセラーでもない。
の心の底にあるものなど、が自ら話すのでなければ聞き出す気はない。
「わかった。もう止めねえ」
が離別を恐れるというのなら、直接刻み付けるまでのことだ。
そのこころも、身体も、全て。
離してやる気はないのだということを。
「――お前が嫌だと、言ってもだ」
にのしかかる小十郎の、ふだんはワックスで後ろに流している前髪が、はらはらと顔に落ちる。
その前髪の間から覗く瞳は、どうかすれば狂気じみたようにも見える、剣呑な光を湛えていた。
10月6日(土)午前0時32分
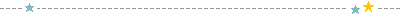
顔に飛ばしてしまった白濁を舐め取っていく。くすぐったそうに動かそうとするの顔を両側から腕で押さえつけるようにしてその口を塞ぐように口づけを落とす。
薄く開いたままだったの唇をこじ開けて、己の口に溜まっていたそれを唾液とともに流し込むように舌を動かす。
「ん、・・・・・・ふ」
歯列をなぞり、探り当てた舌を吸う。
唇を解放すると、酸素を求めるようにが浅い息を繰り返す。その口の端から、飲み込みきれなかった唾液が一筋、つうと垂れていく。
「ったく、不味いだろうがこんなもん」
「はい、驚きました」
いや、驚かれても。
相変わらず淡白なの返事に脱力しそうになりつつ、しかし小十郎はそのことに思い至る。
驚いたということは、少なくとも男の精を飲み込むなどいうことはしたことがなかったということだ。
それだけで優越感を感じられる、男とは単純な生き物だと自分でも思う。
それにしても、それならばなおさら、大胆な行動に出たものだ。
ふと嗜虐心が湧いて、小十郎はを見下ろした。
「どこがイイんだ?触ってやるから言ってみな」
見せつけるように口角を上げて言ってみると、それまでどこかぼんやりとしていたの顔がみるみる赤く染まっていく。
ああ、やはりかわいい。
「・・・・・・ッ」
じいと見下ろす視線に耐えきれなかったのかが自分の両手で顔を隠そうとし、小十郎はその細い腕を簡単に捕らえてシーツに押さえつける。
「隠すな。顔を見せろ」
逃げ場をなくしたはうろうろと視線を泳がせ始める。いつだって人の眼をまっすぐと見据えるが、だ。
「どうした?」
頬が緩みそうなのをなんとか抑える。
がもはやかわいそうなほど狼狽えているので、あまりいじめてはいけないかと思った、そのとき。
「・・・・・・その、・・・・・・はじめて、なので・・・・・・」
羞恥によるものか眼尻に涙まで溜めて、が絞り出すようにそう言った。
その言葉を咀嚼する間、小十郎は言葉を失う。
初めて、だと?
「・・・・・・お前初めてであんなことしやがったのか」
不慣れだろうとは思った。
だが、初めてとは。
の年齢、人柄を考えれば、そういう経験のひとつやふたつ、あっても不思議ではないと思っていたのに。
が泳がせていた視線を、小十郎へと戻す。
「・・・・・・そうするものだと、読んだので」
「・・・・・・」
絶句した。
一体どこで何を読んだのだ。
それを聞きだすのも面白そうな気がしたが、それよりも男を知らない身体に文字通り己を刻み付けられるのだという多少歪んだ欲の方が勝った。
「――わかった。俺が全部教えてやる。だからそのいらん知識は捨てろ」
いいな?と顔を覗きこむと、はおずおずと頷いた。
「よし」
もう一度軽くキスをしてから、その唇を顎から首筋へと滑らせる。
の両手を押さえつけていた手を離し、バスローブの前から中へと差し入れる。その下に小十郎の手を阻むものは何もない。するすると、そのすべらかな感触を味わうように掌を這わせる。
「・・・・・・下も、穿いてねぇのか」
耳元で囁くように言うと、びくりとの身体が震えた。
「そ、の・・・・・・ッ、どうすればいいか、わからず、」
シャワーを浴びながら、おそらくものすごく悩んでいたのだろうと想像に難くない。
小十郎は喉の奥でくつりと笑う。
「いい子だ」
朱に染まった耳に口づけを落としながら、バスローブの前を肌蹴させて胸元の膨らみをやわやわと揉む。
「・・・・・・ん、」
もぞり、とが身をよじるように動く。
「どうした?」
強弱をつけて揉みながらわざとらしく聞くと、揺れる瞳がこちらを見上げてくる。
「くすぐったく、て、」
「なら、これは?」
両手で、その頂をそれぞれきゅうと摘まむ。その途端、の身体が跳ねた。
「はぅ、ッ!」
「痛いか」
「いえ、痛くは、ッあ、」
爪の先でかりりと引っ掻いたり、指の腹で転がすように弄ったり、その都度の口から嬌声が漏れる。
本人は自分のその声に驚いているようだ。自由になった両手が、今度は口を塞ごうとするのを、小十郎はふたたびその腕を捕らえて制する。
「声も、抑えるな。聞かせろ」
「っひ、ですが、んッ」
「俺が聞きたいんだ」
その眼をまっすぐと見つめて言えば、もがいていたの両腕が暗示にかかったかのようにぱたりとシーツに落ちる。
もう一度「いい子だ」と囁いて、額に口づける。そして、左手で片方を弄る動きを止めないまま、もう片方を口に含んだ。
「ッあ!」
舌の先で転がし、甘噛みして吸い上げる。
「んぅ、あ、ッ、」
ひくひくと全身を震えさせるを満足げに見下ろして、今度はもう片方の頂に舌を這わせる。唾液で濡れた片方は、右手の指先でくちくちと音をたてて刺激を与えていく。
「あァ、あ、ぃや、」
「――こんなに濡らして、嫌はねえだろう」
いつの間にか下に滑り降りていた小十郎の左手の指先が、の足の付け根のそこを撫でた。ぬるりとした感触。
「ふあ、」
小十郎はそこを掬うように動かした指を、の眼前まで持ち上げる。
「見ろ、」
命じるように言えば、は閉じていた瞼をゆるりと持ち上げる。その眼に濡れた指先を見せる。
「女の身体は、興奮すると濡れるようにできてる。わかるか?」
見せつけるようにゆっくりと指を開けば、その間をわずかに粘性を持った透明な液体が糸を引いて伝っていく。
「お前は、俺に触られて、興奮してるんだ」
は、は、と浅い息を繰り返しているが、戸惑ったようにその潤んだ瞳を小十郎へ向ける。
の、こんな顔を見られるのは、後にも先にも自分だけなのだと思うと、それだけでずくりと中心が熱を持つ。
だが、まだ耐えねばならない。にはまだ教えなければならない。自分に触れられて、その身体がどうなるのか。
もう一度左手をそこへ降ろす。無意識にだろうか、閉じられようとしたの足の間に自分の身体を入れる。中指と薬指の腹で、溢れ出ている蜜を掬うようにして、その少し上、肉芽に塗りつけるように撫でると、途端にの両足が突っ張るように強張った。
「ふあ、ア!」
「ここ、が。イイところだ、」
「ぃア、あ、や、」
がくがくと跳ねる腰を抱くように押さえつけて、そこを撫でる動きを速くする。
「や、こじゅろ、さんッ、やめ、」
「やめねぇ。気持ちいいだろう?」
「ッひ、あ、変です、なに、あ、あ!」
閉じられた瞼の端から零れ落ちた涙を舐め取って、小十郎はの耳元で囁く。の不安を取り除くように、優しく。
「変じゃねえ。お前が感じてる証拠だ」
「あ、あぁ、ア、や、だめ、何か、あ、ア、」
「大丈夫だ。――イけ」
指と指の間で捏ねるように摘まむ。が腰を浮かせる。
「ッぁ、ア――――・・・・・・!!」
二度、三度との身体が大きく跳ねるのを抱きしめる。
突っ張っていた足が、シーツに沈む。全身を弛緩させたの頬に、唇に、軽くキスをして、小十郎は左の指を蜜を溢れさせているその中へ潜り込ませた。
「ッ!!」
再びの身体が跳ねる。
「あァ、いい具合だ、。わかるか?お前のナカが、俺の指に吸い付いてきてるぜ」
一本ずつ指を増やし、三本を挿入するとが腰を強張らせた。その両手が掴んでいるシーツに皺が寄る。
きつく締めつけられて、指がもげそうだと冗談交じりに思いながら、小十郎は右の掌での下腹あたりを擦る。臍より拳ひとつほど下の、そこを押さえるように。
「、力を抜け。『ここ』に意識を向けろ」
「ちから、」
「そうだ、――そう、」
が呼吸を整えるように大きく息を吸う。吐く。そのとき、膣内の締め付けが幾分弱まり、小十郎は指を進める。
「んッ」
「痛いか?」
聞くと、は首を横に振る。
「いいえ」
「なら、次だ。この奥、ナカに意識を向けろ」
「なか、ですか」
右手で押さえているの下腹を、膣内から突き上げるように、その一点を探る。
仕事中と同じく生真面目な様子で小十郎の指示通りに意識を向けているのだろう、中空を見つめていた瞳が、唐突に揺れる。
「――ぅあ!」
「ココ、か?」
挿入した指先を曲げて、見つけたその一点を引っ掻くように動かすと、が逃げるように腰を引く。その腰を抱き寄せて、執拗にそこを擦る。息もつかせぬように、追い立てるように。
「ふぁ、や、だめです、そこ、だめ」
「駄目じゃねぇ。覚えろ、。ここがお前のイイところだ」
「ですがッ、やぁ、あ、だめ、また、」
膣内の指はその一点を責めながら、親指を先ほど弄っていた肉芽へ伸ばす。の甲高い悲鳴。
「――ア!もっ、だめぇ、あ、・・・・・・ゃああああッ」
電気ショックを与えられたように反り返る身体、こぷりと音をたてて蜜が溢れだす。
「・・・・・・ッあ、ぅぁ、は、」
立て続けに与えられた二度の絶頂に、ぐったりと力を失ったの頬にキスをする。
「、大丈夫か」
焦点のあっていない眼を何度か瞬いて、は小十郎を見上げる。
「こじゅろう、さん」
舌足らずな声、小十郎はの頭をゆっくりと撫でる。
「すまねぇ、俺の方がもう限界だ」
右手での足を持ち上げて腰を進める。しとどに濡れそぼったそこに先が触れる。くちゅり、という音。
がゆるりと両腕を持ち上げる。自分を見下ろす小十郎の両の頬にその掌をそうっと添える。
その口元に、わずかな笑み。
「だいじょうぶ、です。小十郎さん、――きて、ください」
「ッ」
こいつの「大丈夫」は信用ならない、それがわかっていても。
もう、止められない。
「いらん知識は、捨てろと言ったろ・・・・・・ッ」
そのまま一息に、最奥を突いた。
10月6日(土)午前1時10分
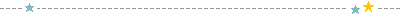
その衝撃に、反り返ってその白い喉を晒したの口からは、しかし悲鳴が掠れて音を成さなかった。
慣らしてはいたが、きつい。膣内の襞が一つ一つ絞るように絡みついてくる感覚に、小十郎は奥歯を食いしばった。
すぐさまがむしゃらに突き動かしたいという衝動を、理性をかき集めて何とか納める。
「・・・・・・、」
身を屈めて、声のないの薄く開かれた唇にキスをする。
「痛いか?」
自分でも愚問だと思った。初めて身体を開かれたのだ、痛いに決まっている。
ふるり、と瞼が持ち上がる。
涙に濡れた眼が、小十郎を見上げる。
「痛くは、ない、です」
「そうか」
やせ我慢だと、わかりきっていた。それでも今はそれに縋らざるをえない。今ここでやめろと言われてもそれは無理な相談だ。
は、と短く息を吐いて、小十郎は身を起こす。
組み敷いたの、その薄い下腹に手を当てた。
「、・・・・・・わかるか?」
情欲にまみれた声が、掠れる。こんなに余裕がないのも珍しい。行為を覚えたてのガキのようにただただ腰を動かしたくなる。
お前がそうさせてるんだ、。
瞬きをする、その瞳を覗き込む。
「お前のナカが、俺の形に広がってるのがわかるか?」
「・・・・・・ッ!!」
その言葉に、が眼を見開いた。きゅうと締め付ける圧が強くなる。
「――ふ、ぁ」
自分に埋め込まれたものを意識したからだろう、が上ずったような声を上げる。また締まる。
本当に、かわいい。
「動かす、ぞ、」
「ぁア、」
ずるりと引き抜くと、の身体が震える。限界まで抜いたところで、再び最奥を突く。
「――っひア!」
ゆっくりと挿送を繰り返す。その動きに合わせたように、の口から声が漏れる。痛みによる悲鳴に、艶が混じり始めていると、確信する。
だんだんと、動きが速くなる。
「ッ、・・・・・・!」
「あ、あ、ァあ、ッ、こ、じゅろ、さん・・・・・・ッ」
名を呼べば、呼び返してくれる彼女が、愛おしくてたまらない。
もっと。
俺のことだけを考えろ。
他に何も考えるな。
「ふ、あ、や、ソコ、はッ」
「ああ、いい子だ、覚えたな?ココがお前の、イイところだ」
先ほど弄った膣内の一点を探り当て、ぐりぐりと押し付けるように刺激する。
「や、あァ、あ、」
の口から嬌声が漏れるたびに、締め付ける力が強くなる。こちらも、限界が近い。
ひっきりなしに水音をたて、蜜が漏れ出ているそこへ指を這わせる。指の腹で、熟れた肉芽を捉える。
「――ぃあァアッ!!」
の身体が大きく跳ねる。軽く達したのだと分かったが、容赦なくそこを捏ねるように指を動かす。
「やあ!だめ、アアッ、あ――ッ!、」
休ませる気はない。
腰を打ちつける、肌と肌のぶつかりあう音。
「だめ、です!も、ヘン、おかしく、なるッ、」
「安心しろ。どこまでだって、一緒に堕ちてやるから」
優しい声色で囁きながら、しかし「いい所」だと教え込んだ場所を、ひたすら責めていく。
もはや断続的に絶頂が続いているような状態に、は涙を散らしながら、腕を伸ばす。
「こじゅ、こじゅろうさん、ッぁ、アぁッあ、こじゅうろう、さん――」
縋りつくように背に回った腕、小十郎は口角を上げる。
そうだ。
お前にはもう俺しかいないと、そのこころに刻み込め。
「、」
お前がたとえ嫌だと言っても、俺はお前を離さない。
「こじゅろう、さん、ッ、あ、あぁ、ッァあ―――!!!」
10月6日(土)午前9時18分
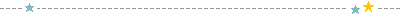
眩しい光で、眼が覚めた。
晴れた朝の清冽な光が、壁一面を切り取った窓から部屋に入り込んできている。
そういえばカーテンを閉めるのを忘れていた。窓とベッドの位置関係から外から見えるようなことはなかっただろうとは思うが、やはり昨日の自分はどうも色々とぶっ飛んでいたらしい。
腕の中に視線を戻し、
「・・・・・・起きてたのか」
ぱちりと開かれたの双眸が、まっすぐと小十郎を見上げていた。
「おはようございます、小十郎さん」
いつもどおりの、平坦な声色。
「・・・・・・おはよう。いつから起きてた」
「少し前です。小十郎さんの寝顔が可愛らしくて、見惚れていました」
どうしてこいつは、こういう歯の浮きそうなことを平気で言うのだろう。
「・・・・・・お前な、」
「ひゃ」
こうして抱きしめたり、キスをしたり、その身体に触れたりすれば、すぐに真っ赤になるくせに。
そこまで考えて、昨夜の記憶がよみがえる。
「・・・・・・、大丈夫か、身体。無理させて悪かった」
「問題ありません」
即答だった。
そんなわけあるかと心の中では思うが、しかしそれを指摘してもが頑として認めないだろう。そういうとろこは無駄に頑固だ。
ひとつ息を吐いて、の眼を見つめる。
「・・・・・・気は、済んだか」
「・・・・・・何が、でしょうか」
怪訝そうな、の顔。
小十郎はもう一度吐息。
「昨日。何か不安がってたろ。その不安を殺すために、――ああいうことがしたかった、違うか」
ぎくりと、の肩が強張る。
しまった、こういう言い方はよくない。
幾分語調を弱めて、小十郎は言う。
「責めてるわけじゃねェ。むしろ俺はそれに気づいていながら、お前を抱いたんだ。その『何か』がお前から消えればいいと思って」
が眼を見開いた。
そしてゆっくりと一度瞬いて、小十郎を見る。
「お見通し、ですね。仰るとおり、・・・・・・怖かったんです。昨日はとても、とても幸せで。実は全部わたしに都合のいい夢なんじゃないかと思って」
「そんなわけあるか。この俺が夢だとでも言いたいのか?」
小十郎の呆れたような口調に、は首を横に振る。
「いいえ、そんな。小十郎さんは小十郎さんです。・・・・・・ただ、わたしはあまり人づきあいがうまくなくて。昨日まで仲が良かったはずの人から突然無視されるようになったり、好きだと言ってくれた人が一日で離れていったりすることも、あるものですから・・・・・・、怖くて」
昨夜の予想はだいたい当たっていたようだった。
いくら取りつきにくい印象があるとはいえ、これまで周りにいた男がに興味を示さないとは到底思えなかった。これまで交際した男のひとりやふたりはいるだろうと考えていたのだ。だがは「初めて」だと言った。昨日はそれを意外だと思ったが、交際らしい交際をこれまでしてこなかったのなら、それも頷ける。
沈んだ様子のの頭を撫でながら、言う。
「それはそいつらが悪い人間だったんだろ。お前はきれいだから、悪いものは逃げ出すんだ。誰彼かまわずそうなわけはねぇ。――証拠に、あいつは、・・・・・・猿飛は。お前、仲がいいだろう」
二人で迎える初めての朝に何が悲しくて他の男の話をしなければならないのかとは思ったが、とにかく今はを納得させることのほうが重要だ。
あの男は到底信用できそうにもないが、それでものことは大切に思っているのだということが見ていて明らかだった。が彼へ、同じように思っていることも。
だからてっきり彼が昔の男であるとかそういう関係なのかと思っていたのだが。
「・・・・・・佐助は、わたしの兄のようなもの、なのです。大学を出るまで同じ里親の元で過ごしましたので」
「・・・・・・あぁ、そういうことだったのか」
これで合点がいった。あの男が、自分に向けた威嚇の意味も。
小十郎はを抱きしめる。
「俺はてっきり、猿飛はお前のいい男なんだと思ってたんだ。少なからず、嫉妬した」
「!」
が腕の中で身じろぐ。
「わかるか、。それくらい俺は、――お前に、惚れ込んでるんだ」
少し身を離して、の顔を見る。
固まったように動きを止めていたが、
「・・・・・・わたしは、なんて幸せなんでしょう・・・・・・」
そう言って、微笑んだ。
表情の変化に乏しいの。
これは、とびきりの、笑顔。
「・・・・・・ッ」
「小十郎さん?」
「お前は・・・・・・、俺を煽る、天才だな」
「は、え!?」
にのしかかって、キスを落とす。
「ちょ、小十郎さんっ」
昨日はあの後、そのまま気絶するように眠ったから、二人とも全裸だった。
その胸元に、小十郎は躊躇なく唇を落とす。
「っひゃ、や、小十郎さん、」
「言ったはずだぜ、」
ちゅ、とその頂を吸い上げてから、小十郎はを見下ろす。
「お前が嫌だと言ってもやめねぇとな」
「っぁ、ッ、それって、今日も、なんですかッ!?」
「何言ってんだお前、この先ずっとだ」
「ぇえ!?」
眼に見えて狼狽えるの様子が、可愛らしくて仕方がない。
「その、でも、っ、ここの、チェックアウト、とか、ッ」
「お前はそんなもん気にしないでいい」
ツンと芯を持ち始めたその頂を指先で引っ掻きながら、小十郎はくつくつと笑う。
その双眸が光を宿して、を捕らえる。
「お前は俺のことだけ考えていろ」
「そん、ッぅ」
「嫌々言ってるがココは喜んでるみたいだな」
「ぁうンッ!ひゃ、や、そこ、」
「まあ安心しろ。歩けなくなったって、俺が抱いて帰ってやるから」
「そんなっ、ぁ、ぁあ、ッ」
――それから、どれくらい時間がたったのかもわからない。
何度も何度も絶頂の淵に落とされて、息も絶え絶えには言った。
「・・・・・・小十郎さんがそんな、ずるい人だった、なんて・・・・・・」
「何だお前、今更気が付いたのか?」
答えた小十郎の声は、至極楽しげだった。
10月16日(火)午後7時25分
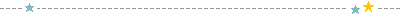
エレベーター横の休憩スペース、がこんと音をたてて落ちてきたコーヒーを自販機から取り出して、小十郎は一息吐いた。
ブラインドの降りた窓の向こうはすっかり夜景だ。すでにフロアにも人影は少ない。も先ほど退社した。
コーヒーのプルタブを開けながら、考える。来月発売の新商品の研修会は週明けだ。この週明けというのがミソで、全社向けの資料を今週中に作成できなければ休日を返上しろというスケジュールなのである。
この週末は、と出かける約束をしている。何が何でも、金曜までに仕上げなければならない。
まだあと三日ある、なんとかなるだろうと考えたところで、自販機のがこんという音に顔を上げた。
「あ、片倉の旦那。どーもー」
間延びした声、明るい色の髪。
「・・・・・・こんな時間に別フロアに用か」
「いや、これがさ。うちのフロアの自販機には置いてないもんで」
相変わらず張り付けたような笑みを浮かべる男だ。猿飛佐助はにいと笑って、自販機から取り出した缶を小十郎に向ける。
リアルゴールドの黄色い缶に、わずかに眉を動かす。
小十郎の様子には構わず、佐助は缶を開ける。ぷし、という音。
なんとなく、聞いてみる。
「お前そんなもん飲むのか」
「炭酸がさ、飲みたかったから」
既視感を覚えるような言葉が返ってくる。やはりこの男は気に入らない。
一口飲んでから、佐助が小十郎に視線を向けた。
「うちのが、いつもお世話になっております」
わざとらしい敬語に、小十郎は不快げに眉を上げた。
「テメェのじゃねえんだろう。独立したと、あいつは言っていた」
声を低くして言う。自分のこういう声は、ともすればカタギらしからぬ迫力があることを、小十郎は自覚している。
しかし佐助は捉えどころのない笑みを浮かべたままだ。
「あは、怖いねェ。ま、それはそうなんだけどさ、だからって誰彼かまわずあの子に手ェ出していいわけじゃないってこと」
口元は笑っているのに、眼が笑っていない。
小十郎は口角を上げて、佐助を見下ろす。
「つまり、あいつを奪い返すとでも言いたいわけか?」
「まっさか。あの子が幸せなら俺様それでいいんだよ?シアワセなら、ね」
佐助の双眸に、昏い光が宿るのが見えた。
「ここまで蝶よ花よと大事に育ててきたのはどこの馬の骨ともわかんない奴に触らせるためじゃないんだ。近寄ってくる蛆虫を排除するのはそれなりに大変だったんだからさァ」
「・・・・・・成る程、テメェの仕業か」
話が、つながった。
は、離別をひどく恐れていた。親しかったはずの者が唐突に離れていくことを何度も経験したようだった。それは、つまり。
「一匹二匹ならまだいいけどさ。あの子かわいいから。一人ひとりそれぞれ潰していくのって結構骨が折れるわけよ」
佐助の仄暗い笑顔を、小十郎は表情一つ変えずに見つめる。
「で?俺を同じように排除してみるか?」
そう聞くと、佐助はにこりと笑った。
「今はやめておくよ、言ったでしょ。が幸せならいいの。ただ、傷つけるようなことがあったら、」
底冷えのするような笑顔だ。
が対人関係に不安を覚えるようになった原因を作っておきながら、どの口がそんなことを。
そう思いながらも、小十郎はにいと口角を上げた。
「そういう意味ならテメェは用無しだ、安心しろ。――それに俺はテメェに礼を言わなきゃならねぇな」
この男の愛情はひどく歪んでいる。だが。
「あいつに男を近づけないでいてくれた、そのことには」
自分もあまり、人のことは言えない。
佐助がわずかに眼を見張り、飲み干した缶をゴミ箱の方を見もせずに放った。
黄色い缶は、示し合わせたように「空き缶」と書かれた箱に着地する。
「アンタとはちょっとは気が合いそうだ。ま、そういうわけだから。あの子のこと、よろしく頼むよ『片倉課長』」
へらりと笑って、佐助はふわふわとした足取りでその場を後にする。全体的に掴みどころのない、妙な男だ。
「・・・・・・言われるまでもねェ」
つぶやいて、歩き出しながら背後に缶を放る。
ブラックコーヒーの黒い缶は、綺麗な放物線を描いて、「空き缶」のごみ箱に収まった。
(fin.)
+戻+