男女逆転大奥パロの、雰囲気小話です。
配役は春日局=佐助、家光(女)=夢主。家光(本物)は幸村そっくりという設定。
死ネタぽかったり、才蔵視点だったり、名前変換がなかったり(そもそも夢小説と言えるのか怪しい)、佐助が病んでいたりとやりたい放題です。
何でも大丈夫!という方はスクロールどうぞ。
原作のような仄暗さ・薄暗さが少しでも伝わると、幸いです。
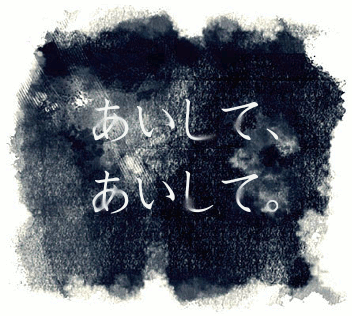
涙なんて、とうの昔に捨てたんだよ。
霧隠才蔵の、それは古い記憶だ。そのころはまだ、ほんの童であった主人に向けて、彼がそう話しているのを見ていた。
ああでも、もちろん流そうと思えばいくらでも出るよ?今すぐ号泣してみせようか。
絵巻でも読んで差し上げましょうか、と言うのと同じくらいの気安さでそう言った彼に、幼い主人はその可愛らしい眉をひそめたのだ。
――やめておけ。なみだとは、ひとがうれしいとき、かなしいときに、それがこころのなかでどくにならぬよう、ながすものだ。
年端もゆかぬこどもに諭された彼は、しかしふわりと笑った。
心配してくれてありがと。でもダイジョーブ、俺様ひとじゃないから。
「ひとではないから」は彼の口癖のようなものだった。それを言うたびに主人は怒ったものだ。主人は彼を、自分たちを、どうしても同じひととして扱いたかったようだ。しかしあれから十年以上がたった今も、彼はそれを受け入れてはいない。他の命令はどんなものでも、恐らくは「今ここで死ね」というものであっても(万が一にも主人がそのようなことを言うとは考えられないが)、なんだかんだと軽口の不平を言いながらも最終的には必ず従ってきた。彼は、己が主人と同じ「ひと」だという事実を、ひどく恐れていた。
だから、今も。
「・・・・・・嘘、だろ。ねえ。旦那。起きてよ」
開ききった瞳孔、震える声。穏やかな笑みを浮かべる、美しくも溌剌とした美丈夫であったかつての面影はない、醜く、赤黒く腫れあがったその顔を見下ろす彼の眼には、それでも涙はない。
――後は、任せた。そなたは生きよ。
彼に、そう最後の命令を下して、ぱたりと褥に落ちた、顔と同じく変色した腕。
「起きてよ、旦那。いやだよ。ねえ。ねえってば」
その、震える指先が、主人の頬に触れる。ねえ。旦那。譫言のようにそう繰り返す。
瞬きすらしない。眦が裂けそうなほど見開いた瞼から、ごろりと眼球がこぼれるのではないかと思った自分は、これでも動揺しているのか頭がおかしいのか。おそらく後者だろうと思う。彼に仕える自分も、彼と同じ。ひとではない。
「ねえ、嫌だよ、やめてよ、置いて行かないで」
彼は、望みというものを持たなかった。欲するものなど何一つなく、彼自身の生命すら「目的」の前には紙切れより軽かった。
彼の目的はただひとつ、主人の幸福。
幸せの何たるかも知らないくせに、ただそのひとつの目的のために生きていた。それは希望などという綺麗な言葉では到底表すことのできない、彼のたったひとつの生きる意味、あえて名をつけるなら、
――妄執。
その彼が、ここまで誰かに――主人に、願いの言葉を口にするところなど、見たことがなかった。
嫌だよ。起きて。まるで呪詛のように彼は繰り返す。そうしていれば死人も歩くと信じているように。やめて。いかないで。起きて。ねえ。
「ひとりに、しないで」
そこまで言って、彼が口を噤む。
そしてその場に静寂が落ちた。
彼も、自分も。主人も、主人の侍医も。誰も、何も言わない。
つい先ほどまで聞こえていた、病に侵された主人の苦しげな吐息の音は、
もう、ない。
「・・・・・・、佐助様」
見かねた侍医が、腰を上げかけ、しかしそれ以上の言葉を発することはなかった。
どこか獣じみた、電光石火の動きで抜いた脇差の刃が、寸分違わずその心の臓を突き、血油にまみれた切っ先が背中に突き出ている。
逆手にその脇差を握っている彼は、しかしそちらを見すらしていない。まるでただの穴のような、茫とした双眸は、ただ主人の顔に向いている。
ずるりと刃を引いて、侍医の骸が崩れ落ちるのをやはり見もせず、その返す刀で躊躇なく己の首に刃を当てた。
侍医の生命を奪ったばかりの刃は彼の首の薄皮一枚を裂いて、つうと一筋、血が垂れ落ちる。
ひとにあらざるとはいえ、その身に流れる血はやはりひとと同じ色なのだなと、どこか他人事のように思った。やはり自分は頭がおかしい。
彼がそこで、動きを止めた。
生きよ。
最期の最後に、主人が彼に下した命令。
主人の命令に背く術を、彼は持ってはいなかった。
――そうして、三代将軍・家光はこの世を去った。
誰よりも彼の傍らに仕え続けてきた、ひとりの側用人を残して。
幕府開闢から、三十年がたとうとしている。
関東一円に広がっていた流行病は、いよいよ大坂、西国にも手を伸ばさんとしていた。
十代後半から二十代前半にかけての、若い男子だけがかかるその病を、人々は「赤面疱瘡(あかづらほうそう)」と呼んでいた。天然痘に似て致死率の極めて高いこの病にかかると、読んで字のごとく、赤い発疹で全身が爛れ、膨れ上がるのである。戦国の乱世が漸く終わりを告げ、泰平の世の営みを始めんとしていた人々は、謎の奇病にただ恐れることしかできなかった。どんな高名な医師でも匙を投げ、原因すらもわかっていない。人から人へ伝染するのか、何を介して伝染するのか、それすら。
病が狙うは必ず男子。
それは農夫の子であっても、商人の子であっても、譜代の大名家の嫡子であっても、
――そして当代の将軍であっても。
その猛威は、何ら変わることはなかったのである。
静かな、静かな夜だ。
政の中心たる江戸城であるが、奥に近いこの辺りはすでに人払いを済ませている。
野犬の遠吠えも、風の音もない。
秋も深まっているというのに、虫の音ひとつ聴こえてこない。
耳が痛くなるような、完全なる静寂。
「――『これ』、捨てといて」
漸く、佐助がぽつりと、そう言った。
力なく降ろされた彼の右手には、血油にまみれた抜身の脇差が握られたままである。すぐ隣には、胸元を緋色に染めて仰向けに倒れている男の姿。心の臓を正確に一突き。どれほどの動揺に侵されても、ひとを殺す刃筋は一寸たりとも揺らぎはしなかった。それがこの、猿飛佐助という男なのだと、才蔵は知っている。
そして、その佐助が。
才蔵の知る限りでは初めて、取り乱しているのだと、理解している。
「・・・・・・お匙(さじ:医者のこと)ひとりを殺したところで、何も変わりはしませんよ」
もしかするとこの場で自分も殺されるのかもしれない。
それはそれでいいのかと、才蔵は思っている。
才蔵が忠誠を誓っているのは幕府でもなければ徳川将軍家でもない。家光公には親しく接してもらったしそれなりに恩義もあるが、それでも才蔵が仕えているのはこの猿飛佐助ただひとりなのだ。この生命はもとより佐助のために使うもの。ならば奪うのは佐助の自由だ。
佐助は、眼の前の褥に横たわる「それ」を、ただ見つめている。
否、実のところどうなのかはわからない。その瞳に存在するのは、ただただ空虚だけ。視線の向きは確かにそちらに向いているのだが、見えているのかどうかは定かではなかった。
家光公も無体なことをなさると、才蔵は考えていた。
佐助がただ、家光のためだけに生きていたことを、知っていたはずなのに。
生きる目的を奪われた「ひとならざるもの」に、生きろとは。
「いかに人払いしていようと、家光公の死を隠し通せるものではない。それは長もわかっておいででしょう」
もはや、これまで。
この先家光を失った佐助が生きながらえるとは思えない。主人の命令には逆らえずとも、生きようとしなければどうとでも死ねる。
そして自分には、佐助の死後を生きる気は毛頭ない。
さあ殺せ。
今すぐここで。
わざとらしく、平時のように口元に緩やかな笑みを浮かべて、才蔵は佐助を見る。
「家光公は、もう、死んだ」
その瞬間、佐助の双眸が光を取り戻した。
狂気じみた輝きを瞳の奥に宿らせて、こちらをぎらりと見据える。
佐助も才蔵も、もともとは忍びであった。
家光が生まれたのは天下分け目の大戦から数年、神君・家康が京の帝より征夷大将軍を命じられ幕府が開かれたとはいえ、まだまだその力は盤石ではなかった時分のことだった。徳川家は幼き世継ぎの身の安全のため、乱世に暗躍した忍びの里から常に護衛を雇い入れていた。佐助はその、最後期に雇われた忍びのひとりである。幼い主人に対し、佐助自身もまだ少年と言える年頃ではあったが、しかし彼はその歳ですでに生粋の忍びであった。たとえ戦がなくとも、戦忍びとして訓練された腕は確かで、己を闇に生きるものと自覚し、ひたすら主人の影に潜んだ。
それを光の下に引きずり出したのが主人である家光である。
友のように、兄弟のように佐助を慕い、ただの草であった彼に「猿飛」の名を与え、彼がどれだけ嫌がろうとも「ひと」として接した。
将軍職を継いでからは、才蔵もろとも側用人として召し抱え、武家よろしく裃まで設えて、決して踏むはずのなかった表舞台を踏ませたのだ。
幕閣の中にはもちろんそれを面白くないと思う者もいたが、どんなときでも佐助は優秀であった。乱世は終わったとはいえ、政の中枢を担う者たちはいずれも戦国の戦場を駆け抜けた武士(もののふ)であり、優秀な者に対しては素直に称賛する手合いも多い。おかげで佐助も才蔵も彼らと打ち解け、ともに家光を、徳川将軍家を守って行かんと団結した。関東に奇病が蔓延し、家光が倒れたのは、その矢先のことであった。
ゆらりと、水の中を揺蕩うように、佐助が動く。
その右手の刃が、己の身体を刻むのを、才蔵は待つ。
「――・・・・・・才蔵、」
刃は、この身に届かなかった。
佐助は懐から、紙を取り出していた。
刃の血油を拭き取って、鞘に納める。きん、という涼しい音。一連の所作は、まごうことなく武家のそれ。身に着けたのはもちろん、家光の傍に在るため。
「『上様』は、死んじゃいないよ」
ぴくりと、才蔵は眉を動かした。
身体の前に、こころが壊れてしまったかと一瞬考えて、そして気づく。
佐助は家光を、「上様」とは呼ばなかった。ただの一度も。
「仰ってる意味がわかりかねます。家光公は死んだ、そして世継ぎのない徳川家は途絶えることになりましょう」
「それがわかっているなら、死んだなんて口にするな」
佐助が、こちらを見た。
その双眸を彩っていたはずの狂気が霧消している。何故。
「今、将軍が逝去したなんて言ってみろ、いまだ天下を狙ってる連中がこぞって江戸に攻め込んでくるぞ」
その軽妙にも聞こえる声色は、いつもの佐助そのもの。
もちろんこちらも、忍びとして鳴らした技術は健在だ。顔色一つ変えていない。
だが佐助はこちらを見て、にいと口角を上げた。
「なんだよ、俺様がお前を殺すとでも思ったか?これから忙しくなるんだからそう簡単には楽にさせないよ?」
「忙しく、ですか」
今の今まで死人のように蒼白だった顔色に、血の気が戻ってきている。
その顔に、いつもの人好きのする笑みを張り付けて、佐助は言う。
「当たり前でしょ、まずは影武者、これはもう小介でいいやあいつなら背格好もだいたい同じだし。今すぐ小介呼んで。とにかくことがバレてまだ病が届いてない西国の馬鹿どもに攻められでもしたら目も当てられない、上様には生きててもらわないと」
ぺらぺらとよく滑る舌だと、頭の隅で思いながら、才蔵は平静に努める。
「それではこちらの『ご遺体』は、」
「ああ、もういーよ小介ってことにしよう。アイツもう死んだことにすればいい」
「ですが、仮に影武者をたてたとしても、徳川家の血筋は」
才蔵の問いに、佐助が小首を傾げた。
「・・・・・・そっか。お前知らないっけ」
佐助がにこりと笑う。
「上様には、江戸の町娘に産ませた姫君がおありだ」
「は?」
思わず聞き返してしまった。
御台所がありながらもなかなか手を出さない、あの奥手だった家光が。江戸の町娘に、産ませた姫君?
にわかに信じられず眼をしばたかせた才蔵に、佐助が眉を下げる。
「やー、あのときはほんとくだらない売女に騙されたもんだとひやひやさせられたよ、速攻殺してやろうと思ったのに止められてさァ。でもま、結果的にはあの時殺さなくて正解だったよ」
生まれた子が男児であれば、家光がどう言おうと殺されていたのだろう。何しろ御台所や側室方には子が無い。落胤の存在が明るみに出て権力闘争にでも発展すれば面倒なことになる。
初耳ではあったが、この場で佐助が嘘を言うとは思えない。才蔵はとりあえず頷く。
「・・・・・・それで、その姫君とやらは」
「上様のご厚意で、乳母までつけて江戸の外れの屋敷に暮らしてる。その姫さんに世継ぎを生ませて四代に挿げれば何の問題もないだろ?」
ああ、こういうところは昔と何ら変わらない。
どれほど重大な、深刻な内容を話していようと、この男にかかれば明日の天気の話のように軽いものに聞こえてくる。明日の天気など占ったところで当たる確率は五分、晴れようが雨が降ろうがどうでもいい。そのような軽さだ。
「そうと決まれば善は急げだ、陽が昇ったら早速迎えに行かないと」
どこか、揚々としているようにすら見える軽い足取りで、佐助が部屋を出ていく。
才蔵はそれを目で追ってから、短く息を吐いた。
先ほどから、佐助は目の前の主人の亡骸を一度も見ていない。
あれほど取りすがった主人を。
「・・・・・・」
何にしろ、これから忙しくなる。
江戸城内はもちろん幕閣たちにも、真実が告げられることはないだろう。
最小限の頭数で、将軍逝去を隠し通さねばならない。
正直なところ、このまま戦国乱世に立ち戻ってくれた方が、才蔵としてはありがたかったりするのだ。
どれだけ武家として扱われようが、やはりこの身に流れる血は修羅道を行く忍びのもの。血で血を洗う、あの冷たい闇の世こそが生きがいを得られる場なのだ。そしてそれは、佐助とて同じである、はず。
だが。
「・・・・・・ま、仕方ないですねえ」
もう少し頑張ってみるとしましょうか。
間延びしたようなその声が、静寂の中に溶けていく。
室内には物言わぬモノが「二人」、才蔵の声に応える者はない。
翌日、その日もこれまでと全く変わらない様子で、陽はいつものように高く昇った。
先導する佐助が立ち止まったので、才蔵は部下たちに止まるよう命じる。
佐助の言葉通り、江戸の外れにその屋敷はあった。
ある程度の扶持は与えられているらしいが、それでも手入れを行き届かせるほどの余裕はないのだろう。方々に伸びた木々で静謐な屋敷が隠れてしまっている有様は、これが夏場であれば鬱蒼とした雰囲気を醸したのだろうが、今は秋。
夕陽を思わせるように色づいた木々の葉が、見事な錦を織りなしている様子は、ここが外れとはいえ市中であることを、しばし忘れさせるほどだった。
前を行く、終始上機嫌な様子の、その紅葉と同じような色をした頭に視線を向ける。彼の眼にはおそらく、この見事な紅葉も入ってこないに違いない。その頭の中に在るのはただ。
「――じゅーなな、じゅーはち、」
朽ちて崩れかかった門をくぐったところで、女童の高い声が聞こえてきた。
「じゅーく、」
風が、吹く。
ざあ、と一斉に葉擦れの音が鳴り、夕陽の色の葉が舞い上がる。視界を、その錦の色が染め上げる。
「にーじゅっ」
「・・・・・・才蔵、」
舞い散る葉から庇うために顔の前に腕を上げていた才蔵の耳に、佐助の声が聞こえた。
「長?」
「見てよ、才蔵・・・・・・!」
その声色は、名を付けるとすれば感嘆、だろうか。
佐助は常に、巧妙に感情を隠す。普段彼が纏う軽妙な物腰は、すべてそのこころの内を明かさないためのもの。その彼にあって、このような声色は極めて珍しいことだった。
風が収まっている。才蔵は腕を下ろして、見た。
小奇麗な身なりの少女だった。歳は十を数えたところであろうか。
「ちょっと、目元なんて上様にそっくりじゃない?眉の感じも、耳の形も!」
この距離で振分髪にかくれた耳まで確認したのか。
呆れ混じりに、引き連れていた部下たちに手で合図する。帯刀した部下たちが、ぞろぞろと屋敷に入っていく。
草の生え放題なその庭は、ここが草原であるかのような錯覚を見せた。
はらはらと舞い散る紅葉の中、少女が佐助を見上げる。
少女の前まで歩いた佐助が、膝をついて目の高さを合わせる。
「・・・・・・だれ、ですか?」
ぱちりと瞬きをして、少女が一歩後ずさる。見知らぬ大人に警戒しているのだろう。その両手で抱えている毬を、佐助は見る。
「二十もつけるなんてスゴイね。いっぱい練習したの?」
褒められたのだとわかって、少女が笑う。
――太陽のような。
「!」
息を呑みこんだ。
眼も鼻も口も、耳もどうだか正直才蔵にはわからない。だが。
この笑顔は、
「うん、れんしゅうした!つぎはさんじゅうできるようになるよ」
まるで。
「・・・・・・そっかぁ」
ふわりと笑って、佐助が少女を抱き上げる。
「あ!」
驚いた少女の手から毬が滑り落ちる。それには目もくれず、佐助は笑顔のまま、門の方へ歩き出す。
「帰ろう、上様」
「なに、まって、やだおろして、かあさま!」
少女が逃れようともがく。屋敷の方へと小さな両手を伸ばす。
「かあさまっ!」
「やだな、上様。上様の母上様は、もう三年も前に病で亡くなられたでしょ?」
その一点の曇りもない笑顔の不気味さを、幼いながら察したのかどうか。
「・・・・・・やだ・・・・・・や!かあさま、かあさまっ!!」
火のついたように少女が泣きだし、そしてそのとき、屋敷から絹を裂くような女の悲鳴が聞こえた。
その悲鳴に、少女がぎくりと身体を強張らせる。
少女からは見えない角度で、佐助がこちらを見る。その温度のない目。
才蔵は苦笑して頷く。
まったく、音はたてるなと厳命したはずだ。ただでさえ流行病のおかげでこういう荒仕事ができる男が減ってきているというのに、どいつもこいつも使えない。そう思いながら腰の刀に手をやる。どうせ盗人に仕立てて処刑の予定だった、殺すのが今になったところで特に問題はない。
「かあさま!まって、いまのはかあさまのこえだった!かあさまっ!やだはなしてェッ!!」
「大丈夫だよ、上様。怖いことなんかなんにもない」
屋敷の方へ足を向けた才蔵とすれ違う、佐助は笑顔で腕の中の少女の顔を覗きこむ。
「ね、上様。帰ろ?大丈夫、母上様の分もぜんぶ、」
才蔵はそれを視線の動きだけで追った。
佐助のその笑顔は、作ったものではない。
生前の主人に向けていた笑顔、そのもの。
「ぜんぶ、俺様が――愛してあげるから」
そうだった。
理解はしていた、はずだったのだ。
この男は、主人を失って壊れたのではない。
――もともと、壊れていたのだった。
(これはおわりのはじまりか、それともはじまりのおわりか)